弦楽器 Q&A
弦楽器に関するいろいろな疑問にお答えします。
2023年12月31日をもちまして、新規投稿・コメントの書き込みを終了させていただきました。
5203件のQ&Aがあります。
Q:Vn.アジャスター
投稿者:D.O. 投稿日時:2006/08/07 20:34 ---225.78.19
失礼します。
一つお聞きしたいのですがヴァイオリン用アジャスターでフレンチタイプ?(ボールエンドも付けれる物でネジ部分がテールピースより前に出るタイプなのですが、そういう名前で良いのかどうかも…説明が解りにくいでしょうか…)なのですが、これは今でも作っているのでしょうか?
今はアジャスターはE線にしか使っていませんし、ループしか使うつもりは無いのですが、もし比較的容易に手に入るならぜひ一つ欲しいと思っています。
どうも上手く見つけられず、皆さんご存知でしたら一つお聞きしたいと思って質問させていただきます。また、お使いの方がいらっしゃいましたら感触なんかお聞きできると嬉しいです。
よろしくお願いします。
投稿者:杏 投稿日時:2006/08/07 21:34 ---226.141.59
こちらに写真があるものですよね。
http://www.sasakivn.com/werkstatt/qa/violastimer.htm
製造中止になったと5年ほど前に聞いております。中古で一個譲っていただいて、とても使いやすいので、もうひとつ欲しいのですが、、復活しませんかねえ、、
投稿者:D.O. 投稿日時:2006/08/08 02:25 ---225.78.19
有難う御座います。
そうです、これです!!
なるほど、もう作ってないのですか…残念です。
使いやすいですか、なかなか良く見えるもので結構優秀なんじゃないか?と思っているのですが、やっぱり良いですか。
う〜ん、かなり復活してもらいたいです(苦笑
…正直、FIXより良さそうに見えるんですけどねぇ(失礼
有難う御座いました、知人で誰か持っていないか聞いてみようと思います。失礼します。
Q:4/4と7/8サイズの間の楽器について
投稿者:ミニミニ 投稿日時:2006/08/02 19:42 ---80.69.129
今までずっと4/4のヴァイオリンを使用していた者です。
知人の小ぶりなヴァイオリンがフィットしたので同じような物を探しております。サイズは4/4と7/8の中間のサイズです。
7/8は最近よく売られるようになったようですがこのサイズはどんなメーカーで売られているのでしょうか?
投稿者:ストラッド店員 投稿日時:2006/08/04 15:38 ---192.41.135
こんにちは、
>サイズは4/4と7/8の中間のサイズです。
少し調べてみたのですが、いわゆる大手メーカーではこのサイズは見当たりません。
恐らく、個人製作者が特注で作った物と想像できます。
それでは!
投稿者:ミニミニ 投稿日時:2006/08/05 10:06 ---80.69.129
そうなんですか。
レディースサイズの楽器は特注以外ではないんですね。
ありがとうございました。
投稿者:弦喜 投稿日時:2006/08/05 10:46 ---6.34.143
もう、スレ主さんは見られないかもしれませんが、以下情報です。
メーカー名、ブランド名となりますが、少なくとも下記には7/8のラインナップがあります。(日本、ドイツのメーカーではありません。)
Gliga
Henri Delille
Stentor
またgoogle などで violin 7/8 をキーワードに探すとある程度目星が付けられます。
中国製の楽器でも、7/8を標準的に作っているメーカーを見た覚えがあります。
投稿者:弦喜 投稿日時:2006/08/05 11:13 ---6.34.143
分数楽器のサイズはあまり明確に規定されていません。
例えば、Gligaですと、7/8の楽器のボディー長は348mmほどありますので、国内メーカーの3/4サイズのボディー長332mmと4/4サイズのボディー長355mmから考えると、かなり4/4寄りのサイズと言え、いわゆるレディーサイズと呼んでいいと思います。
お友達の楽器のボディー長はどれくらいなのでしょうか。(ボディー長とは、裏板側でネックを取り付けるための出っ張り:ボタンと呼びます、を除いた縦の長さです。)
クレモナの多くの楽器(グァルネリやグァダニーニ)で4/4サイズに属するもので350〜352mmといったものもありますので、結構レディースサイズという定義も曖昧です。
投稿者:はりせん 投稿日時:2006/08/05 13:12 ---46.20.220
うちの娘がこういう質問をするとパパとしては背中を見せて根性教育をします。
えーと、ストラッド在庫で7/8と明記してある
va-0265が348 mm
であることを考え、通常のサイズを355mmとしてみると
中間は、351〜352mm。
ストラッドの在庫品をすべて見るとこれに当てはまるモノは
va-0015の351mm
va-0110の352mm
va-0131の352mm
va-0150の352mm
va-0203の352mm。
少ないね、なぜ少ないか分かる?
で、サイズを大きくしたとき音が良くなったのを覚えてるでしょ。いい音のバイオリンを作ろうとすると、大きく作る方が作りやすいわけ。でも弾きにくくなっては本末転倒なので355ミリかそのちょっと大きいくらいで収めるわけ。また、大きさが数ミリ小さくなっても材料費も職人の手間もほとんど変わらないからあえて小さいのを作ろうという誘因も働かない。
でも栄養状態のせいか体位が今より小さい人が多かった昔のバイオリンは小ぶりのものが今より多かったかもしれないね。(ということは高いということか?そういえば上の5本。パパ買って、といわれると少々きついものが一部混じっているなあ。)
投稿者:弦喜 投稿日時:2006/08/05 16:55 ---6.35.47
>>はりせんさん
想像での話を常識のように書き込むのはどうかと思います。
ヴァイオリンの生い立ち、歴史、そのなかでの重要な登場人物・商売としての思惑・市場での評価の推移・時代や演奏者が楽器に求めるものの推移などを、もう一度勉強されてはいかがでしょうか。
355mmという数字がなぜベストなのか論理的に説明した資料を私は見た事はありませんが、歴史を見ればその値が今標準とされている背景がある程度見えてきます。
投稿者:はりせん 投稿日時:2006/08/07 20:04 ---46.20.220
当掲示板はあくまでQ&Aですから、推測は書かない方がいいですね。失礼しました。
私の推測ではなぜ弦長が際限なく長くならないのか、が分からないという欠陥があるのは自覚しております。パガニーニのカノンがネックを継ぎ足した分だけ長いという噂は聞きますが、本物のデータは分からない。では、とフルコピーと銘打ったものを参考にしようとしても、弦長はノーマルと同じです、という話だったし。千住真理子はデュランティのネックをすげ替えようと思ったが止めたと言っているが、じゃあ何ミリ?も資料がない。
ここで元の質問に戻ると、弦長を数ミリ短くするだけならネックをすげ替えたら?(あるいはネックの根元を削ったら?)という回答はありうるもんなんでしょうか。
投稿者:弦喜 投稿日時:2006/08/07 23:02 ---6.34.38
最初の質問からはずれ申し訳ありませんが、書き込みをさせていただきます。
>>はりせんさん
カノン砲のボディーサイズをお知らせします(CD&資料のセットが販売されていますので)。
ボディー長(裏板側):353mm、ストップ長:197mm、ネック長:129mm
デル・ジェスの写真集で十数台のサイズの載っているものがありますが、351mm、352mmといったボディー長のものが結構あります。
1700年前後のオールド名器達が産声を上げていたころには355mmが標準などと思っていた製作者はおらず、その工房、製作者により一番よいと思うサイズのものを試行錯誤の中で作っていたと思います。ストラディヴァリでさえ、360mmを超える楽器を作っていた時期があったのですから。
私見ですが、No.1=ストラディヴァリウスの黄金期の楽器!、ストラディヴァリ信奉者で楽器商兼製作者兼研究者のJ.B.ヴィヨーム、バロックからモダン楽器への改造、名人はこぞってストラド弾きに、演奏は高度になり演奏互換性重要に、などが、キーワードではないかと思っています。いったん主要な部位のサイズの標準化が進んでしまうと、非標準品は互換性のなさ故に楽器の持ち替え・買い換えの障害となり、どうしても嫌がられます=売りにくくなります。
傾向としては、楽器が大きくなり容積が増えると低域含む音量が出やすくなると思います。しかし、音色の良さと楽器の微妙な大きさはとくには関係ないように思っています。
サイズが標準よりかなり小さくなったとき重要なのは、ネック長とストップ長の比が2:3であることでしょう。この比率が守られていれば、標準の楽器から音程間隔が若干狭くなっただけのものとして演奏できます。これが狂っていると、正しい音程はその楽器でしか弾けない、なんてことになる可能性大です。
Q:ヴァイオリン。
投稿者:小雪★ 投稿日時:2006/08/04 00:23 ---204.209.105
こんばんは、初めまして。小雪と申します。
実は、最近、ヴァイオリンの楽器購入を考えています。
先日、知り合いの楽器屋さんから連絡があり、R.Antoniazziと、ガイビスト(すみません、綴りが分かりません・・・)
が入ったとのこと。
弾かせてもらう前に、少しでもいいので、彼らがどんな製作者だったのか知りたいのです。
なんでもいいので教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿者:弦喜 投稿日時:2006/08/04 08:53 ---6.35.47
Antoniazzi は、左上の過去ログ検索で調べると、いくつか情報はあります。
ただ、Rの頭文字は2人いるので、どのAntoniazziか明確にする必要があります。
ガイビストという名前も、調べるためには綴りが必要です。
高価な楽器でしょうから、お知り合いの楽器屋さんに、どのような製作者なのか説明を求めるのが先決ではないですか。(これなら、電話でも聞けます。)
投稿者:yajiuma 投稿日時:2006/08/04 16:34 ---5.80.25
Giovanni Battista Gaibissoのことでは?
投稿者:セロ轢きのGosh 投稿日時:2006/08/05 00:02 ---81.65.230
わざわざ自分に先入観を植えつける前に楽器そのものを見ては如何ですか?
もっとも、骨董的価値や資産価値を求めておられるなら話は別かも知れませんね(高い楽器だそうですから)。 それなら大きなお世話、失礼しました。
投稿者:小雪★ 投稿日時:2006/08/05 19:47 ---204.209.105
弦喜さん>書き込み、ありがとうございました。&返事遅くなりまして本当に申し訳ありませんでした。早速、インターネットで調べてみました。細かい経歴は分からなかったのですが、楽器の写真とかが表示されているものがいくつかあり、ドキドキ、ワクワクしながら見ました。
自分が田舎に住んでいるので、楽器に会えるのは来週になりそうです。本当に楽しみです。
yajiumaさん>どうもありがとうございましたー。楽器屋さんがお休みで、まだ分からないのですが、来週に行けそうなので、また詳しく聞いてきます。
セロ轢きのGoshさん>アドバイス、あろがとうございます。
もちろん、先入観を植えつけるのも危険とは思うのですが、どういう楽器か気になって気になって・・・。って感じです。
楽器購入は、10年前からの私の念願でもあったので。
投稿者:セロ轢きのGosh 投稿日時:2006/08/06 13:19 ---81.65.230
小雪★様、
少々不躾な書き方でした。お赦しください。
> どういう楽器か気になって気になってになって・・・。って感じ
は解らなくもありません。 10年越しの念願、う〜ん、羨ましい。 いい楽器でありますように!
投稿者:小雪★ 投稿日時:2006/08/07 03:40 ---204.209.105
セロ轢きのGoshさま。
全然気にしてませんので大丈夫ですよ〜
Q:私のバイオリンについて調べています。
投稿者:Iris 投稿日時:2006/08/02 10:54 ---147.109.205
初めまして、いつも過去ログなどでいろいろ勉強させてもらっています。
私が購入したバイオリンについて、ラベルを頼りにいろいろ調べていたのですが、より深く知りたいと思い、知識をお借り出来たらと書き込ませて頂きます。
ラベルは以下の通りです。
-----------------------------
LUTHERIE ARTISTIQUE
Faite entierement a la Main
Laberte'magnie
mirecourt:
Vosges. France
-----------------------------
製作月日の記述がありませんが、工房の方には100年くらい前の物だと聞いています。
Lutherie=弦楽器製作家
Artistique=芸術的な
と訳せるので、合わせると”芸術的な創作”とでもなるのでしょうか?
次に以下ですが
Faite entierement a la Main
作る 完全に 主に
となりいまいち意味が掴めません。
Laberte'magnie
というのは製作工房だと思います。
1776年設立のFourier Magni'e Co. 社が1919年にLaberteに吸収?されたらしいのですが、つまり、1919年以降の作品という事でしょうか?
最後に、mirecourtとVosges. Franceですが
ミラクールはフランスのバイオリン製作が盛んな土地ですよね。
ヴォージュというのはフランスの地方名だと思うのですが、
なぜ2つあるのか良く分かりません。
それぞれの文が何を意味するのか教えていただけると嬉しいです。
自分の楽器の事をもっと知りたいので宜しくお願いします。
投稿者:ぶらっちぇ 投稿日時:2006/08/02 16:11 ---238.16.8
フランス語初級ですが……
LUTHERIE ARTISTIQUEは「弦楽器工房」の決まり文句のような言い方のようですよ。
Faite entierement a la Main 完全手工
mainは英語のmainと違って「手」ですね。
地理も苦手ですが……
Pre´fecture des Vosgesの中にla ville de Mirecourtがあるんでしょう、たぶん。
投稿者:Iris 投稿日時:2006/08/06 05:59 ---38.60.250
ぷらっちぇさん有り難うございます。
ヴォージュの中にミラクールがあるんですね。
地図を見てみましたがミラクールの位置しか詳しくは分かりませんでした。
残るLaberte'magnieですが、どなたか詳しい方いませんか?
投稿者:弦喜 投稿日時:2006/08/06 11:16 ---6.35.47
VosgesとMirecourtのおよその関係がわかる地図です。(Vosges県はフランスの地図でいうと右上の方になります)
http://www.gaf.tm.fr/en/france/lorraine/vosges/thaonlesvosges.php
Mirecourtでヴァイオリン作りが発展したのは、Vosges山脈で表板の材料のスプルースが採れていたのかもしれませんね。
フランスのヴァイオリンの歴史の書物は、ヴィヨームに関するものを除いてあまりなく、あってもフランス語がほとんどなので、なかなか情報が入手できません。
Laberte-Magnieという会社?は、すでに書かれているような時期に主にピアノ会社であったFourier Magnieと一緒になってできたようですが、1800年前から双方繋がりはありブランド名としてはその名前は使われているようで、くわしい定義はよくわかりませんでした。
Q:ガルネリとパガニーニの楽器について
投稿者:カノン 投稿日時:2006/08/04 21:42 ---80.69.129
ガルネリタイプ、ガルネリコピーとよく耳にしますが、ストラディバリウスタイプとの違いは何でしょうか?
また、ガルネリの楽器は型がいろいろあるそうですが、「ガルネリタイプ=パガニーニが愛用しらカノンの形」と考えていいのでしょうか?
投稿者:ぶらっちぇ 投稿日時:2006/08/04 22:45 ---7.228.10
他のお店のサイトで恐縮ですが、下記にストラッド・モデルとガルネリ・モデルを並べた写真があります。
http://www.minehara.com/showcase/hosco/antiquevn.htm
f字孔の形の違いがよくいわれるところですが、Cバウツのえぐれ方がストラッドのほうが深いというんでしたっけ。
ガルネリでは、裏板の湾曲が少ない、つまり楽器の厚みが少ないのがあるんではなかったでしょうか。それからスクロールが独創的、あるいは雑、というのも有名です。
また、ガルネリではボディ長が短いのが多いはずです。ただし、形態は真似たまま、サイズは標準の355mmといったコピーも多いようです。
カノンがやはり有名ですからなんとなく「ガルネリ・タイプ」というとカノンのことかも知れませんが、特定の楽器をコピーしたものは、「ガルネリ、何年」あるいは愛称を明示してあると思います。
間違っていたらご訂正お願いします。
Q:教えてください
投稿者:おはな 投稿日時:2006/08/04 17:29 ---100.31.51
Lorenzo Marchiさんのバイオリンについて教えてください。現代クレモナを代表する名工だとか…。とても興味があるのですが、あまり数も出回っていないと聞きました。入手は可能でしょうか?楽器の作風とか、サウンドについて、ご存知の方、是非教えてください!
投稿者:アノニマス 投稿日時:2006/08/04 19:20 ---44.59.210
Google(グーグル)という検索サイトをご存知でしょうか。
http://www.google.co.jp/
このサイトに「Lorenzo Marchi」というキーワードを入れると
国内の楽器店のHPがヒットします。
そのトップページの主要取扱商品の中にその作者の名前があるので
入手は可能だと思います。
詳しくはその楽器店に聞いてみてはどうですか?
投稿者:丸木 投稿日時:2006/08/04 21:23 ---121.123.151
クレモナ在住の日本人バイオリン製作家のHPに少し情報が載っていました。
取扱店はあるようですが、確かにあまり出回っているのを見たことはないですね。バイオリン製作学校で教えていて、後進の指導に当たっているから、忙しいのかもしれません。音については弾いたことがないのでよくわかりません。ごめんなさい。
投稿者:丸木 投稿日時:2006/08/04 21:34 ---121.123.151
すみません。リンク張り忘れていました。
http://www.webalice.it/violino45/index.html
の「マエストロ紹介」です。
Q:楽器を替えたら曲の好みが変わった!?
投稿者:ミィ猫 投稿日時:2006/08/01 15:26 ---41.130.73
先日はこちらの皆様には関税の件でお世話になり、本当にありがとうございました。
さて、その折のイタリアン・オールドのバイオリンに持ち替えたところ、私自身の曲の好みが変わったようです。
それまでのフレンチ・モダンとフレンチのコンテンポラリー弓を使用していた頃には、バッハやビバルディーの淡々とスケールを弾いてるような曲を好んで弾いていたのですが、今度のイタリアン・オールドとフレンチ・オールド弓を弾くようになってからというもの、カラオケでマイクを握り締めて”歌わせてください!”みたいな曲が好きになりました。
大した腕前ではないので弾ける曲は限られているのですが、具体的にはマスネーの『タイスの瞑想曲』とかラフの『Kavatine』とかです。(上記の例えは両作曲家に対して思いっきり失礼でしたね。)
そこで質問です。
現在はベートーベンの『ロマンス』ヘ長調を大人のためのバイオリン教室でせっせと練習しているのですが、何か他に底板をブイブイいわせる熱唱曲はございませんでしょうか?
半世紀以上も木箱で寝ていた楽器を叩き起こすような、お勧めの目覚まし曲をアドバイス願います。ただし、重音が苦手で、早弾きも危うくなってきた中年族の指に優しいものでお願いします。
また、もう1つ質問なんですが”大型のバイオリン”とはどの位の大きさのものを言うのでしょうか?
先日このバイオリンを調整に出したところ、ボソっと「おっきいね」と言われました。公式カタログによれば長さは35.6cmですが、大きいというのは横幅の事なんでしょうか?
わたし的には以前のフレンチと大して変わらない大きさだと思っていたので不思議でした。ただ、見かけの大きさは同じくらいで板厚もそれほど厚いわけではないのですが、何故かイタリア製の方が重たいです。
この辺の事も関係しているのでしょうか。ご存知の方、よろしければお教えください。
投稿者:ぺてお 投稿日時:2006/08/01 21:10 ---105.5.81
そのイタリアン・オールドの製作者名を教えて下さい。
投稿者:ミィ猫 投稿日時:2006/08/02 09:58 ---41.130.73
ぺてお様
領収証によると、オリジナルのラベルを運んだ1876年の Antonio Guadagnini だそうです。
オークションでは”真作”とは言い切ってないんですが、買い手がつかずに流れて、持ち主に返却されたところを英国内の委託販売の楽器店を通して私が買い取りました。
オークションではバイオリン単体で出品されていたのですが、我が家には20世紀初頭に英国で売られたままの格好でやって来ました。つまり、骨董品のみたいな木製のケースと古い弓、朽ちた松脂等と一緒にHillという当時の売主の領収証が入っていました。
良く出来た贋作なら趣味で弾くにはちょうど良いと思って購入しました。なので本物かどうかは分りませんが、見立てによれば19世紀半ばから後半のクレモノ以外のイタリアの楽器である事だけは確かだそうです。
で、こういう楽器で35.6cmは大きい方なんですかね?
ちなみに、以前のフレンチでは左右に隙間のあったケースが、この楽器ではむっちり一杯になりました。お尻でっかちみたいです。
投稿者:パスツール 投稿日時:2006/08/03 23:58 ---253.180.196
>底板をブイブイいわせる熱唱曲はございませんでしょうか?
ロンドンデリーの歌あたりは、如何でしょうか。
投稿者:ミィ猫 投稿日時:2006/08/04 18:54 ---41.130.73
パスツールさま
さっそく試聴しました。ロンドンデリーの歌って、この曲だったんだ!って感じの耳に馴染んだ曲でした。
なるほど、サビで熱唱できそうですね。楽譜を探してみます。
アドバイスありがとうございました。
投稿者:パスツール 投稿日時:2006/08/04 20:57 ---253.180.196
参考のCDは、これをお勧めします。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00005GIUX/250-1517034-0300268?v=glance&n=561956
先に挙げられた2曲も含んだ熱唱曲がたくさん入った超熱演?です。
Q:フランスの楽器?
投稿者:kaz 投稿日時:2006/08/03 23:46 ---116.51.99
こんにちは。はじめまして。
最近、弦楽器店でヴァイオリンを購入したものです。残念ながら楽器にはラベルはなく、下のページのように「LHF」と読める?の焼印があるくらいです。そして、ネックは継ぎネックされているようです。
購入した店の方は、このヴァイオリンはフランスで作られたことしか分からないそうです。楽器本体で40万くらいでした。私は自分でこの焼印について調べたところ、弊社の過去の掲示板に質問がありました、Laberte−Humbert Freres(仏) ではないかと思っております。ヴァイオリンに詳しい方々にこのマークをご覧になった事がもしかしたら居て下さればと思い、ペンを取りました。
よろしくお願いいたします。
・私自身のページの楽器の写真
http://members.at.infoseek.co.jp/kazooou/Violin/LABERT.jpg
Q:はじめまして。
投稿者:Kolya 投稿日時:2006/08/01 09:57 ---51.214.175
こんにちは。
レンタルヴァイオリンを探していて、
このホームページを見つけました。
楽器をお借りできるのでしょうか?
投稿者:ストラッドです。 投稿日時:2006/08/01 16:50 ---192.40.36
こんにちは、お店の業務に関するご質問はメールにてお願いいたします。koji-sons@strad.co.jp
レンタルの簡単なご説明は下のページになります。
http://www.strad.co.jp/navi/point5.html
それではよろしくお願いいたします。
投稿者:Kolyasha 投稿日時:2006/08/02 10:17 ---51.214.175
拝見いたしました。
どうもありがとうございます。

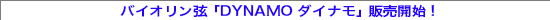
Q:ついついネットで購入
投稿者:aged new player K 投稿日時:2006/08/08 11:37 ---4.172.173
ネットでバイオリンを買うなんてかなりのリスクだと思うのですが、ついつい買ってしまいました。修理の傷やニスの部分的剥離があり、また裏板にわざとぶつけたような小さな傷が10箇所ぐらいあります。19世紀末のイタリア製のようです。音は結構しっかり出ています。やはりネットで直接売買するのは危険ですか。
投稿者:かめ 投稿日時:2006/08/08 12:08 ---196.104.66
買ってしまった後にこのように書き込むと言うことは、
届いた商品に関して後悔していると言うことでしょうか。
でしたら、返品なり、二度とネットで購入しないようにするなり
気を付ければいいことではないでしょうか。
ネットで購入すると言うことは、ある程度手軽に、安価で手に
入れられる可能性を持っている反面、リスクを伴います。
そのリスクを承知で購入すれば、それなりの満足感を得られる
買い物もあると思いますよ。
投稿者:ガルネリ 投稿日時:2006/08/08 21:53 ---24.203.53
修理の傷、ニスの乖離、10箇所の傷など、19世紀のヴァイオリンには当たり前のことです。
今回の買い物が成功だったかどうかを見るポイントは、もっと別のところにあるはずですよ。
それよりも気になるのは、たとえネットでも、本物の19世紀末イタリア製が100万円以下などということはありません。もしあったとしたら、相当劣悪な品だと考えねばなりません。ご参考までに
投稿者:弦喜 投稿日時:2006/08/09 08:41 ---6.35.134
以下、私見です。
ハイリスク・ハイリターンがネット・オークションの特徴です。特に海外の大手オークションでは、膨大なゴミの中に、ある程度ましなものが見え隠れし、ほんのわずかな宝物が中に埋まっているという状況だと感じています。
オークションでなく、売ります・買いますコーナーであっても同様です。一方ネットでのお店の場合は、安くともそれなりの値段にはなります。
海外大手ネットオークションを見ていると、多くのイタリアラベル(最近は厚かましくもJ.B.モラッシやシメオネ・モラッシまで登場)の楽器が出ていますが、どうみてもドイツ・チェコの昔の量産品だったり、中国製のアンティークフィニッシュだったり、といったものがほとんどで、写真でも本物かもと思わせるものがまず極めて少なく、実際安い値段で本物であることは毎日1000台は出品されているのを一年間眺めて1〜2度あるかないかだと思います。
以前、フランスの楽器でこれは!というものがありましたが、やはりいい物にはみな注目しているようで、終了間際で5000ドルほどに値があがりました。(その時、お金があれば、買いたかったものです...)
ネットオークションでは、独・チェコ・仏あたりのそこそこ使い物になる楽器を、1000ドル以下で見つけるにはよいところだとは思いますが、本当の名品は素人にはまず手に入りません。
一方国内の大手オークションの古めの楽器は、多くは上記海外オークションで入手し、1)買ってみたけど気に入らなかったので処分 2)転売で小金稼ぎ 3)ラベルの記載を誇張して説明し高く売りつけようとする悪意の出品,などが多いように思います。どのような中にも、調整がしっかりなされ、日本のお店での価格よりかなり安い物もありますので、利用価値のある入手チャンネルだとは思います。
なお、本当のイタリアの楽器の場合、新作でも70万円くらいが最低ラインで出品されているのではないでしょうか。
また、ほとんどは調整がいい加減なので、入手後工房に持ち込んでの調整は必須と思った方がよいでしょう。
投稿者:弦喜 投稿日時:2006/08/09 08:46 ---6.35.134
個人的には、骨董品屋めぐりのような感覚があって、またインターナショナルで多くの楽器が参照できるので、ネットでの楽器取引の世界は好きです。
投稿者:フリッツ・ベンジャミン 投稿日時:2006/08/09 09:17 ---110.187.62
弦喜様のおっしゃること、なるほど〜と感心して拝見しました。個人的な経験として、2度ほどオークションでバイオリンを購入しましたが、いずれも実物を見て弾いてみたところ調整が不十分で工房に出しました。古い方の1台はそれなりに費用がかかってしまいました。また、比較的新しい方のもう1台は前者よりは安く上がりましたが(ネック下がりなどがないため)、それでもペグ、駒、魂柱などの交換、調整などでやはり数万ほどはかかりました。実物を見ない買い物の場合、購入費以外のコストも予算に入れておかないといけない。これは痛感しました。だからと言ってもうこの方法では購入しないとは思いません。何か表現が適当ではないと思いますが、それほど高額でなければ大人になってからの少々高めのお遊びの要素もある、そんな気がします。もちろん、自分にとってメインになる楽器がないと、遊びでは済まない可能性もありますが。
オールドも含めてイタリアの楽器は実力以上の値段がついている。これが私の実感です。特にモダン以降は国による差ではなく、作り手個人によるものが大きいにもかかわらず、相変わらずイタリアのラベルが物を言っている。だから騙す人間も出るというもの。憂うべき傾向だと思います。