弦楽器 Q&A
弦楽器に関するいろいろな疑問にお答えします。
2023年12月31日をもちまして、新規投稿・コメントの書き込みを終了させていただきました。
5203件のQ&Aがあります。
Q:チェロ弓
投稿者:ミルモ 投稿日時:2012/12/16 18:06 ---93.1.146
チェロを始めて7年目。
本体は数年前にセットものから50万の物に買い替え、ようやくお小遣いが貯まってきた所で、弓を購入しようと思っています。
二件ほど回りましたが、なかなか決められません。
よくブログ等で本体の半分の価格が弓の値段と申しますが、
工房の店主だと「値段気にしすぎ」とポツリと言われてしまいました。
いくつか試奏した商品の中で定価36万台の弓を試奏しましたが、これは高すぎる商品ですか?
同じメーカーで定価26万円の弓もいい感じだったのですが、先ほどの弓のほうが音の残り具合(?)がいいのです。
上を見ればとてつもない金額の弓もありますが、しょせんアマチュアでございますので、無理はしないようにはしてます。
ちなみにメーカーは某日本の製作のものです。
投稿者:検索好き 投稿日時:2012/12/17 12:59 ---13.51.97
ヴァイオリンの場合の知識なのですが、弓の値段は楽器の値段の3分の1から2分の1という説がありますね。楽器にはお金をかけても弓が安価な場合には性能が釣り合わないので、せめてこれくらいは弓にもお金をかけるべきということのようです。
個人的には挙げられた弓のいずれも高すぎるということはなく、妥当ではないでしょうか。
今回のケースには関係ありませんが、楽器が安価な場合には、3分の1から2分の1では弓が安くなり過ぎると思います。
投稿者:F 投稿日時:2012/12/17 16:47 ---146.120.165
楽器、弓の値段は時期や場所によっても変わるので、値段を見て買うのはあまりいいとは思いません。
楽器屋のご主人もそれを分かっているから、値段気にしすぎ、と言ったのだと思います。
あくまで自分の場合ですが、まずは音、なるべく自分が理想としている音に近い音が出るかどうか、次に操作性や総合的な性能、弓の状態、金額を重視します。
弓の性能や状態については聞けば詳しく教えてくれるはずです。
逆に言えば、自分が気に入りさえすれば安い弓でも自分にとっては十分価値があると思います。
投稿者:弦喜 投稿日時:2012/12/22 02:10 ---51.234.38
弓は手の延長であり、できるだけ持っている感のないものを購入したいですね。
個人的には、楽器の値段に関係なく、弓はよいものを選ぶべきかと思います。
私は、一時期、弓が楽器の2倍の値段という状態で演奏していましたが、買い替えるまでは苦労して弾いていたものが、ある程度良い弓を持つと苦もなく演奏可能となり、また音色も変わりますので、弓を変えたことで演奏の質が数ランク上がった気がしました。
これは私の少し前の経験からの感覚ですが、現代製作者の弓がヴァイオリンでは60万円〜100万円くらい、チェロはその2割増くらいの価格で購入できるので、アマチュアとして一生ある程度満足して使い続けるもの、と考えるとそのあたりの弓で気に入ったものを購入するのがよいと思います。
またもっと安価なメーカー品でも、当たり外れがあり、稀に大当たりのものもありますので、同じメーカー&グレードでもできれば複数試して、これだと思ったものを購入するのがよいと思います。
投稿者:ブラックボックス 投稿日時:2012/12/26 21:52 ---206.85.213
「値段気にしすぎ」も、ある意味で有なのでは。
本体の半分の価格を、押し通せば、26万の弓も1万オーバーで、NGです。
他の楽器店を探した方が良いのでは。
個人的には、15万くらいのカーボン弓というのは、どうでしょうか?
好き嫌いはあると思いますが、性能的には、36万の弓以上の可能性もあります。
Q:過去に質問があったか分かりませんが・・・
投稿者:まなべえ 投稿日時:2012/12/21 17:25 ---237.52.107
ヴァイオリンを習い始めて5年経ちます。
最近60年ほど前に作られた楽器に変えたのですが、古い楽器を使うならスチール弦はやめたほうが良いと聞きました。
スチール弦は張力が強いためネック下がりなど楽器に負担が掛かることが多く、特に古い楽器を長く使うなら、張力の弱い弦に変えた方が良いということらしいのです。
私も始めの頃はナイロンコア弦を使っていたのですが、寿命が短く巻線が(特にA線)すぐにナットのところでほつれたりして経済的に良くないと思い、スチール弦(ヘリコア)を今は使っています。
(私は演奏をして利益を生む訳ではないので、経済的に優しいスチール弦を使い始めました)
それまでは新作の楽器だったので、何も問題にせずスチール弦を使っておりましたが、やはりこれからはスチール弦の使用は控えたほうが良いのでしょうか?
楽器に負担が掛かるという点が一番気になっており(ネック下がりなどの修理代が高いことも先々の問題として心配です)音色とかは腕が未熟なため、弦の善し悪しでどうの・・・というのは判断出来ません^^;
(高価な弦の方が、音色が良いだろうことは想像出来ますが・・・)
的確なアドバイスをお願い致します。
投稿者:QB 投稿日時:2012/12/21 21:05 ---182.150.63
古い楽器:どれくらい前のどのような楽器をお持ちですか?それにより答えが多少変わるかもしれません。
スチール弦は張力が強いためネック下がりなど楽器に負担が掛かることが多く
>迷信だと思います (参考:http://www.sasakivn.com/werkstatt/report/saitenschpan.htm)
古い楽器を長く使うなら、張力の弱い弦に変えた方が良い
>YesともNoとも言い切れません。お持ちの古い楽器がモダンのネックにすげ替えていないものでしたらYesと言っても、まぁ良いと思います。
すぐにナットのところでほつれたりして経済的に良くないと思い
>コレは弦のせいよりも、まずナットの調整不具合の可能性を疑ってください。
楽器に負担が掛かる
>スチールよりはるかに楽器に張力の高い弦はいくらでもあります。(上記リンク参照)
投稿者:まなべえ 投稿日時:2012/12/22 12:00 ---95.33.85
QBさま>
ご回答有難う御座います。
楽器は質問に書いた60年ほど前の日本で作られた楽器です。
なのでネックは取り替えられておらず、製作時のままです。
今まで使っていた楽器を調べたところ、指板の端から表板までの距離が18mmしかありませんでした。
これはネック下がりなのでしょうか?
(そもそも、ネックが下がっているかどうかを調べる方法が分かりません。上記の調べ方は、どこかのサイトにあった方法で、標準で20mmほどだそうです)
質問から逸れますが、ネック下がりとはどのような状態なのでしょうか?
また自分で調べる方法がありましたら教えていただけると有難いです。
投稿者:QB 投稿日時:2012/12/22 23:50 ---182.150.63
お持ちの楽器は所謂モダンですので、その点をもってネック替えの必要はありません。
指板の端から表板までの距離は、お持ちの楽器のモデル(具体的に言うと、表板の膨らみ)によって異なりますので、その数字のみではネックが下がっているかどうかは分かりません。
ネックが下がっているかどうかを調べる方法自体は、それほど難しいわけではないのですが、まなべえ様が簡易に調べるためには、何か基準となるポイントが必要です(例えば現在の駒が適正な高さであるとか)。ところが、その確証も無いので、文章のみでお伝えするのは躊躇します。
一つの手がかりとして、e線の7ポジション前後で、指を押さえようとした時に、かなり痛いですか?
もし、相当強く押さえる必要があり、指に弦が食い込む感じで痛いのであれば、何か処置が必要です。
お近くに、弦楽器を取り扱っている楽器屋さんか、弦楽器専門店はございませんか?
今後の事も考えて「主治医」を見つけるのが良いと思います。
投稿者:まなべえ 投稿日時:2012/12/24 14:47 ---95.59.80
QBさま>
重ねてご回答有難う御座います。
確かに、実際に楽器を見てみなくては判断しかねることですよね、失礼致しました。
駒の高さは一番高いところで約32mmありました。
購入した時から駒は変えていません。
指が痛いとか演奏に差し支える感じは今のところありませんので、このまま使ってみようと思います。
弦に関しても、スチール弦よりも張力のある他の素材の弦があると知って驚きました。
一概にスチールだからダメとかではないということが分かりスッキリしました。
身近に信頼出来る楽器に詳しい方がいないもので、ネットで調べているのですが、情報が錯綜して、どれが正しいのか信ぴょう性がなく困っておりました。
的確にアドバイスを頂けるお店を近場で探してみます。
有難うございました。
Q:Ersen Aycan のチェロについて
投稿者:三角フラスコ 投稿日時:2012/12/13 18:37 ---93.185.9
はじめまして。
私の好きなチェリスト、Martin Ostertag が使用しているチェロに
質問させていただきたいと思います。現在ドイツに在住の製作者の方のようですがweb上にはほとんど情報がありませんでした。この製作者のプロフィールなどもし情報があればご教授いただければ幸いです。可能であれば購入を考えているのですが、入手できるとしたらチェロの価格帯はどのくらいなのでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿者:F 投稿日時:2012/12/13 23:02 ---230.16.152
http://www.instrumenten-scout.de/instrumenten-bauer/details-firmen/article/aycan-ersen.html
aycan@t-online.de
ご本人に英語で問い合わせてみれば確実です。
投稿者:三角フラスコ 投稿日時:2012/12/14 12:08 ---93.185.9
Fさま
早速情報をいただきましてありがとうございました!
問い合わせるとしてみます。
Q:表板の接着部分の隙間
投稿者:まなべえ 投稿日時:2012/12/06 20:53 ---95.63.207
しばらく使っていたヴァイオリンの表板、ロウワー部分の中央、左右の板を接着した部分に剥がれを見つけました。
ほんの少しの隙間で音にも影響がないようなのですが、このまま使い続けて問題はないでしょうか?
後々、楽器に重大な問題が起きないか心配しています。
また修理する場合は、表板を剥がして、継ぎ目を接着し直して、パッチを貼って・・・と大掛かりな修理しか方法はないのでしょうか。
そこまで高額な楽器ではないので、あまり費用を掛けたくないのです。
宜しくお願い致します。
投稿者:猫丸 投稿日時:2012/12/11 11:02 ---106.119.140
表板は剥がれるように(剥がせる様に)他より弱く接着されています。
薄いニカワをしみ込ませてクランプで押さえて接着ですが、大変な修理ではありません。
>また修理する場合は、表板を剥がして、継ぎ目を接着し直して、パッチを貼って・・・と大掛かりな修理しか方法はないのでしょうか。
この修理は表板が割れたときです。
他に異常が無いようなら簡単な修理で終わるでしょうから、総合的に診断してもらって下さい。
投稿者:QB 投稿日時:2012/12/12 22:28 ---182.150.63
「表板、ロウワー部分の中央、左右の板を接着した部分」これは、中心線のことですか?(マッチブックしたところが剥がれ、というか開いてきた?)
もし横板との接着面ではなく、表板の左右の中心が開いてきたのであれば、修理はもちろんなのですが、猫丸氏のおっしゃるとおりきちんと診断してもらってください。
たまたま経年による何か単純な原因で開いただけであれば、左右から挟み込むタイプのクランプで、表板を開けずとも治る方法で閉じるだけという可能性もありますが、使用していた膠の種類によっては日本の気候にあわず、今回処置しても未処置の部分が開いてしまう可能性から、一度表板を空けて全体を処置しなければならない可能性もゼロではありません。(比較的なの通った新作の作者でもその処置の必要な事で知られた人もいます)。他に木釘が原因だったケースもあります、その際には木釘を外して処置しないと再発します。。
いずれにせよ、よく診てもらってください。
投稿者:まなべえ 投稿日時:2012/12/13 18:28 ---31.148.200
猫丸さま、QBさま>
ご回答有難うございます。
開いてきたのは、表板中央のブックマッチ接合部分です。
楽器店に問い合わせしたところ、隙間に膠を流し込み接着する方法もありますが、負荷が掛かればすぐに開いてしまう可能性が高いため、やはり表板を剥がしてしっかりパッチを当てて修理する方が後々のことを考えても安心という回答がありました。
長く使う楽器ですので、ここはしっかり修理して貰いたいと思います。
Q:バイオリンの駒
投稿者:SGS 投稿日時:2012/12/12 20:45 ---47.18.137
最近,某楽器店で新品で30万円ほどのバイオリン本体を購入した者です。
自宅に戻って楽器を確認したところ,駒の足の下(バイオリン本体との間の接触部分)に,透明の接着剤のようなものがはみ出ているのを発見しました。
触ってみたところ,駒がバイオリン本体に動かないように固定されているようです。
これまで使ったことのあるバイオリンは,駒がバイオリン本体にのせてあるだけでしたが,初心者用のバイオリンでは駒が固定されているということもあるのでしょうか。
購入店に相談する前に,詳しい方の御意見をうかがうことができると有難いと考えて投稿します。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿者:F 投稿日時:2012/12/12 22:16 ---144.214.61
楽器店で購入されたということですから、そのような楽器ではあり得ないと思います。
弦を緩めて駒が固定されていないかチェックしたわけではないのなら、思い違いも考えられますね。
いずれにしても、購入元に電話すれば済む話です。
投稿者:QB 投稿日時:2012/12/12 22:18 ---182.150.63
それは、ニスが駒足からの圧力と振動で変形した(のけられてはみ出してきた)だけだと思われます。
新作楽器でまだニスが柔らかいものほど、なりやすいです。
どうしても気になるようでしたら、購入したお店に聞いてみるのがすっきりしていいでしょう。
投稿者:SGS 投稿日時:2012/12/12 23:03 ---47.18.137
F様,QB様,
早速にご回答をありがとうございます。大変参考になり,また安心致しました。
購入時には気がつきませんでしたので,QB様のご指摘のとおりの現象が生じたのではないかと考えています。これまで新作楽器を使ったことがなかったので,とても驚いた次第です。
改めて,感謝申し上げます。
Q:音感について
投稿者:時刻表 投稿日時:2012/10/11 12:20 ---49.94.184
こんにちは。いつも楽しく拝見しております。
ふと感じた疑問なのですが、もしお分かりになる方がいたら
ご教授ください。
とあるサイトで「絶対音感テスト」なるものを見つけやってみました。
(当たり前ですが、自分には絶対音感はありません)
ドとかレとか、和音であっても音が違うものは分かるのですが
同じ音でヘルツ?が違うものはまるで分かりませんでした。
ここで質問です。
よくヴァイオリンで、同じ音でも高くとったり、低くとったりするという話を聞きますが、これはそのヘルツ?の違いを言っているのでしょうか。
これまでは、単に曲調によって明るい、もしくは暗い「ラ(例えば)」という意味なのかと思っていました。つまり、あきらかに少し音が違うものという把握です。
しかし、ヘルツレベルの差のことを指しているならば永遠に音程というものが理解できないなあと思っております。
ヴァイオリンの音程って一体どういう意味なのでしょうか?
投稿者:猫丸 投稿日時:2012/10/11 16:17 ---106.119.140
マシーンレベルのヘルツの差というのは音楽とは関係ありません。
規準のAはオケでも2Hz程度のずれで合わせられますが、管楽器、ピアノとは原理的に合いませんので、合奏上どちらかが音が濁らないように合わせる、高くとる、低くとるはあります。
バイオリンなら、生ガットのコルダを張ってみてください、弾いている内にたちまち4弦合わなくなります、後は、耳と頭が頼りですね。
物理学的周波数列というのは規準としてありますが、最終的に必要なのは、音楽なので、ずれようが、何の支障もありません。
投稿者:猫丸 投稿日時:2012/10/11 18:40 ---106.119.140
追加訂正 失礼!
>合奏上どちらかが音が濁らないように合わせる、高くとる、低くとるはあります。
金管管楽器、ピアノは合わせられないので、弦楽器が合わせます。
管楽器の名人はできますが、ピアノは名人でもできませんね。
曲芸になってしまいます。
投稿者:kuro 投稿日時:2012/10/12 09:41 ---33.45.33
>ピアノは合わせられない
>ピアノは名人でもできませんね。
音高を変えることはできませんが、弾き方を工夫することで
対処することはある程度可能です。
ここは弦楽器の会議室なので、これ以上の情報は必要ないとは思いますが
一応。
投稿者:時刻表 投稿日時:2012/10/15 12:11 ---49.94.184
皆様、ご回答ありがとうございました。
数値でなく、周りの音の高さに合わせるということですね。
音程の話は奥が深いです。
ちなみに、バイオリンとピアノのAではヘルツが違うと思いますが、
これは明らかに音程が違うのでしょうか?
また、普通の人にも分かるものなのでしょうか?
またの質問になって恐縮ですが、よろしくお願いします。
投稿者:大熊猫 投稿日時:2012/10/16 11:24 ---9.96.227
最近では、オケや弦楽アンサンブル、あるいは弦楽器の独奏の場合でも、Aを442Hzに合わせることが多いです。
これに対して、ポピュラー音楽や、普通にピアノの調律を依頼すると、Aを440Hz(国際基準)に合わせることが多い。
442Hzに合わせたバイオリンのAと、440Hzで調律したピアノのAでは、明らかに音程が合いません。また誰が聞いてもその違いがわかります。
うちでは、バイオリンが主であるので、当然ピアノはA=442Hzで調律してもらっています。
因みに、私はチューナーやピアノが無くても、正確にA=442Hzでバイオリンをチューニングすることが出来ます。別にこれは偉い訳でも何ともなく、単に何十年もバイオリンを調弦していることで、少なくともA=442Hzだけは完全に記憶してしまったという訳です。
投稿者:時刻表 投稿日時:2012/10/17 12:11 ---49.94.184
大熊猫様
コメントありがとうございます。
ピアノの音とは明らかに違うということなのですね。
意識して聴いた事がありませんでしたが、
一度注意して聞いてみます。
ありがとうございました。
投稿者:元ラッパ吹きです 投稿日時:2012/10/19 14:52 ---158.5.88
管楽器でも音程の微調整はできます。 そこらのアマオケでも一寸気の利いた管楽器奏者なら誰でもやっていますよ。アナログなのはトロンボーンだけだと思っているなら大間違いです。
投稿者:猫丸 投稿日時:2012/10/20 09:51 ---201.175.161
音程の微調整が可能か、不可能かと言うことを言ったのではありません。
オーボエはリードの抜き差しでわずかですが微調します。
ファゴットは可変範囲が小さくなるため、リードを交換しないと無理のようですが。
クラリネットも当然微調可能、吹き方でも微調するのはオケでは常識です。
ホルンに至っては、吹き方とラッパに入れた手で調整しているのはこれも、オケマンなら常識ですが。
>アナログなのはトロンボーンだけだと思っているなら大間違いです。
当然です!
スレ主さまの疑問、弦楽器のと言う質問に答えた訳ですので、誤解なきように。
投稿者:大熊猫 投稿日時:2012/10/21 01:16 ---157.26.121
逆に昔、オケの演奏前のトロンボーンのチューニングには一体どういう意味があるのか、疑問に思ったことがあります。
でも実は、音程連続可変な構造であっても、音程を決めるポジションはある訳で、これはフレットが無い弦楽器の場合も同じですね。
投稿者:猫丸 投稿日時:2012/10/21 08:25 ---201.175.161
金管のチューニングには、温度が関係します。
吹き続けると体温で管内の温度上昇、同じポジションでも音程は上っていき、弦楽器は弦が伸びるため下がっていき生き別れになります。
金管が休憩時間に舞台の上の椅子に楽器を置いているのは、楽屋に持っていくのが面倒だと言うわけではなく、温度変化を嫌うためで、演奏前に舞台上で音程確認しないでいきなり吹き出すのは、ギャンブルになってしまうからだと金管吹きから聞いております。
楽器の種類により特性があり、悩みがあるようで、クラリネットが曲間に舞台上で掃除をするので、楽屋でやればいいだろうと言ったら、掃除しているのではない、水滴を除去しておかないと、最悪演奏中に管が割れるとのことです。
投稿者:ギリシャ 投稿日時:2012/10/29 21:40 ---3.99.86
ピタゴラス定理の音程を研究してみてください。
投稿者:α 投稿日時:2012/12/11 23:25 ---223.171.181
スケールを弾く時に上昇と下降では指使ひが違ふし、実際に音程も違ふのは絶対音階やピタゴラス音階が実在しないためなのでせうか?
Q:教えて下さい
投稿者:けんけん 投稿日時:2012/12/02 23:32 ---156.211.48
初めまして、お世話になります。
古いカールヘフナー製のバイオリンをいただいたので
ネットで情報収集しようとしてココに辿り付きましたので質問させて下さい。
fホールから覗きますと
KARL HOFNER
BUBENREUTH NEAR ERLANGEN
GERMANY47047
と記載されております。
黒いレザー性のバイオリン型のケースに本体と弓が入っています。
バイオリン本体の状態は弦が1本のみ残っており
ペグが一つ本体から抜けています。
弓は切れ切れで張り直しが必要だと分かります。
肩当も有りません。
使用するとなれば修理したうえで
松脂やチューナーやメトロノームや教本等が必要になると思います。
(ギターの経験者なりの見解です。)
修理にいくらかかるのか分かりませんが
安価な修理代金でないことは予想できます。
(たぶん弓とか弦のグレードにもよると思いますが…)
そこでこのカールヘフナー製のバイオリンが
結構な修理代を使ってまで直して使う価値が有るものなのか?
それが型番等で分かるのではないか?
と思い検索してみましたがヒットしませんでした…
問合せさせていただきたい内容は
上記の型番から何年頃の製品で当時価格はいくらくらいだったのか?
(現在の価値としてはいくらくらいのものなのか?)
そして使用できるように修理した場合にいくらくらいの修理費用になるのか?
です。
くださった方は「ガラクタに近い」と言っておりましたが
カールヘフナー製エレキベースは充分に価値が有ると知っていますので
修理が必要なこのカールヘフナー製のバイオリンも無価値ではないのではないか?
と(勝手に)思っています。
分かる範囲で構いませんので情報をもらえたらと思います。
ご回答いただいた内容によって修理するかどうか?
修理するならどの程度まで修理するか?
の判断を下したいと考えております。
何卒よろしくお願い致します。
投稿者:弦喜 投稿日時:2012/12/03 00:35 ---51.234.38
カールヘフナーの品番ですが、少なくとも10数年前以降は、正規輸入販売品は、品番がアルファベットと数字に変わり、数字がグレードを示すようになりました。いつから変わったかわかりませんが、例えば1970年頃の楽器では5桁の通し番号になっており、その番号自体はグレードを示しませんし、メーカにはその記録がもしかして残っているかもしれませんが膨大な数(数万以上)ですので聞いても回答は期待できません。
また海外での販売品では通し番号も見かけましたし、その番号からどのようなランクの楽器であるか想定するのは、まず諦めた方がよいでしょう。従って、その楽器自体を見ないとわかりません。
今迷われている件は、一旦懐具合から素直に修理に投資できる上限金額を決めた上で、修理をする職人さんのいる弦楽器店、弦楽器工房にその楽器を持ち込み、どの程度の楽器なのかをお店で見てもらうとともに、修理見積もりもした上で、すべてで折り合いのつく金額でおさまるかを判断すればよいと思います。
先方はプロですから、楽器を見ただけで、どのような材料のどのような作りの楽器は判断できますので、今のヘフナーやスズキで言えばどの程度のグレードのものかについて、経験に基づく意見はもらえると思いますよ。
投稿者:Y 投稿日時:2012/12/03 12:22 ---144.214.86
弦喜様が完璧な回答を書いてくださっているので、私は個人的な意見に留めておきます。
ご自身がその楽器を使いたいと思っているなら、修理する価値はあると思います。状態は見ないと分かりませんが、市場価値、ということで考えるならば修理代金の方が高くつくかもしれません。あくまで個人的推測、意見ですが。
大切に扱われる事を望みます。
投稿者:あがるま 投稿日時:2012/12/11 23:11 ---223.171.181
ドイツ製の − 中国に外注したのではない − 古い量産楽器は
(非常に)品質が良いと思ひます。5万円以下で修理出来るなら新しく買へば20万程度のものと同等でせう。
Q:古い弦について知りたいです
投稿者:下手っぴバヨリン弾き 投稿日時:2012/12/02 20:20 ---95.63.207
最近、古い弦がパッケージとともに付いているヴァイオリンを購入しました。
ヴァイオリンにはラベルがあり、製作者とTokyo、製造Noなど記載されていますが、製作年号は書かれていませんでした。
楽器の大体の製作年代を知りたいと思い、付いていた弦の年代が分かればと考えました。
「PATORIO」というブランドの弦と赤い筆記体文字で「Pirastro」と書かれた弦で、ピラストロの方は、西ドイツとドイツ表記の2つがあり、どちらともA線のクロムコアで、ドイツ表記のものには¥230と金額が書かれています。
このような情報で年代を調べることが可能か分かりませんが、どうか宜しくお願い致します。
投稿者:大熊猫 投稿日時:2012/12/07 10:31 ---175.177.162
一般的な話ですが、弦は消耗品なので、ついている弦でもって楽器の年代を判断推定することはできません。
プロや音大生では毎月弦を変える人も少なくないし、パールマンは毎回の本番ごとに張り替えるそうな。
中古車の年代を、交換が可能なタイヤの消耗具合だけで判断するのが無理なのと同様ですね。
いずれにしても、その楽器を使い始める前に、弦をすべて替えましょう。
投稿者:下手っぴバヨリン弾き 投稿日時:2012/12/08 11:22 ---95.63.207
大熊猫さま
ご回答、ありがとうございます。
楽器について少しでも情報をと思い、手がかりになればと質問しました。
確かに同封されていたからといって、消耗品である弦が、楽器と同年代の品とは限りませんね。
詳細に見ましたら、楽器自体にも問題があり、修理が必要でした。
他方からも貴重な情報が手に入り、とても役に立っています。
有難う御座います。
Q:スズキ教本のCDについて
投稿者:時刻表 投稿日時:2012/12/03 12:53 ---49.94.184
こんにちは。いつも楽しく拝見しています。
また質問させて下さい。
スズキの教本に付属しているCDについて、
よく「音が悪い」という話を聞きますが
これはどういう意味なのでしょうか?
1.録音の質が悪い
2.音色/音程の狂いなどあって、演奏が下手
2の場合、どの部分がダメなのでしょうか。
ド素人の自分からすると、とても上手な演奏に聞こえるのです。
現在、音程や音色を意識した練習に取り組んでいるため
ぜひ真意を知りたいと思っています。
お分かりになる方、説明していただけるとうれしいです。
投稿者:通りすがり 投稿日時:2012/12/03 19:42 ---159.224.56
そういう話は聞いたことがありません。
123巻付属CDの演奏は日フィルのコンミスさんです。
投稿者:QB 投稿日時:2012/12/03 20:40 ---182.150.63
おっしゃっているのは改訂前のCDだと思います。(それが改訂の理由?と勝手に思っています)
私は当時、子供には聴かせませんでした。USのSUZUKIでは2種類の演奏のCDがありましたので、そのCDを聴かせるか自分で弾いて聴かせていました。
投稿者:ブラックボックス 投稿日時:2012/12/03 23:54 ---206.85.213
改訂前は、誰が弾いていて、いつの録音かわかりませんが、3巻のCDを聞いた限りでは、江口 有香さんの演奏は、すばらしいです。(どこかのブログで、五嶋 みどりより上では?というのを見たことがあります。)
やさしい曲ほど、プロは弾きたがらないものです。
きっと、恩返しのつもりで、123巻の演奏を引き受けたのではないでしょうか。
投稿者:くま 投稿日時:2012/12/06 20:19 ---215.124.217
スズキの教本の付属CDの音の良し悪しなどはどうでも良いことだと思います。それよりも、何のためにCDが付属しているかを考えたほうが意味があると思います。
これはスズキメソードにおいて付属CDがどのような役割を果たしているかを考えればすぐに解ることですが、結論を先に言うと、これは全国統一規格で子供たちに全く同じ演奏をさせるためのツール(道具)なのです。
この付属CDがあるからこそ、武道館でのグランドコンサートを頂点とした各種演奏会で一糸乱れぬ演奏(統一規格演奏)を実現することが出来るのです。
スズキメソードで習わない人でこの教本を使う人は、付属CDは参考程度に一回くらい聞けば十分だと思います。
投稿者:時刻表 投稿日時:2012/12/07 12:28 ---49.94.184
皆様、ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
音が悪いというのは改訂前の話だったのですね。
自分の手持ちのものは比較的新しいものだと思うので
該当しないようですね。
これでスッキリしました。
ありがとうございました。

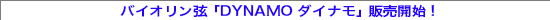
Q:作家の名前を調べて頂きたいのですが。
投稿者:イグノーベル 投稿日時:2012/12/29 21:43 ---108.237.137
初めて書かせて頂きました。実はあるヴァイオリンの作家を知りたいです。3/4分数ヴァイオリンT.Campanella.Tokio.Anno1990という、ラベルが貼ってありました。手書きのラベルでした。よろしくお願いいたします。
投稿者:検索好き 投稿日時:2012/12/30 11:40 ---13.51.97
「campanella strings」で検索すると、米国のヴァイオリン製作者がヒットします。「J」と「T」は似ていますから、可能性がありそうに思います。
Tokioは東京の事と思います。とすると、米国のヴァイオリン製作者が東京で製作したことになってしまい、疑問もわきますが。
投稿者:イグノーベル 投稿日時:2012/12/31 09:37 ---108.237.138
検索好き様、ありがとうございました。イタリーと、聞いてましたのでアメリカの作家さんと知って良かったです。それでも縁なので、買うつもりです。ありがとうございました。
投稿者:F 投稿日時:2012/12/31 10:48 ---214.57.148
ラベルはあてにならないので、信頼出来る楽器屋に状態、造りを聞いた上で音が気に入り、また予算の範囲内であれば買えばいいんじゃないでしょうか?
投稿者:イグノーベル 投稿日時:2012/12/31 22:45 ---108.239.250
F様。
ありがとうございます。もちろん音はとても気に入ってますので、購入予定です。プロの方に試奏して頂きました。音は3/4の割にはフルのヴァイオリン並みにでて、しかしとても軽く、娘の友達になってもらえそうです。年末の忙しい最中、質問に答えて頂き、誠にありがとうございました。検索好き様、F様。良いお年をお迎え下さい。