弦楽器 Q&A
弦楽器に関するいろいろな疑問にお答えします。
2023年12月31日をもちまして、新規投稿・コメントの書き込みを終了させていただきました。
5203件のQ&Aがあります。
Q:1点装着式肩当とクローソンの顎あて・・・
投稿者:PC 投稿日時:2009/05/20 13:37 ---12.18.5
1点装着式の肩当を使用しています。
クローソンの顎あてが気に入ったので交換したいのですが、
これだと肩当が装着できません。
顎当ての足を変えることは可能でしょうか?
投稿者:猫丸 投稿日時:2009/05/20 15:47 ---71.201.156
投稿者: PC ---112.18.5
投稿者: 駒子 ---112.18.5
顎当てがないと、弾けません、肩当ては、なくてもかまいませんが、肩当て装着のために顎当てを改造したいというのは聞いたことがありません。
何を、おやりになりたいのか、もう少し、詳しく質問されてはいかがでしょう?
投稿者:QB 投稿日時:2009/05/20 16:34 ---05.227.127
的確な突っ込みです(特に前段)>猫丸氏
---112.18.5さん
ちなみに1点装着式の肩当ってStoweですか?
http://www.stowemaster.com/story.html
使っている人はめずらしいのですが、、駒パッタンの投稿と合わせると、そのアンバランスさに戸惑います。
投稿者:(HNはなるべく同じ方が良いと思う)rio 投稿日時:2009/05/20 18:55 ---7.3.207
>顎当ての足を変えることは可能でしょうか?
金属アレルギーの人や
HILL足の金具より軽量な金具を装着したい人は
少なからずおり、
顎あての金具交換は実際になされています。
弦楽器工房や楽器店に相談すれば
顎あてを加工して
金具を交換してくれるでしょう。
Q:駒が倒れてしまいました!!
投稿者:駒子 投稿日時:2009/05/19 20:59 ---12.18.5
弦を張り替えている最中、後ろに少し倒れた駒を元に戻そうとしていたら、力余ってパターンと駒が前に倒れてしまいました!!
この場合、自分で駒を立てても、根柱との関係は壊れてしまっているのでしょうか?
何か音が元に戻っていない気がします!!
今すぐに楽器屋さんにいけないのですが、とりあえずどうしたら良いでしょうか?
投稿者:ライムライト 投稿日時:2009/05/19 22:01 ---60.77.133
楽器屋さんいって、魂柱たたいてもらいましょう。
駒が倒れて楽器が膨らんだため、魂柱がずれたんだとおもいます。
間違っても、自分でたたこうなんて思わない方がいいです。
f字孔をぼろぼろにするだけだとおもいます
投稿者:弦喜 投稿日時:2009/05/19 22:20 ---102.246.184
以下、弦は全体として普通に張られている状態で、無防備に駒が倒れた、という想定のもとに書きます。
駒が倒れた際に、楽器への衝撃で思い浮かぶのは下記です。
−表板への圧力が急になくなり、少し表板がたわむ。
この際に、魂柱がずれたり、傾いたり、倒れたりすることがあります。
−駒が倒れて、表板に激突する。
表板に傷がついたり、運が悪いと表板の割れにつながることがあります。
駒自体の足などが欠ける事もあります。
−支えがなくなりテールピースが表板側に落下する。
特に、アジャスタの表板側の突起が問題で、普通は表板に傷がつきますし、
ひどい時はかなり食い込みます。それが表板の割れを誘発する場合もあります。
−弦が指板にぶつかり、駒側を下に押し下げます。
めったにありませんが、ネックの付け根が痛んだり、指板の剥がれに
つながったりする可能性もあります。
f字穴からみて、魂柱がまっすぐ立っていればラッキーですので、そうであればまずはそのままにしておきましょう。魂柱が動いていない可能性も十分にあります。
傾いていたら衝撃でずれたということでしょうが、これも普通の人は手が出せないので、できるだけ早く弦楽器工房へ。
駒は、足の跡がついていれば元の位置に立てましょう。なければ、f字の内側の切れ込みを結ぶ線上が駒足の中央になるようにとりあえず立てましょう。楽器を正面に見ての駒の左右の位置関係は、とりあえずスクロール側から指板を覗き込むようにして、弦と指板との相対位置から左右のバランスのよさそうなところに合わすくらいしかないと思います。
一番怖いのは、表板の割れでしょうから、もし割れがある場合は、弦を緩めにして、できるだけ早く弦楽器工房に持って行くべきかと思います。
いずれにせよ、近いうちに一度弦楽器工房でみてもらってください。
投稿者:駒子 投稿日時:2009/05/19 22:42 ---12.18.5
短い間にたくさんのお答えをありがとうございました。
魂柱はまっすぐのままで、表板の表面にも傷や割れ目はついていませんでした!
音も元に戻ってきたので、今すぐに楽器やサンにいけない状況の中では一安心しました。
来週になったら楽器屋さんに持って行きます。
Q:初投稿です
投稿者:福招き 投稿日時:2009/05/15 16:31 ---103.118.42
こんにちは、はじめて投稿させて頂きます。
このサイトを見ていて、ちょっと知りたくなった事があったので、どなたか教えて頂けませんか??
ある方が、バイオリンの裏側にできた1センチくらいのヒビで工房に持っていったという投稿をみつけたのですが、、ヒビはそんなにまずいものなのでしょうか?
ヤマハの弓張替えとか調節のときに、何も言われないし、私自身気にしたこともなかったのですが、、私のバイオリンはヒビだらけです。
なにかすべきなのでしょうか???
投稿者:horn103gb 投稿日時:2009/05/15 19:08 ---74.26.196
基本的にヒビは非常にまずいものです。
人にたとえればヒビだらけ=傷だらけの状態でしょう。
ただ、どこにどの様などれくらいの深さ・長さのヒビが入っているのかが重要だと思います。
ひざをすりむいているだけなのか、骨折している状態なのかさっぱり分かりません。専門医にかかる必要があるのか、あるいはほっておいて良いものなのか?自覚症状が有るのか、実は悲鳴を上げているのに気づいていない状況なのか?ご質問の内容だけでは分かりません。又、弓の張替え調節とバイオリンのヒビの関連も意味不明です。できれば、ヴァイオリンのご紹介も頂ければ回答する人も回答しやすいと思います。
投稿者:福招き 投稿日時:2009/05/15 19:20 ---103.118.42
回答有難うございます。
指摘の通り詳しい説明をします。
使っているバイオリンは知人に作ってもらったものです。2000年製造です。cremona annoと書いてあります。有名な方ではないです。
後、ヤマハの調節と弓替えは、一緒に点検もしてもらえるので、点検という意味の言葉として使いました。わかりにくかったですね。すいません。
ヒビの状態は、、、あまり深くないですね。一ミリ以下です。それが、無数に走っています。長さは、、、1〜3センチ程度ですね。音は私の知る限り、変化在りません。
投稿者:福招き 投稿日時:2009/05/15 19:46 ---103.118.42
あと、バイオリンの木材部分にヒビはまったく達していません。表面の透明層の部分だけです。
投稿者:じゅん 投稿日時:2009/05/15 23:00 ---87.92.38
ニスのみのヒビでしたら、美観はともかく機能面には全く心配はないと思われます。
オールド楽器やモダン楽器には板全面にニスにヒビが入ったものも有りますし、
出来て数年しか経ていない新作楽器が同様の状態で店頭に並んでいる事も珍しくありません。
乾きの速いアルコールニスが、完成後の木材の乾燥による収縮に追従できず、ヒビが入ると聞いた事があります。
(私の持っている15年モノの国産中級楽器もこんな状態です。)
本人が気にしなければそれまででしょう。
投稿者:福招き 投稿日時:2009/05/16 07:36 ---103.118.42
>じゅんさんへ
なるほど、安心しました。
そういった原理でヒビが起こるとは、、、。勉強になります。
確かに、湿度によってバイオリンの形が変化するのは実感があります。湿度が高いとかなり音が変わりますね。
とりあえず、壊れない限り私は気にしないので、これからも大事にしていきたいと思います。
投稿者:QB 投稿日時:2009/05/19 14:40 ---05.227.127
ニスの調合具合によっては、ヒビが入った後、ボロボロと剥がれてくる場合もあります。
また、手が触れるところがそうなっている場合は、木に対してあまり良い影響はありません。
処置はいろいろあります。
念のために、いつも見てもらっている専門の方に「大丈夫ですか?」とご確認なさっても損はないと思いますよ。
Q:ひょうたん型ケースの肩当て収納方法
投稿者:mairo 投稿日時:2009/05/12 22:23 ---83.9.230
長らく角型バイオリンケースを使用しておりましたが、軽さに惹かれてひょうたん型ケース(GEWAのStratoというモデル)を購入しました。しかし、肩当てが収納できません。無理やり入れている人がいるとも聞きましたのでいろいろ試してみましたが、どうしても入りません。(kunの足が折りたためない肩当て使用)皆さんはどんな工夫をして収納されているのでしょうか?あるいは無理に収納せず、楽譜などとともに別に持ち歩くのが一般的なのでしょうか?ご経験がある方、アドバイスをお願いします。
投稿者:ゴマゾウ 投稿日時:2009/05/13 09:00 ---168.206.16
アハハ、確かにね。
ケースに入りそうもない時は無理しないで別に持ち歩いた方がいいに決まってる!ただそれだけのこと。悩まない、悩まない!笑
あと・・・
身体のこと(耳鳴りも!)は勿論、医者だけれど、こと楽器に関しては地方在住の人は専門店や工房が無いのでまあ、このような掲示板に頼るのも方法だとは思うよ。
でもね、あまりに初歩的なことを聞く前にまずは自分でいろいろと手を尽くしアレコレやってみて、それでもどうしても解決しない場合に救いを求めましょう!
(それにしても軒並み弦楽器専門店のエラソーな態度や敷居の高さは何とかならんもんかね?世間一般の常識をわきまえていない奴が多すぎる!(欧米の一流ディーラー気取りかよ?)あと、やたら職人ぶって客を見下す工房も多いしね。あえて言わせてもらえば、楽器職人の分際で何様よ?へ〜、いつから本場クレモナの名工気取りかい?主客転倒も甚だしい!まあ、そうは言っても頭でっかちで理屈っぽくそのくせ楽器の腕はへたくそ!といった客も確かに彼らの勘に触るのだろうけどね・笑)
さらに、見ていて・・・
・こういった掲示板では誰にもご自分の素性を知られていないためか、にわか専門家?になってしまい、かつ長年のうちに自分自身の語録やアドバイスに酔い、ついついエスカレートしてしまう例
・虎の威を借る狐の如く、必ず常連の後にひっついて便乗回答する例(見ていると、どうもご自分にはそんなに深い知識は無い様子で相手の揚げ足を取ったり重箱の隅をつついたり罵倒するためだけに主に出現)
・私を含めて貧乏人?(笑)の(欲しくても買えない!汗)気持ちを逆なでするかの如く平気で延々と高価な楽器・弓の購入の相談を持ちかけて(まあ、その人に財力があるので仕方ないけれどね・笑)、問題はその後のスレが高価な同じ楽器・弓の所有者同士で盛り上がる例(ちっとも面白くないゾ!)
以上!(きっとまた反論・反撃の嵐が来るだろーな・笑)
投稿者:taka 投稿日時:2009/05/13 17:34 ---38.26.148
一応、荒れる前に
有名な鉄則を一言
荒らし対策としては 【スルー(相手をしないこと)】 が一番効果的
なぜなら荒らしというのは基本的に構ってチャンだからです。
以下のような行為をしても荒らしを喜ばせるだけなのでやめましょう。
・真面目に反論
荒らしを喜ばせるだけです
・説得
相手は愉快犯なので無駄
・煽り返し
スレがグダグダに荒れてしまいます
・おちょくる
一見賢い選択に見えますが、荒らしと同レベルです
投稿者:もーりん♂ 投稿日時:2009/05/13 23:43 ---155.10.131
私はメーカー不詳のひょうたん型ヴァイオリンケースを使っていました。肩当てはKUNでしたが、ヴァイオリンのネックのところに平行にして収納していました。
あと、ヴィオラの方は楽器ケースに肩当てが入らなかったので、アマオケの練習に行くときにはいつも楽譜と一緒にカバンに入れていました。ただ、それだとカバンの中身がかさばるのが非常に煩わしかったです。
その後、ヴァイオリンは自分に合うあご当てに変えたので肩当てが不要になり、ヴィオラの方は楽器の構え方を変えたら肩当てなしでもとりあえず演奏できるようになったので、当分の間はこれでやっていこうと思います。肩当てがないと持ち物が一つ減るのでスッキリします。
ただ、安易に肩当てなしで弾くことを奨励はしませんが、私個人の体験を書かせていただきました。
投稿者:ちょろ 投稿日時:2009/05/15 13:22 ---51.13.213
まぁ、値段でしかモノの価値を判断できないさびし〜人もいますからナ。
投稿者:のんちゃん 投稿日時:2009/05/17 13:42 ---60.131.117
私は今は小さな肩当てを使っていますので関係ないのですが、以前肩当てを使っていた時は、小さな巾着袋に肩当てを入れてヒョウタン型の楽器ケースの取っ手のところにぶら下げていました。
Viva la Musicaの肩当てには巾着袋が最初からついていましたよ。
Q:masakichi suzuki No2 について
投稿者:T.S 投稿日時:2009/05/11 13:05 ---133.147.80
30年ほど前に、私の田舎(山形)のとある私設?民芸館でオンボロのバイオリンを見かけました。明治・大正・昭和初期には東北の田舎ではオルガンなどなく、唱歌の時間には先生がバイオリンでイロハを教えていた。との記述を見て、当時まだ生きていた祖母(明治28年生)もバイオリンに合わせて歌ったという昔話を思い出し、なるほどなあ〜と思い、館長?に頼み譲ってもらいました。 弾けるように修理して、ほんのお遊びレベルで楽しんで現在にいたっていましたが、2年ほど前に裏板がエンドピンの力に負けたのか、側版よりはく離しはじめました。修理に出したらいいものかお金をかける価値があるものなのか迷っています。
思い出深い物なので、とりあえずはく離部分は修理しようと思っていますが、どうせならしっかりメンテしようかな?などとも・・
バイオリンは、masakichi suzuki NO2 のラベルが貼ってあります。色々調べてみたのですが、よく分かりません。。どう見ても、あまりたいしたものではないことはたしかですね。
NO2は当時のグレード番号なのでしょうか?音は大きく枯れてて、ほんとに大正ロマンを感じさせるし面白いです。
なにか教えていただける方がおりましたらお願いいたします。
投稿者:rio 投稿日時:2009/05/11 18:12 ---7.5.166
suzuki violin のホームページで
過去の機種の製造年と当時の価格を表にしていますので
参考になさってみてはいかがでしょうか?
No.2 という型番は
1907年〜1926年の間つくられ
グレードは1907年当時 16グレードの内下から5番目でした。
(1907年のグレード間の価格幅は 2〜40円です。No2は6円でした。)
古い楽器は、所有者の思い入れもあり
単純に、お金をかけるべき、かけない方が良い と
判断できるものではありません
思いで深ければ、私なら
存在意義は楽器としてではなく
一つの思い出の楽器としてみますので
直して使うと思います。
なお
物価指数だけでいえば、1907年は現在の約3,000分の1になります。
1907年はアンパン1個約1銭、鉛筆1本約2厘の時代です。
投稿者:T.S 投稿日時:2009/05/13 01:47 ---133.148.50
rioさまへ
さっそくのお答えありがとうございました。
調べて頂いて恐縮です。
まったくおっしゃる通りですね。
そんなにも時を経たものだったのですね・・・。
戦争や色々な事に巻き込まれながらも、どんな人の手を渡ってきたのか・・・。
あらためて想いをはせてしまいました。
裕福な人はもっと高価な物を買った事でしょうから、きっとこのNo2のグレードを買った人は、これ以上はお金を出せないぎりぎりの生活!しかし、バイオリンを弾いてみたい想いとの葛藤・・・店の前をうろうろ。
想像すると、親近感すら覚えてしまいました。私にぴったりのグレードです。
修理から戻ったら今まで以上に大切にしたいと思います。
ぼろぼろでほこりにまみれていたバイオリンと私の30年前の出会い。これからもこのバイオリンで遊びます。
コメントを有り難うございました。
投稿者:まさ 投稿日時:2009/05/13 13:12 ---20.108.67
現在はチェロを弾いていますが、今から約30年前私が大学生になって初めて何の因果かヴァイオリンを始めたときに弾いていたのが、まさにmasakichi suzuki No2でした。
元をただせば大学生になって始めるヴァイオリンにあまりお金は出せないと思っていたときに、そう言えば母の実家に壊れた(と言っても指板がはがれていた程度ですが)ヴァイオリンがあったことを思い出し修理できるのならとお願いして5万円ぐらいで直してもらい、学生時代はずっと弾いていました。もちろん腕も良くないですし初心者でしたが室内楽で楽しむには特にいやではないと思っていましたが、ほかの人の楽器より重い(板が厚い)印象はありました。
その楽器は実は母の実家が農家で戦時中に、どこかの音大の先生が疎開してきて食べ物の変わりにこの楽器を買ってくれないかということでもらったものらしいので、たぶん価格もそれほどでもないのかなと思っていました。買ったからにはと言うことで私の叔父はその楽器で練習してかなりの腕前になったと聞いています。
取るに足らない話ですがmasakichi suzuki No2という名前を見て少し懐かしく思ったので書かせていただきました。
その楽器は再び叔父にお返ししてまた懐かしく弾いているそうです。
投稿者:ゴマゾウ 投稿日時:2009/05/13 21:07 ---168.206.16
鈴木バイオリンの初代・鈴木政吉翁(1859〜1944)のヴァイオリンはパリ万博(1900年)で何と銅賞を取るほどの腕!だったとのこと。
やがて特殊専用機械の導入により念願の大量生産を実現します。
1907年(明治40)〜1914年(大正2)の定価表によると、ヴァイオリンは最も安いもので「号外A」というのが当時の2円。逆に高いもので「特製6」が120円。また、この頃は分数楽器の製作も開始されています。
ちなみにラインナップは号外A・B・C、No.1〜13、特製1〜6、そして分数ヴァイオリンを含めて種類は25にも及んでいたということですよ。
以上、ご参考になれば・・・
PS:ヤレヤレ、少しでもこのスレの回答の方向性を正しく是正してあげようとあえて苦言を呈し助言してあげたのに、荒らし!?とは・・・(実に視野・了見の狭い人もいるものだねぇ・汗)
では、また!
投稿者:rio 投稿日時:2009/05/13 23:30 ---95.2.121
ゴマゾウさんありがとうございます。
「特」を失念しておりました
(追記です)
鈴木バイオリンの方から教えていただいたのですが
特製といっても
年代によって(ほとんどの年代で)
特製1〜4はプレス品だったそうです
投稿者:T.S 投稿日時:2009/05/13 23:53 ---133.148.50
まさ様へ
良いエピソードですね!ちょうど30年前私も大学生でした。もしかするとまったくの同い年かもしれませんね。ちなみに私は昭和35年生まれです。私は修理にたしか3万円ほどかかった記憶があります。まさ様や叔父上様、そして音大の先生の疎開・・・その前もあるかもしれませんね。製造期間からすると、最低でも80年以上の時が流れているのですね。私も自分の子供や孫に伝えたいと思います。当時6円の響きを。温かな気持ちにさせていただきました。ありがとうございました。
ゴマゾウ様
これまた詳しくおしえていただき感謝いたします。
号外という表現もなかなか良いですね。弾いてみたいものです。
最高ランクが特製6・・・これまたはっきり「特製」ですから分かりやすい事です。rio様のお話からすると現在の3〜40万クラスの値段でしょうかね・・・。
分数もあったとはすごいですね。急速な西洋文化の流入を感じます。
コメントを有り難うございました。楽しく謎を知ることが出来ました。
投稿者:T.S 投稿日時:2009/05/14 00:08 ---133.148.50
あらら、今見たら、rio様からのコメント追記を見て、ちょっとがっかり・・・
でも事実は事実、しょうがないですね。そんな時代なのですね。
せっかくの銅賞がもったいないですね。
事実、鈴木政吉の手工作品は何本ぐらいあるのでしょうかね?
すばらしい製作家なのでしょうに・・・。
だんだん話に夢が無くなってきました。(笑)
投稿者:T.S(鈴木 尚) 投稿日時:2009/05/14 01:34 ---133.148.50
自分で続けて3回も書くのはどうかとも思いましたが、ゴマゾウ様のPSの意味が不明だったので、過去やら最近やらの質問とアドバイスなど拝見させて頂きました。それぞれの意見や感じ方など興味深くあちこちと・・・。
イニシャルでは失礼かと思い、実名で書かせて頂きます。
その方の音楽性や興味の度合い・・・特に何百万の話などは私には驚きでした。プロの方なのでしょうか?・・・。しかし、考えてみれば高級車を趣味として乗っている人も沢山いるのだから高価な楽器に見せられる人がいていいわけだし、ひとそれぞれなのでしょうね。(私も持てるものなら持ってみたい。笑)
また、その知識の凄さ!!私には日本語として解せないものも多くびっくりです。専門楽器店の方かもしれませんね。
私などは昔話のようなくだらない内容で、なんだか場違い?かな・・。しかし、そんな話でも答えてくださる方がいてありがたいことです。私のように小さな楽しみとして音楽を楽しんでいる人でも気楽に参加できるように、皆さんが少しだけ気を使ってコメントしたり意見交換していけば心地良い音楽が流れるのではないでしょうか?
私の「masakichi suzuki NO2」6円のビオロンを一流の演奏家が弾いたらどんな音楽が聞こえるのでしょうね? ストラディバリウスもびっくり! がはっ!
またいつの日か拝見させて頂きます。北海道 鈴木 尚
投稿者:rio 投稿日時:2009/05/14 04:03 ---95.2.121
T.S(鈴木 尚)様
夢を壊すようなコメントをして申し訳ありません
また、誤記もありました
「特製1〜4」ではなく、「1〜3」です
更に追記ですが「特製」という品番は、戦前と戦後に発売しております。鈴木バイオリンがいつ頃から、プレス製法を始めたのかが
わかりませんが、少なくとも戦後品はプレス品が入っており、戦前ももしかするとある時期からプレス品がはいりはじめているかもしれえません。
本当に、何度も訂正・追記をし、申し訳ありません。
私は廉価なプレス品がなければ、バイオリンという楽器と出会うチャンスはなかったと思います。それゆえ自分が使用していた、プレス製で日本の木材が使われた鈴木バイオリンを今でも工房にお願いして調整してもらいながら保管しています。どんなに安物であろうとも私にとっては思い出の品だからです。
ピアノやオルガンも簡単に購入できなかった時代、廉価で比較的大きな音が出るバイオリンは当時の学校には欠くことのできない教材だったと思います。そのような時代背景を持った楽器を引き継ぎ大切にしておられることはとても素敵なことだと思います。楽器を性能や価格だけで評価する人もいらっしゃるかもしれませんが、私はそれだけが物の価値・評価になるとは思いません。貴殿の「masakichi suzuki NO2」6円のビオロンの音色は、当時の子供たちがその音を聴きながら音楽を学んだ「時代の音」だとおもいます。バイオリンが大量生産で安価に供給されたからこそ音楽にふれることのできる子どもたちがいたのだと思うと、プレス品も含めた量産品、低価格品は大変重要な意味を持つと思いますし決して忌み嫌うものではないと私は考えています。
投稿者:鈴木 尚 投稿日時:2009/05/14 13:16 ---133.147.80
そのうち見ようと思っていましたが、昼休みに見てしまいました。
rio様・・・ごもっとも。その通りだと思います。
さて、楽器店より政吉no2の修理の面白話です。某工房の説明。
楽器の価値・・・・・0円
そもそも、構造に問題あり、構造にゆがみ・ずれがあり現在ではありえない破損状況。当時、見よう見まねで、形だけ作ったような感あり、裏板の剥がれは修理可能だが、弦を張ることは薦めめられない。完全に破損するおそれあり。
簡単にまとめればこんな感じ・・・。とにかくはく離部分はしっかりはり付けて頂くことにしました。
では。
Q:FINKELチェロの弓
投稿者:キチキチ 投稿日時:2009/05/13 19:54 ---249.184.60
こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいております。
皆様、大変知識が深い方ばかりでただただ感心するばかりです。
さて、本題ですが先日、人から、FINKELの4/4チェロ弓を譲っていただきました。まだ試し奏程度ですが結構、芯がありいい音色で気に入っております。しかし、弓についての素性がわからず、日に日に気になるばかりです。どなたか製作者について、一般的な評価どれくらいの価格帯のものなのか、ご存知の方いらっしゃいませんか?
現行商品ではJ.S FINKEL E.ERNST などの刻印の商品はあるようですが、私の入手したもの少し違うんです。
どなたかご存知の方よろしくお願いいたします。
刻印 *S.FINKEL* GERMANY
フェルナンブコ シルバー金具、黒檀フロッグ オクタゴンスティック
パリジャンアイ
以上が現在、わかっている仕様です。
投稿者:toy 投稿日時:2009/05/14 05:02 ---170.195.237
弓はあまり詳しくないのですが、レスがつかないので。
刻印がGERMANYならば、Johannes S.Finkelではなく父親のSiegfried Finkel(ジークフリード)ではないでしょうか?
だとすると、25才くらいの時にスイスに移っているので若い頃の作品って事になります。
ネットで見てみると価格帯は$2,000〜$4,000位のようです。
Q:バイオリンのペグが緩みません
投稿者:どんどん 投稿日時:2009/05/11 19:12 ---220.134.21
しばらく触っていなかったヴァイオリンですが弦を張り替えようとしたら、ペグが硬くて緩みません。
ADGはやっと緩みましたがE線が全くビクともしないのでどうしたらよいのか教えてください。
これはもうペンチではさんでまわさないと回らない感じです。そんなことをするとペグが折れてしまう気もします。手で回す分にはどんなに力を入れても折れることはないのでしょうか?
投稿者:たかとし 投稿日時:2009/05/11 21:39 ---31.73.139
ペグの材質が何かにもよりますが、黒檀、あるいは紫檀なら結構硬い木材なので、よほどの事では折れることはないと思います。
手で回らないならペンチを使う手もあるでしょうが、その時は、ペグとペンチの間に厚手の布を噛ませてペグに傷が付かないようにするといいのではないでしょうか。
絶対折れないとは言い切れませんが、試してみては如何でしょう。
投稿者:どんどん 投稿日時:2009/05/12 06:48 ---220.134.21
たかとし様
回答ありがとうございます。やってみます。
ところで、本体重量が当初446gと記憶しているのですが今計ってみると462gになっていました。これは湿度のせいか?そのせいでペグがキツくなっていたのかと思いました。
皆さんのヴァイオリンの重量はどのくらいなのでしょう。
投稿者:スティールラバー 投稿日時:2009/05/12 08:49 ---228.39.89
ペンチではさんで無理やり回すってのはやらないほうがいいと思いますよ〜。ペグが折れるのはまだ良いほうで、下手したらペグボックスのほうにペグ穴からヒビが入りますよ。
ちょっと前に湿度でペグが廻らなくなったときの対処法のスレッドがあったと思います。
投稿者:スティールラバー 投稿日時:2009/05/12 14:30 ---94.43.61
それと湿度で重量が軽くなったとしたら、乾燥しているという事なのでペグは緩くなると思います。
以上、私見です。
投稿者:弦喜 投稿日時:2009/05/12 22:29 ---115.120.23
私も、無理した結果のペグボックスのクラックが一番心配です。
スティールラバーさんが書かれている、”ちょっと前に湿度でペグが廻らなくなったときの対処法のスレッド”は、まだ過去ログに入っていないようです。
確か、東南アジアに行かれている方の相談で、暫定対処法は、冷蔵庫に入れる、と乾燥剤と一緒に袋に入れる、などだったように思います。
いずれも、乾燥させるというのがポイントでしょうから、日本でなら、後者あたりでペグボックス近辺のみ攻めてみるのはいかがでしょう。エアコンをきつくかけた部屋にしばらく置くのも効果があるかもしれません。
460gはどちらかと言えば軽い方でしょう。我が家にあるヴァイオリン達は、430g〜530gくらいに分布しており、フィッティングの材質や形状の差だけでも40gくらいはばらつきますので、ほかの人にヴァイオリンの重量を聞いてもほとんど参考にはなりません。
私は、素直に弦楽器店に持って行く、というのが正解だと思います。
投稿者:コクシネル 投稿日時:2009/05/12 23:25 ---25.172.55
無理に回してペグが折れると、自分では取れなくなり、結局は工房に持っていくはめになります。(経験者です。 但し分数楽器でしたが。)
とくに分数楽器は、普段アジャスタで調弦することが多く、気がつくとペグが固まっていることがあるので、時々回しておきましょう。
投稿者:どんどん 投稿日時:2009/05/13 22:26 ---220.134.21
回答くださった方々、ありがとうございます。解決しましたのでお知らせいたします。
弦喜さまの「乾燥させるのがポイント」とのアドバイスにピーンときました。
4畳半の室内を締め切って除湿機を24時間回しっぱなし、10リットルの水が取れました。湿度60%から35%になったのでペグを手で回してみましたら、な〜んと回りました。
ペグは黒檀ではなくツゲ材?(茶色の)のようでボックスと馴染みやすいのでしょうか?
たったこれだけの湿度でこんなにも調子が違ってくるということを初めて感じました。
どうもありがとうございました。(楽器店って近くにないんですよね)
Q:TUA SILVIO
投稿者:びおら弾き 投稿日時:2009/05/07 03:23 ---38.34.209
ビオラを買い換えようと思っているアマチュアです。
先日、ある楽器屋で試し弾きをして、「いいなぁ」と思ったビオラがあり、購入を迷っています。
製作者は「TUA SILVIO」で1930年ごろNICE(フランス?)で作られたものです。
売値が220万で、財布に怒られるのであきらめようと思いましたが、「150万まで値引きするよ」と言われて、心がときめいています。
製作者の「TUA SILVIO」についてもう少し情報があれば、購入に踏ん切りがつくのですが、なにか教えていただけないかと思い投稿しました。
ご教授願えれば望外の喜びです。
投稿者:SP2 投稿日時:2009/05/07 11:20 ---241.143.230
1894年トリノ生、ミラノのRadrizzaniに師事。ガルネリデルジェズのコピーを製作、優美なスクロール、オレンジレッドのオイルニス、古材を用いて製作し、修復も上手だった。息子のSerge(1927年生)も製作家として1944年以来父の工房で製作を助けた。
あまり名の知られた製作家では無いようでこの程度しかわかりませんでしたが、何か参考になれば幸いです。
投稿者:びおら弾き 投稿日時:2009/05/07 11:34 ---47.27.16
わあ、こんなに早くレスがいただけるなんて!
しかも詳しく教えていただき感激です。
SP2様、ありがとうございます。
オレンジレッドのオイルニスってことは赤っぽい作品が多いのかな。購入を考えているビオラはかなり黄色っぽいです。
もともと薄い色の方が好みだったのでそれでいいのですが(^^)v
いろんな意見かき集めて納得して購入しようと思います。
投稿者:弦喜 投稿日時:2009/05/07 21:56 ---115.120.23
TUA SILVIO violin
あたりをキーワードに、検索エンジンで探すと、まともなオークションに出品されたヴァイオリンの画像が見られます。
>製作者は「TUA SILVIO」で1930年ごろNICE(フランス?)で作られたものです。
ラベルは本体と違うもののことの方が多く、ラベルを信じないとすれば、上記は何を根拠にしたものなのでしょうか。その楽器店がまっとうなオークションでそのように鑑定されたものを購入した、とか、著名な鑑定家がそうであると言った何かの証拠があるのでしょうか。そうでなければ、そのようなラベルが貼られただけの楽器として一旦は見た方がよいです。
以下、私見です。
少ない情報ながらも、ネットや文献で見る限り、本物であれば、フランスというよりも、モダンイタリーとして扱っているものも多く、状態がよければ高くはない買い物でしょう。
特にヴィオラというものは、いろいろなサイズがあり、ヴァイオリン以上に音も様々ですので、「これだ!」と思うものが見つかり、購入できる資金があるなら、それが買い時とも言えますが、このケースではかなりの金額となりますので、(1)真贋の証拠の明確化 2)そのお店での下取り保証(ストラッドさんのところでは購入金額の80%)によるリスク回避、などは、恋は盲目とならないために必要かと思います。あるいは覚悟の上で盲目的に購入するのであれば、それは後々後悔もないでしょう。
また元々の値段が値引き覚悟の値付けの場合もありますので、値引きでのお得感ということは考えずに、素直にその金額に見合う楽器か、ということを考えるべきかと思います。
投稿者:コクシネル 投稿日時:2009/05/07 21:57 ---25.173.56
その楽器の本当の作者が、必ずしもラベルに書いてある作者とは限らないので、ご注意ください。 もちろん楽器そのものの品質について、提示された価格で納得いかれるなら、問題はありませんが。 ただラベルの作者名を今回の購入決定の鍵とされているようなので、ちょっと心配になりました。 あまり有名な作者ではないようなので大丈夫かもしれませんが、一応念のため。
投稿者:びおら弾き 投稿日時:2009/05/08 14:19 ---47.27.16
弦喜様、コクシネル様
丁寧なレス、ありがとうございます。
大変、参考になり、感謝いたします。
製作者名にはこだわっていないのですが、どんな職人だったのか知った方が楽器に愛着がわくと思い、ちょっとでも知りたくて投稿しました。
そもそもは、ラベルや値段を見る前に、楽器の音を気に入りました。
「一目惚れ」みたいな感じで、すでに盲目的になりそうですが、私にとっては高額なので慎重になっております。
「真贋の証拠の明確化」ですね。楽器店の店長に聞いてみます。店長が現地に行ったときに購入したらしいので。
「ラベル」というより「店長」を信じるといった方が正確かもしれません(^^;
投稿者:びおら弾き 投稿日時:2009/05/12 00:06 ---38.22.202
<追記>
ちょうどバスパーの修理の必要があったので、楽器を開いたところ、表板裏板の両方の裏側に、ラベルと同じ内容の「サイン」があったとのことで、店長いわく「ラベルは製作者等のあてにならないが、サインの信頼性は高い」とのことでした。
ともあれ、状態も良く、音の感じも好きなので、思い切って購入しようと思います。
いろいろありがとうございました。
投稿者:rio 投稿日時:2009/05/12 04:44 ---95.2.121
否定的なコメントで申し訳ありませんが
表板裏板の両方の裏側に、ラベルと同じ内容の「サイン」
については
署名の大きさ
署名の筆記体(書体)
署名した筆記具の種類
署名した箇所
等が
同じ製作者の他の楽器にも
共通することかどうかがカギとなります
(TUAの名前の楽器は、1970年代後半に楽器店で何台か見た記憶があります。そのころ楽器を取り扱っていたお店なら製作者に関する情報を持っているかもしれません。)
サインの信頼性 は
それ次第ということ と私は理解しています
フランスの某製作者の楽器は、
鉛筆で表板のある位置に署名をすることで有名ですが
コピーものでさえ、そこに鉛筆で署名を書いてあることが多く
売値をつりあげるために、楽器をオープンして
細工(ラベルの張り替え、内部のいろいろな個所に
署名や焼印、あるいは古く見える薬品処理など)
をして販売するのは残念ながらよく見ることです。
また弦楽器専門店であれば、オープンしなくとも
楽器内部を見ることができる道具を所有しているか
同業から借りることができ、内部の状況もわかるはずですので
オープンしてサインがあったことがわかるのは不自然さを感じます。
「ともあれ、状態も良く、音の感じも好きなので、思い切って購入しようと思います。」とのことですので、真贋に関係なく購入されることと拝察いたしますので、関係ないと思いますが…
Q:ヴァイオリンのメーカーについて
投稿者:かい 投稿日時:2009/05/11 21:35 ---31.73.139
EL TESORO と書いたラベルのヴァイオリンを所持しておりますが、このラベルについて、何かご存知の方いらっしゃいませんか?
色々と調べてみましたが何も分かりませんでした。
宜しくお願い致します。

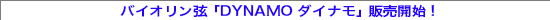
Q:表板の厚み
投稿者:さおり 投稿日時:2009/05/21 12:19 ---136.161.68
携帯からですが、質問です。
私の愛用するビオラ(昨年購入)は、F字孔のところで見ると、表板の厚みが2〜2.2ミリくらいです。
友達から「薄すぎるんじゃない?」と言われ、ちょっと不安になっています。
音に不満はありませんが、「薄い楽器は後で鳴らなくなることが多いって聞いたよ」と言われ、さらに不安に(-_-;)
購入した店の人は、「確かにちょっと薄いけど、1920年くらいの製作で、今も良く鳴っているので大丈夫」と言ってましたが、いかがなもんでしょうか。
参考にならないと思いますが、価格は110万円のものでした。
投稿者:弦喜 投稿日時:2009/05/21 23:58 ---115.122.60
「薄い楽器は後で鳴らなくなることが多い」は新作について言われることですので、その楽器が出来上がって90年も経っていて今鳴っているなら、気にしなくてよいと思います。90年鳴っていて、数年後に板の厚みが原因で突然鳴らなくなることはないでしょう。
板の厚みは、全体的なバランスが重要ですので、f字の箇所だけでは一概に判断できません。また、状態もよく、薄めで丈夫でよく鳴る(遠くまで音が通る)のであれば、f字の箇所で薄くてもよいのではないでしょうか。
なお、近くでは鳴るけれど、遠くで聴いたり、ホールで聴いたりしたときに、密度の薄い音で音が届かない場合は、表板が薄いことが関係するかもしれません。
投稿者:さおり 投稿日時:2009/05/22 14:06 ---146.174.71
弦喜様
非常に分かりやすい説明ありがとうございましたm(_ _)m
すごく安心しました。
遠くでよく聴こえるかどうかははっきり確認したことはありませんが、前の楽器より楽器全体が響いている感じがするので、満足しています。
厚かましくもさらに質問なのですが、今のビオラはCG線を引くと「チー」といった摩擦音みたいな音が聞こえます。(分かりにくい説明ですみません)
ピチカートでは聞こえない音なので、楽器の不整備ではなく弓のせいかとも思ったりしてるのですが、高音域では聞こえません。
合奏だと気にならないが一人で練習すると気になる程度です。
なにか参考意見あれば嬉しいです♪
投稿者:弦喜 投稿日時:2009/05/22 22:36 ---115.122.60
>今のビオラはCG線を引くと「チー」といった摩擦音みたいな音が聞こえます。
この音がどのようなものなのか、いくつもの可能性がありますので、残念ながら想像ではわかりません。従って、あって当然のこすれ音なのか、どこかに何か不具合があって変な共振がおこっているのか、お使いの弦の特徴なのか、などが特定できませんので、申し訳ありませんが、回答できません。まずは、購入元の楽器店に、現物で現象を見せながら、相談するのが一番よいと思います。