弦楽器 Q&A
弦楽器に関するいろいろな疑問にお答えします。
2023年12月31日をもちまして、新規投稿・コメントの書き込みを終了させていただきました。
5203件のQ&Aがあります。
Q:表板・裏板の削り
投稿者:YE 投稿日時:2005/11/11 18:25 ---217.58.84
よく「この楽器は表板や裏板を削りすぎてダメになっている」「板が厚すぎて鳴らない」という言葉を聞きます。確かに、指で押してそれと判るほど薄い板の楽器の場合は判りますが、そうでなくとも、そのような話をよく聞きます。しかし、そもそも製作者でない限り、作られた当初の楽器の板の厚さが判るわけでもなく、また、楽器を開けてみない限り、板の厚さは判りそうもありません。
1.なぜ、板の厚さが判るのでしょう?
2.なぜ、板が削られた、ということが判るのでしょう?
3.なぜ、鳴らない原因が板の厚みにあると判るのでしょう?
ご教授願えれば幸いです。
投稿者:かめ 投稿日時:2005/11/11 19:27 ---196.107.130
1.板の厚みを測る道具があります。それを使えば、正確な板の
厚みがわかります。
板を軽く叩いた時の音でも、板のだいたいの厚さはわかり
ます。
楽器を弾いてみたときの感触で、板が厚いか薄いかわかりま す。
楽器を持ってみて、明らかに軽い場合は板が薄い場合が
ほとんどです。
2.(楽器の素性が確かだとして)板の内側が明らかに表よりも
新しく見える場合は、板が削られています。ラベルと板の
変色の度合いの違いでもわかります。
板の接着面の膠の状態を見ると、板を開けられたことがあ
るかどうかがわかります。接着面の削り直しは通常あまり
しませんから、外からわかる板の厚さと楽器の内側の板の
厚さが極端に違えば、削り直されています。
投稿者:隣の女の子が好きだった 投稿日時:2005/11/11 20:32 ---110.60.85
3についてがまだ出されていないので。
「3.なぜ、鳴らない原因が板の厚みにあると判るのでしょう?」
おっしゃる通り、鳴らないだけでそれが即ち「板の厚み」が原因などと言えるはずがありません。ですから「判るのでしょうか?」の通りで「判りません」。ではなぜそのように受け取れる発言がたくさんあるかと言えば、厚い板は物理の原理の通り振動しにくいからです。昔、好きな女の子が隣にいて、一緒に太鼓を叩いて紙に耳をつける実験をしたのをよく覚えています。あの子は今頃何をする人ぞ・・・。おっとっと話がズレました。楽器が鳴らない要因は他にも山ほどあります。魂柱の位置、駒の調整、割れ、弦などなど、だから板だけを要素に「鳴らない」などと言う人がいたら、それこそ恥ずかしいことです。おっしゃることは正論だと思います。
投稿者:かめ 投稿日時:2005/11/11 21:28 ---196.107.130
「分厚い板は鳴らない」というよりは「鳴らせない」という感覚
のほうが当たっているような気がします。良質の板でやや厚めに
削られている楽器の場合、その板を振動させるようなボーイング
ができていない奏者が結構いるようです。
確かに薄い板の方が楽に音が鳴るので、ある意味でたらめな
ボーイングでも音になります。
あと、新作の時に少し厚めに削っておいて、経年変化で木材の
含水率が低下してきたときには素晴らしい振動特性を示し鳴る
ようになる楽器もあるようです。それを、単に板が厚いからと
削られてしまった1900年前後の楽器も多く見られるよう
です。
投稿者:YE 投稿日時:2005/11/11 23:01 ---217.58.84
かめさん、隣の女の子が好きだったさん、お返事、ありがとうございました。
1.板の厚みを測る道具があるのは知っておりますが、中を開けずとも測定できるのでしょうか?
>板を軽く叩いた時の音でも、板のだいたいの厚さはわかります。
板の硬さ・材質・ニス等でタップ音はかなり変わると思います。タップ音だけで厚みの見当をつけるには、他の要素の影響があまりに大きいと思いますが、その点如何でしょうか?
>楽器を弾いてみたときの感触で、板が厚いか薄いかわかります。
私にはあまり判りません。最初に板の厚さを教えてもらって楽器を弾く、という経験を積み重ねていれば学習できますが、自分の弾いている楽器の板の厚さを知ることなく弾いてきたので、経験からの見当が付かないのです。どのようにして見当をつけていらっしゃるのか、興味があります。
2.オールドの場合は、板の内側が外側から推測される古さよりもかなり新しければ削っているという見当が付きますが、モダンや新作の場合、なかなか中が古色にならず、削られているかどうかの見当が付きにくいように感じます。如何でしょうか?また、膠の接着面に関しては、実際に開けて詳細に検討しないと判らない、ということはないのでしょうか?
3.厚い板の楽器は正しいボーイングでないと鳴らしにくい、と言う話はよく聞きます。しかし、1.で述べましたように、最初に楽器の板の厚みを教えてもらってから楽器を弾いて、厚みと音の出し方の相関を学習するのならともかく、そういう経験のない多くのプレーヤにとっては、演奏から判断するのは困難ではないか、という気がします。この点、如何でしょうか?
純粋に疑問に思っておりますので、ご存知の方・また何がしかの示唆をお与え下さる方がいらっしゃれば、お教え頂ければありがたく存じます。
投稿者:mino 投稿日時:2005/11/11 23:49 ---33.76.136
長年弾き込んでも一向に鳴らない楽器をある工房に持ち込んだところ、板を削るしかないと言われたので削ってもらい、その結果とても良く鳴るようになりました。業者からの依頼で鳴らない楽器の板を削ることは良くあるそうです。
職人さんによると、適切な厚みかどうかはタップ音でわかるとのことで、薄くなりすぎてはいないかと聞いたところ、実際に薄すぎる楽器のタップ音を聞かせてくれましたが、確かにその楽器のタップ音は薄い感じがしました。ご参考までに。
投稿者:YE 投稿日時:2005/11/12 01:51 ---217.58.84
minoさん、ありがとうございます。
ただ、タップ音でわかるのは、その板の厚みが適切かどうか、ということで、厚さ自体が判るのではなさそうですね。つまり、「このタップ音だと適切な厚みに削られている」ということが判るので、「このタップ音だと厚さは**mmだ」ということではなさそう、という事です。
ここまで書いて、「板が厚いか薄いか」は材質に依存する、という当たり前の事実を再認識しました。よく言われている板の厚さは、適切かどうか、という意味で論じられる場合と、物理的な厚さで論じられる場合との二通りがありそうですね。
投稿者:パスツール 投稿日時:2005/11/12 11:13 ---5.4.81
板の厚みが適切かどうかについては、弾いた感じでも結構わかります。板が薄すぎる楽器は、楽に音が出ますが耳元でうるさく、楽器の芯から音が出ている感じがしません。またどのように弾いても同じ質の音が出るので、音色の変化がつけにくい。話少しずれますが、高性能な楽器には、弾いた際にある種の抵抗感があって「強い楽器」というような言われ方もしますが、板の厚さもある程度関係しているかもしれません。最近の楽器では、コラード・ベリの板が厚そうです(少し厚すぎるかも)。性能の高い強い楽器に対しては、それに打ち勝つ演奏技術が必要で、高価な名器を購入しても、相応の腕がないと鳴らしきれない、ということになるようです。
投稿者:磯の珍味 投稿日時:2005/11/12 12:11 ---13.98.209
楽器が鳴る、ということと楽器の板の厚さのことで色々書き込みがあったのでちょっとコメントさせていただきます。まず、楽器が鳴るということは、どういうことなのでしょうか?弾いていて気持ちが良い鳴り方がする、とかコンサートホールで良く響くとか色々あると思います。板を薄く削った楽器は鳴りは良くなりますが、削り方がまずいと近くで聞いて大きな音がしているだけで遠くにはあまり届いてにない場合があります。(そば鳴り、なんて言ってますが)逆に、本物のストラドなどは使っている人の言によると弾いている人にとってはそれほど大きな音ではないけれど遠くに音が届いている、というケースもあるようです。また、板を削ると音に厚みが無くなる傾向はあると思います。楽器の板の厚さは作者のポリシーなどもあり一概に言えないというのが私の経験です。空気が湿気っぽい日本では板が厚い楽器は鳴りにくい傾向がある様な気がします。空気が乾燥した欧米では良く鳴る楽器が日本に来ると鳴りが悪くなるなんていう話を聞いたこともあります。(あくまで聞いた話ですが...)音は所詮個人の好き嫌いの世界の問題になってくるのであまりナイーブならなくても...。大体どの人も色んな楽器を弾いてみて、他人の意見を聞いてなんとなく自分の理想の音はこんな感じかな?という人が多いと思います。(大体楽器屋さんに入ってくるドイツ、イタリアの楽器が基準かな?私も含めてそんな感じの人が多いのでは?)ですから、プロを目指すのでないのなら板厚に神経質にならず、自分の好きな音を見つければ良いのでは?ただ、ボーイングがしっかりしてないアマチュアにとって板が厚い楽器は鳴らしきれなく欲求不満の原因になる可能性があるので要注意かな?という感じです。
投稿者:猫丸 投稿日時:2005/11/12 17:01 ---150.237.142
たたいて、板の厚みが分かるかというと、分かりません。
たたいて出てくる音は、表面振動であるからです。
板の厚みを知るためには、開けてみるしか方法がありません。
何とか、開けないで知る方法がないのか、楽器職人の悩むところですが
結局、たたいて反応を見て、類推するしか有効な方法は現在ありません。
責任を持った仕事をする、楽器職人のいる楽器店は、古い楽器を仕入れた場合、一度解体して点検します。
また、新作、あるいは再点検する意義を認めない楽器の場合は、何もしないのが普通です。
投稿者:hac 投稿日時:2005/11/12 22:01 ---189.245.49
hacklinger gauge という磁石を使って楽器を開けずに厚さを測る機器がありますよ。
投稿者:YE 投稿日時:2005/11/13 01:30 ---217.58.84
みなさま、貴重なご意見、ありがとうございました。
パスツール氏のご意見は知識としては持っているのですが、実感が湧かないのです。前にも書きましたが、演奏する楽器の板の厚さに関する予備知識なしでいつも楽器を弾くので、楽器がそばなりしたり、鳴らし切れていないからといって、それが板の厚さに関連があるのか、私には相関関係が判らないのです。あらかじめ演奏する楽器の板の厚さに関する予備知識があれば学習できるのでしょうけれど。パスツール氏はどのようにしてその学習をなさいましたか?長年の経験、でしょうか?
磯の珍味氏のおっしゃる通り、本来は板の厚さにこだわる必要はないのでしょうね。私がここで伺った理由は、先日ある楽器店(楽器を購入した楽器店ではない)に行き、自分の楽器と他の楽器を弾き比べていたところ、私の楽器を手にとって見ていた店主に、「この楽器は板が削られている可能性がある」と言われたからです。私の楽器はコーティングのために非常に薄いニスがかけられているのですが、「コーティングされている割には裏板のタップ音が低い、それに一度ラベルを外した形跡がある。楽器はラベル通りの制作者なので、理由は裏板を削ったことしか考えられない。オリジナリティが損なわれているので価値が…」というのですが、あまり科学的ではないし、どうも納得できないのです。そこで、開けずにタップ音と見ただけで削ったかどうか判るものか、お伺いした次第です。ですから、猫丸氏のご発言には共感できると同時に、安心致しました。それにしても、hac氏のお教え頂いたhacklinger gaugeは知りませんでした。開けずに厚さを測る機械があるんですね。驚きです。
それにしても、多くの方々から貴重なご意見を頂けたこと、改めてお礼申し上げます。
投稿者:猫丸 投稿日時:2005/11/14 20:30 ---2.157.33
>開けずに厚さを測る機械があるんですね
計ることの出来るのはf字穴の周辺と表板の部分だけです。
裏板まで計るのはむりです、ゼロ点の基準が取れないでしょう。
一番確実な方法は、板に小さな穴を開けるという乱暴な方法ですが、ガルネリ(デルジェス)にそのようなものがあります。
音響的に影響は無いのでしょうが、とてもやる気にはなれないでしょう。
アメリカでは、医療用のCTでX線断層写真を撮っている例がありますが、研究目的以外には費用がかかりすぎて使えそうにありません。
表面が保護のためにコーテイングされているのなら、それなりの職人さんが気を付けて扱っていると推測されますが、仮に板が削られたとしても、よほどひどいことになっていなければ、気にすることはないと思います。
タップ音だけであれこれ言う職人は時々見かけますが、信頼の置けるキャリアーの職人さんはもっと根拠のある発言が多いように思います。
投稿者:クレーメル 投稿日時:2005/11/14 21:08 ---110.59.179
日本の測定、測量技術は世界一です。ミツトヨ(川崎市)も世界の最先端をいく企業で、こちら(行ける範囲に在住で了解を得られたら)に事情を伝えて赴けば、ほんの僅かな時間で暑さなど訳なくやって頂けることでしょう。実はこの企業を訳あって見学したことがあり、その時は髪の太さなどを測ってくれました。話題とは全然関係ありませんが、こんなことも可能だということで・・・。
投稿者:クレーメル 投稿日時:2005/11/14 21:10 ---110.59.179
暑さ→厚さ の間違いでした。申し訳ありません。
投稿者:Hiro 投稿日時:2005/11/15 08:32 ---66.159.132
私も、楽器の厚みは、弾いてみて感触で大体わかります。薄い楽器は音は出しやすいですが、ポテンシャルが低くて fff などで弾こうとすると音がつぶれてしまい、好きではありません。
厚みのある楽器は、楽器を鳴らす技術を持った人でないと鳴らせないのだと思います。本当に楽器を鳴らす技術を持っているひとは、音大などに行く人のなかでも少数だと思います。
あるプロの方から聞いた話ですが、昔ガルネリデルジュスを楽器店から借りていたそうですが、始めは全然鳴ってくれず、鳴らすのに1週間ほどかかったそうです。名器は人を選ぶのだと思います。
工房の人の話では、楽器店からの要望で、古い名器の板を削ることが多いそうです。楽器を鳴らす技術は持っていないけど、お金はふんだんにあって古い高価な名器を欲しがる人に対する対策みたいです。要は商売はじめにありきですね。
ヴァイオリンという楽器は(特に名器は)、何百年もかけて何人ものプレイヤーに弾かれる、いわば全人類の財産だと思います。個人的な小さな私欲のために、全人類の財産である楽器に取り返しのつかないことをするのは、大きな罪、だと思いますがいかがでしょうか。
強い憤りを感じます。
投稿者:パスツール 投稿日時:2005/11/16 13:19 ---5.4.81
板の厚さのせいばかりではないと思いますが、優れた楽器は、弓や奏者との相性もあり、本来の音が出せるようになるまで数週間かかるように思います。ストラドでは数ヶ月以上かかったという話もよく聞きます。
知り合いのチェロ奏者(某国オケ首席)は、楽器を探していた時、偶然あるルジェリにめぐり合い、借りて1週間ほど弾いていたが、どうにも音が出なくて気に入らず、返す予定だった。しかし2週間目に彼の奥さん(バイオリン奏者)が、離れた部屋で音が家中に響き渡っているのに気付き(その時本人はまだ気付いてなかった)、可能性を信じて無理して借金して購入、現在は彼のメイン楽器として大活躍しています。
高価な名器の板を、鳴らしやすくするために更に薄く削るなど、とんでもない話です。まともな職人なら、そういう調整は頼まれても引き受けないようにも思います。また不思議なことに、名器は奏者を選ぶので、弾けない人の前に本当の名器が現れることは、そうそう無いとは思うのですが…(そう願いたいです)
投稿者:ゆうな 投稿日時:2005/11/16 15:36 ---2.10.217
>ヴァイオリンという楽器は(特に名器は)、何百年もかけて何人ものプレイヤーに弾かれる、いわば全人類の財産だと思います。個人的な小さな私欲のために、全人類の財産である楽器に取り返しのつかないことをするのは、大きな罪、だと思いますがいかがでしょうか。
アフリカや東南アジア、中央アジアにはバイオリンの存在すら知らない人がいくらでもいます。そのような楽器を「全人類の財産」などと呼ぶのはいささか無理がある気がします。驕り高ぶりすぎではないでしょうか?
板を削る事、すなわち手を加える事に関してはどっちとも捉えられると思います。それで実際に良くなったのであればそれで良いですし、ある程度の実験的なことをしなければ楽器の進歩は生まれません。実際、ヴィヨームが現代のバイオリンのスタイルを完成させるまでに壊した名器の数は数え切れないと聞いた事があります。それでも手を加えること自体を否定するのですか?
投稿者:Hiro 投稿日時:2005/11/16 17:41 ---66.159.132
もし板を削る人がストラディバリよりも優れたヴァイオリンを作る技術を持っていたなら話は別です。いや、例えストラディヴァリであっても他人の作った名品には手を加えるべきではないでしょう。誰がその価値を判断できるのですか?その方が思い上がりだと思います。謙虚さの足りない人が世の財産を破壊するのだと思います。
Vuillaume が何台も名器を壊したなんて話は私は聞いたことがありません。それに彼は名工ですが「現代のバイオリンのスタイル」は彼が作ったわけではないと思います。一方で彼は商売人だったので、名器の表板を開ける位はしても再生不可能になるまえ壊したり手を加えたりして価値が下がるような事はしなかったと思います。中級以下のクラスの楽器では色々と試したかも知れませんが。
楽器店の意識も様々で、例外かもしれません非常に粗雑で不器用なな修理人もいらっしゃいます。ある店を訪ねたら、ガダニーニの表板が開けられていましたが、むりやりひっぺがしたようで横板に表板の破片がいっぱいついていました。本物かどうかは知りませんが。楽器の扱いもとても乱暴で見ていてこちらがハラハラしました。その人が自分で作ったという楽器も、見るからに醜い楽器で、そのような物を自慢げに平気で見せるようなその楽器店には、恐ろしくて絶対、自分の楽器は預けられないと思いました。
「全人類の財産」は別に、存在を知らない人が世にいても全く問題ないと思います。タリバンの大仏も破壊されましたが、世の中の何パーセントの人がその存在や価値を知っているでしょうか。壊すのは簡単ですが再生されるのが非常に困難なものは世の中にたくさんあります。物の価値が分からない無邪気な人がこの世にいる限り、我々共通の文化や伝統や財産を守っていくのはとても難しいと思います。
あと、なかには楽器の扱いがとても粗いプレイヤーがいますが、例えば1年で3つの傷をつけるとすると100年経ったら傷だらけになります。名器は数百年単位で使用されます。もし私が楽器店を経営したなら、粗雑な人には例え高額を払ってくれるにしても名器はあまり売りたくありません。
数十万円程度の楽器なら「人類の財産」というわけでもないでしょうし、板を薄くして鳴りやすくし、売りやすくする様な作業は私はあまり気になりませんが。
投稿者:ks 投稿日時:2005/11/17 05:00 ---98.106.243
この問題については大変興味がありました。私としてはHiro様のご意見に賛同します。1回も作品を作ったことのない工房の職人がイタリアの名器、やモダンの作品の板を削って鳴るようにしたなどはありえないとおもいます。作品の破壊以外になにものでもないと思います。製作者として自分の名前を明確にラベルで表示し世に出しているわけですから調整が正常ならばその製作者の個性だとおもいます。バリバリ鳴る楽器が好きな人はそのような個性の製作者の楽器を選べばよいでしょう。おとなしい音の楽器を板を削ってバリバリ鳴る楽器にするなどおもいあがりです。量産品についてはそのようなことがあるのかとはおもいますが。いずれにせよ板を削って鳴るように出来る職人がいるならばその職人が作った楽器は皆んな素晴らしい楽器になるのでしょうか。
投稿者:cremona2号 投稿日時:2005/11/18 05:41 ---0.51.188
YEさん 投稿日:2005年11月13日(日) 01時30分 の投稿で
「コーティングされている割には裏板のタップ音が低い」と
書いていますが、個人的にはかなり疑問です。
確かにニスを塗りすぎると鳴りにくくなるのは事実ですが
表面保護のニスごときで人間の耳で聞き取れるほどの変化が
起こるとは思えません。まあ、表面ニスをテンコ盛りに
塗りたくれば分かるでしょうけれど・・・
投稿者:Hiro 投稿日時:2005/11/18 09:42 ---66.159.132
>>YE氏:
>>なぜ、鳴らない原因が板の厚みだとわかるのか?
これは、なかなか難しい問題だと思います。色々コメントされた方の意見は大体、「なんとなく感覚でわかる」といったものですよね。どこにその根拠があるのか?と聞かれると難しいと思います。
各ヴァイオリンの音色の個性を表現しようと思うと、その変数の数は非常に多いと思います。また、その音色の個性に影響を与える方のパラメータの次元も非常に高いですよね(駒の形状、板の厚さ、テールピースの材質、肩当、ナットの形状、、、)
音の世界ほど、工学やサイエンスが人の耳の性能に追いついていないものはないと思います。ですから例えば高級オーディオの世界はどうしてもオカルトチックになってしまいます。
なぜ弾いて厚みが分かるか?と聞かれると、人が無意識のうちに様々な弓圧やボウスピード、アタックなどを試し、感覚的に経験則で捉えているとしか答えられないのではと思います。科学的な話では無いので、勘違いや思い込みも多々あるかもしれません。客観的な指標みたいなものを提示するのは難しいのではと思います。
板が厚めの名器というのは、弾き始めは全然鳴らないけど「これは、弾き込めば鳴りそうだ」と“なんとなく”分かります。音に芯があるというか、独特のソリッドな振動感があるというか。それは駒や他の要素ではなく、板の厚みが大きく関与しているだろうと、これも感覚で思います。一方で、本当にただの鳴らない楽器は始めから、弾きこもうとする気も起こりません。私はあくまで下手糞ないちアマチュアなので意見を言うのは僭越で恐縮ですが。
投稿者:ギター弾き 投稿日時:2005/11/18 14:17 ---44.157.216
こんにちは。
板の厚さとかは、弾き手はあまり考えてなくていいと思います。音がよければいいのです。
バイオリンは詳しくないのですが、これまで経験から言いますと、名器と言われる楽器は板が薄いです。薄いけど、密度感のあるしっかりした材料を使っています。そのほうが板の振動特性がいいのだと思います。ギターはバイオリンと逆で、駒が弦で引っ張られるので、薄い表面板は駒の周辺が盛り上がってきます。盛り上がるのを嫌う国産の楽器は、板を厚くして、鳴らなくしている例が多いです。
しかし、固くて薄い板は、割れやすいです。割れたギターはいい音がするという人もいますが、根拠のない話しではないです。
板の硬さで厚みを決めるのに、板の曲げの力を測定する製作家もいます(万力で板を挟み、先に重りを乗せて、板の強さを見たりします)。
新しい楽器で厚い板を使ったものは、低音ばかり出て、高音が出ません。板を厚くして、いい音を出すのはむずかしいと思われます。あと、板を叩いて、響きが同じ板を組み合わせて使う製作家もいます。
投稿者:YE 投稿日時:2005/11/19 01:43 ---217.58.84
こんばんは。スレを立てた張本人です。
cremona2号氏:
>表面保護のニスごときで人間の耳で聞き取れるほどの変化が起こるとは思えません。
同感です。非常に薄いニスなのに、「音が…」と言われたので、正直驚いた次第です。ですから、その方の発言に今一歩信憑性が持てず、ここで伺った次第です。
猫丸氏:
>タップ音だけであれこれ言う職人は時々見かけますが、信頼の置けるキャリアーの職人さんはもっと根拠のある発言が多いように思います。
にも一脈通じるものがあると思います。
ところで、
Hiro氏:
>色々コメントされた方の意見は大体、「なんとなく感覚でわかる」といったものですよね。どこにその根拠があるのか?と聞かれると難しいと思います。
ですが、実は私も、「この楽器は板が厚い」「薄い」ということを感じることはありますが、ではその楽器の暑さが本当に判っているのかと言うと、測ったわけではないので判りません。「きっと厚いだろう」と思っているだけです。私の疑問を正確に言うと、「厚さがわかるといっている人は本当に判っているのか」ということです。感覚でもいいから、「厚い」と判断した時、本当に厚いのか?測ってみたのか?どうも不思議なんです。だから、クレーメル氏ご教授のミツトヨにはとても興味がありますね。
長いので二つに分けます。
投稿者:YE 投稿日時:2005/11/19 01:44 ---217.58.84
話し変わって、
ゆうな氏:
>それで実際に良くなったのであればそれで良いです
ギター弾き氏:
>板の厚さとかは、弾き手はあまり考えてなくていいと思います。音がよければいいのです。
ここでは、ギター弾き氏の「考えなくても良い板の厚さ」とは、「たとえ削られて薄くなったとしても」と解釈します。お二人のお考えは同じ方向性を向いているのでしょう。おっしゃる意図はよく理解できます。ただ、私には「音がよければよい」とは考えられません。やはり、楽器本来の価値を失うような処理は、たとえ音が良くなったとしてもすべきではないと考えます。「良い音」というのは十人十色です。ある人にとって良い音でも、他の人にとってはそうではないことはよくあるでしょう。「良い音」が絶対的基準でない以上、音を良くするために板を削る、ということは、Hiro氏やパスツール氏、ks氏のお書きになったように、削る職人の身勝手、とは考えられないでしょうか。いったん削ってしまうと、修理は出来ても元には戻りません。人は数十年しか生きませんが、ヴァイオリンは、特に良いヴァイオリンは数百年を生きます。それを考えると、取り返しのつかないことは、良心的な職人なら出来ないのではないでしょうか。
投稿者:CABIN 投稿日時:2005/11/19 03:28 ---.85.185
以下多少論点がずれることを先にお詫びしておきます。
現在生き残っているオールド名器は,そのほとんどが時代の要求に応じてモダン仕様に改造されているのではなかったでしょうか?
長く,後方に反ったネック,バスバー等,特にネックはヘッドを一旦切り離して再度取り付け直されています。このような改造にも相当の試行錯誤があったろうと思いますしそのなかで失われた名器も存在するのだろうなとは推察されます。
もちろんこれらの部品は交換可能なものとは思われますが,その時代が求める音にするべくオリジナルのネックを切り取ってしまったことなどは,ずいぶんな手の入れようだと思いませんか?
私も現存する名器の板を削る事に賛同しているわけではありませんが,過去には名器といえども職人によって改造されている事実があったのだと云えるかと思いますが....
結果オーライだったから許せるけど,今後は許さん..のように感じます。
投稿者:YE 投稿日時:2005/11/19 10:53 ---217.58.84
こんにちは。
CABIN氏:
>現在生き残っているオールド名器は,そのほとんどが時代の要求に応じてモダン仕様に改造されているのではなかったでしょうか?
お書きになっているように、それらは全て交換可能な部品であり、バスバー、駒、魂柱、指板は膠での固定、もしくは置いてあるだけで、必要であれば元の所謂「バロック仕様」に戻すことが出来ます。また、駒と指板は消耗品でもあります。ネックもブロックまたは釘で胴と固定してあるだけなので、取り外すことが出来ますし、消耗品の側面も持っているので、交換はやむをえないでしょう。スクロールを切り取るのは、「オリジナリティの尊重」「音には影響しない」という観点から、むしろ妥当な処置だと思われます。以上の観点から、表板・裏板とは同じに論じられず、むしろ古い楽器が長く使われる上で必要な措置ではないのでしょうか。
Q:Audinotについて
投稿者:マイカ 投稿日時:2005/11/16 18:28 ---108.35.210
こんにちは。
私の持っているバイオリンを譲りたいと思っている知人から
楽器の由来について聞かれました。
私はフランスの楽器だろうということくらいしかわからなかったので、もう少し詳しい由来等がわかったら教えていただけませんか?
ラベルには
N.Audinot
17.Boulevard Bonne-Nouvelle
Annee 1899 No.691
と書いてあります。
私の調べた範囲ではNestor Audinotのことではないか
と思うのですが、よろしくお願い致します。
投稿者:ヨシトフ 投稿日時:2005/11/17 12:48 ---2.90.106
viaductviolin
http://www.viaductviolins.com/English/Public/MakerSample.php
に下記の説明がありました。ご参考まで。
ネストル・オディノより少し若い製作者のものですが
私もフレンチ・モダンを愛用しています。
--
AUDINOT Nestor
Birth : 1842 in Mirecourt (Vosges)
Death : 1920 in Paris (Ile-de-France)
Biography :
Son and grand son of violin makers he learnt
his craft with his father Leopold AUDINOT in Mirecourt,
he is known to have worked with Laurent BOURLIER
as well before leaving to Paris.
Early in 1863 he started to Paris to work with
Sebastien VUILLAUME, Nephew of Jean Baptiste with
whom he worked until 1868. At that date he settled
his own workshop at n°17 Faubourg Saint Denis.
At the death of Sebastien VUILLAUME in 1875 he took over his workshop at 17, Boulevard Bonne Nouvelle. He married the same year.
Audinot gained his reputation in producing fine instruments after Stradivarius and Guarnerius pattern, coated with a typical and handsome orange-yellow varnish.
He retired in 1908, Eugene CORVISIER his collaborator succeeding him at the same place.
Q:楽器の値段を教えてください。
投稿者:HH 投稿日時:2005/11/15 01:23 ---46.211.149
現在使っている楽器の値段と歴史を知りたいので、教えてください。自分で調べてみたものの、殆ど情報が得られませんでした。
ラベルには下記のように記載されています。Emdliusのdがiなのか dなのか消えかかっていて分かりません。
Emdlius Piccioni de
Afclo Faciebat 1776
よろしくお願いします。
投稿者:ストラッド店員 投稿日時:2005/11/16 15:45 ---192.40.231
こんにちは、Emdlius Piccioni
調べてみましたが解りませんでした。申し訳ございません。
どなたか解る方いらっしゃいましたら情報よろしくお願いいたします。それでは!
Q:ニス補修
投稿者:ブルーチーズ 投稿日時:2005/11/15 22:39 ---109.80.175
こんばんは。ニス補修について教えて下さい。つい先ほどバイオリンの裏板にうっかり物を当ててしまい、裏板のへり(ふち)のニスがほんのちょっとだけ欠けてしまいました。ニスが欠けた(剥がれた)面積は1ミリ弱四方程度です。キズの深さは0.2〜0.3ミリ程度で、赤っぽい上塗りのニスだけが欠けた(剥げた)ように見えます。(木は傷んでないように見えます)バイオリンは3年前に買った手工の新作楽器です。
こういうニスのキズを補修してもらう場合、作業日数はどれくらいかかるものなのでしょうか?また補修費用はどれくらいかかりますでしょうか?
工房で現物を見せて相談すればすぐにわかることだと思いますが、一番近いバイオリン工房までバスと電車を乗り継いで3時間ぐらいかかるため、こちらの掲示板上で質問させていただいております。こういうキズをつけたのは初めてなので、動揺しております。お知恵を拝借できると幸いです。それではよろしくお願いします。
投稿者:セイジ 投稿日時:2005/11/15 23:32 ---151.3.240
使用にともないニスに小さな傷がつくのはありがちなので
慌てることではありません。補修費用は2〜3000円ぐらいです。
その場でニスを塗っておしまいの場合もありますし、
傷の程度によっては1週間ぐらい預ける場合もあるでしょう。
投稿者:ブルーチーズ 投稿日時:2005/11/16 12:22 ---109.81.166
セイジ様へ。お返事ありがとうございます。お蔭様で、一晩たったこともあり、少し冷静になってきました。幸いなことにキズはごく小さくて浅いので、その場で直ればいいな〜、と思ってますが、週末あたりに工房に行ってみようと思います。それでは。
Q:弓のサムグリップについて
投稿者:Ryo 投稿日時:2005/10/31 19:58 ---109.209.138
はじめまして こんばんは!
困った時よくこの掲示板を参考にさせて頂いてます♪
それで質問なのですが
私は学校の部活でヴァイオリンをやっています。
入部してしばらくは学校楽器を使っていたのですが
去年の12月の中旬に自分の楽器を買ってもらいました。
それでその時に楽器と一緒に購入した弓を
ずっと使ってきていたのですが
最近 木の六角形の部分が爪で磨り減って
角がまったく無くなってしまいました。
サムグリップも剥がれるというか
捲くれてしまった感じなんです。
なんだか最近そのせいか弓が持ちにくいんです・・・
友だちの弓はそんな風になってないし
ひょっとしたら 私の弓の持ち方が間違っているのかな
とも思いまして・・・
何かアドバイスいただければうれしいです
よろしくお願いします
投稿者:ぼこ 投稿日時:2005/11/01 12:34 ---189.149.245
Ryoさん
1年で、弓の木が削り減ってしまうのはショックですね。
弓の持ち方は、人によって多少は違いますので、一概に持ち方が間違っているとは思いませんが、まず左手だけでなく右手の親指の爪もこまめに切っていますか?親指の爪の右側の部分が弓に強くあたっているためにおきるのですが、そのくらい強く持っていても持ち方は間違えではないと思います。親指の指先の腹の部分で支える場合にはこのようなことにはならないと思いますが、親指の爪の右端と肉の部分のあたりを弓に当てている場合にはこのようなことが起こると思います。
それを予防する方法としては、この部分にゴムのチューブをはめるのですが、N響の根津さんのホームページのひとり言(2002年4月29日)に写真入でのっています。少し写真が小さくてみにくいですが。
http://www.nezu.ms/tubuyaki.02.04.html
ボールペンなどの指先のあたる部分のグリップをはずして(手ごろの太さのものを探して)使うこともできます。
弓のボックス部分を一度はずして、はめますが、少しきつめくらいの方がちょうどよいです。長さは1〜1.5cmくらいです。少しきつめの場合、はめるのが大変ですが。
木の部分に2〜3mmくらいでるくらいにするのですが、そうしないと弓の毛を緩めたときに、ゆるみません。
周りのお友達でやっている人もいるのではないでしょうか。聞いてみてください。
わりとやられている方も多いと思います。多いといっても10%もいないかもしれませんが、最近やりだして、少し弓が太めになるので、保持しやすくなりました。
投稿者:よりとも 投稿日時:2005/11/01 16:46 ---44.6.2
ゴムチューブは装着に手間がかかりますが、熱収縮チューブを使うと簡単に挿入できます。
本来の使用目的はアンプ等の配線をまとめるためのものです。
サイズも色々あり例えば直径12mm長さ1mで100円程度で、秋葉原の配線材料屋で簡単に買えます。色は黒色及び透明の2種。
長さを15〜20mmに切断し、弓の皮部分に挿入しアイロンの先で熱するとチューブが縮みピッタリと納まります。
ただチューブ自体の肉厚が薄いので親指の爪が当たる部分に穴があきやすいことが欠点です。
その時は穴部を回転させ、その上にもう一段チューブを被せて使っています。
投稿者:ろーたす 投稿日時:2005/11/04 23:34 ---4.187.178
はじめまして、こんばんはRyoさん。
文章を拝見しての印象なのですが、削れてしまう六角形の所というのはいわゆる右手の小指の当たるところが削れてしまうことなのでしょうか?
ぼこさんがおっしゃいますように右手の爪も短くするのを忘れないことは大切かと思います。
また、コレも印象なのですが弓を持つときに万力でしめる様にがっちりと弓を握っている印象を感じました。
これはあくまで私の意見ですが、弓をがっちり握ってしまうのはあまりよくないのかなぁと感じています。上手な友人の弓の持ち方を聞いてみる、よく観察してみる、巨匠の演奏姿をDVDで見てみるなどするといいのではないかなと思います。
弓の持ち方の変化によって腕の動きなどにある程度の変化もできると感じていますのでそこだけを取り上げて指摘するのは、まして文章だけで、難しく感じますが敢えてコメントさせていただきます。
特に弦の上にのせていないときなどの弓の感覚は万力で挟むような感覚で持つというよりは、親指のあたりを支点に人差し指と小指でバランスを取っている(テコの原理みたいな感じです)かなという感じで持っています。
あくまで私のなんとなくの感じですので本当はいけない持ち方なのかもしれませんので鵜呑みにはしないでくださいね。(私は上手なプレーヤーではありません)
ゴムチューブの話始めて知りました、勉強になりますね。よりともさん、ぼこさんありがとうございます。
投稿者:Ryo 投稿日時:2005/11/06 15:37 ---109.209.138
こんにちは 沢山の返信ありがとうございます!
返事が遅くなってご免なさい;
>ぼこさん
爪はこまめに切るようにしてます
はい 私は親指の爪の右端と指の境目を
弓に当てるように持っています
(そう持つように先輩に教わったので^^;)
ゴムのチューブの事は初めて知りました!
私の周りではその方法をしている人は残念ですが
いませんでした…
是非やってみたいと思います
アドバイスありがとうございます!
とうとう針金が出てきてしまったので
なんとかしないと…;;
>よりともさん
熱収縮チューブという便利なものもあるんですね!
秋葉原はちょっと遠いのですが
検討してみます ありがとうございます!
>ろーたすさん
角が丸くなるのは親指の所です
でも前に小指に力が入り過ぎていると指摘されたこともあるので
弓の持ち方、もっと研究してみますね!
ただ教えてくれる方によって随分と
弓の持ち方は違うようで
最初に弓の持ち方を教えてくれた先輩
(本当に上手な方です)は
小指を鍛える事に凄く重点を置く人で
よく小指で弓を押すようなトレーニングをさせられました
小指と親指だけでも弓を持てるように、と指導されました
でも 先日別のOBさんが私達の弓の持ち方を見て
小指に力が入り過ぎている、小指をそんなに力を入れるより
もっと人差し指と弓の接触する面を増やして
柔らかく持ったらどうかと
アドバイスして下さいました
結局自分が持ちやすい持ち方で持つのが
一番良いのでしょうけれど
人によって多様過ぎて困惑しているのが正直な所です(^^;)
長々と失礼しました
投稿者:のんちゃん 投稿日時:2005/11/13 20:44 ---7.133.64
よけいな力が入らなくなるとの事でしたので、本日文具店に行って鉛筆用のグリップゴムを買ってきました。
クツワのプニュグリップ(左手用)というグミのような感触のしかも左手用のものしかなかったので、安いからいいやと4個入り84円(消費税込み)を出して買ってきて弓につけてみました。この製品は正しく鉛筆が持てるように少しくぼんでいる部分がありその部分を親指が当たるあたりにして持ってみましたところ、なかなか快適でした。ゆびがすべらないので、指の力は今まで以上に必要がなくなり、弓に任せて弾く事が容易になりました。
おもしろいので、しばらく使ってみようと思います。
ただ、ケースによってはプロペラ型のゆみホルダーが窮屈になるかもしれません。私のは大丈夫でした。それから、透明なパステルカラーなので、ちょっと見た目が?と思うかもしれませんが、安いので試してみる価値はあるかもしれません。
とりあえず、ご報告まで。
Q:製作者について
投稿者:トトロ 投稿日時:2005/11/12 01:53 ---52.128.154
エンリコ・チェルティという製作者を知っておられる方いますでしょうか?
投稿者:かめ 投稿日時:2005/11/12 10:12 ---196.107.130
非常に有名な製作者なので、知っておられる方も大勢
いらっしゃると思いますが、その製作者の何をお知りに
なりたいのでしょうか?
投稿者:トトロ 投稿日時:2005/11/12 18:25 ---52.128.154
チェロを始めたばかりで無知なのですみません。
好きなバイオリニストのNAOTOさんがエンリコ・チェルティの楽器を使っていると聞いたので調べてみたくなったんです。
製作者の歴史などが分かる本とかでなにか推薦してもらえないですか?
投稿者:あや 投稿日時:2005/11/13 00:09 ---189.79.51
こんばんは。
私もNAOTOさん、大好きですよ。
エンリコ・チェルティ、かめさんもおっしゃる通り、とても有名な方です。
楽器に関してはバイオリンしか分かりませんが、結構なお値段がしたと思います。
まだ億にはいっていないと思います。
製作者の詳しい事がのっている本は分かりませんが、楽器店に行けば多少なりとも教えてくれると思います。
私も色々教えてもらいました。
投稿者:YE 投稿日時:2005/11/13 01:05 ---217.58.84
こんばんは。
Enrico Cerutiは、Giovanni Battista Cerutiの孫、Giuseppe Cerutiの息子です。G.B.Cerutiは、Lorenzo Storioniと共に、Cremonaの最後の巨匠と言われていますね。G.B.Cerutiほどとは言わないまでも、評価が高まっているメーカーの一人です。先日、ある楽器店で試奏させてもらったG.B.Cerutiの最高のものはG.Roccaと同じ評価で、3,500万円でした。G.Roccaと並べて弾きましたが、確かにG.Roccaよりよい音がしました。E.Cerutiだと、今では1,500万円はするのではないでしょうか。
投稿者:YE 投稿日時:2005/11/13 02:53 ---217.58.84
上記の価格はヴァイオリンの話、ということを書き忘れていました。チェロだともっと高くなるでしょう。
投稿者:トトロ 投稿日時:2005/11/13 20:03 ---52.128.154
あやさん、YEさん書込みありがとうございます。
偉大な製作者なんですね。もう少し自分で勉強してみます!
Q:はじめまして。
投稿者:Ottie 投稿日時:2005/11/12 17:57 ---150.133.196
大学のオケでチェロをやっているものです。現在私の所有しているチェロについてちょっと知りたいことがあって投稿します。
ラベルには、製作者「Santo Bottini」、工房「G.Grisales e E.Russ」、2000年製とあります。
この楽器を買った店主の方が以前、「Santo Bottiniという人は実在しない」みたいなことを言っていた覚えがあります。一体、どういう楽器なのでしょうか?
投稿者:ゆうな 投稿日時:2005/11/12 19:51 ---2.10.217
知っていますが、ちょっとお答えしづらいのでメールを頂ければ折り返しお伝えできます。
もちろん個人情報の問題などもございますので、どちらでも一向に構いません。
Q:松脂・・・
投稿者:as 投稿日時:2005/11/12 15:15 ---0.204.24
初めまして、ヴァイオリン初心者のasと申します。
このあいだヴァイオリンを買って、まだ弾いてないのですが・・・
セットの中に松脂が入っていたのですが何かオブラート?の様な物が掛かっていて上手く塗れません・・
どうしたらいいのか、教えてください!!
投稿者:杏 投稿日時:2005/11/12 18:40 ---147.49.117
ビニール系のもので包む松脂はみたことがないので、多分、一度溶けて、表面がすべすべになってるだけだと思います。
しっかりした楽器店で購入されたのなら、溶けてるみたいだ、と文句を言えば状態を見て、本当に溶けていれば交換してくれるし、そういう製品であるなら(最初っからすべすべのものもありますので)付け方を教えてくれると思います。
出掛けるのが面倒であれば、紙ヤスリでさっと撫でるか、カッターの刃で軽く削って傷つけてやるとそこから粉になります。松脂は布に付けると暖かくなると粘って、でもなかなか落ちなくて、始末が悪いので、新聞紙でも広げて粉を飛ばさないように。絨毯や毛糸物につけないよう、ご注意ください
Q:音大か留学か
投稿者:ぴぃ 投稿日時:2005/11/08 14:14 ---0.255.251
はじめまして。
こちらの掲示板にふさわしいかどうかわかりませんが、
とりあえずお聞きしてみようと思いました。
子供を音大に入れたいのですが、なにしろお金がかかります
よね。
日本の音大に入れるよりも、留学させたほうが金銭面では
親はラクでしょうか?(私費留学ですが)
漠然とした質問で申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿者:rio 投稿日時:2005/11/08 18:28 ---184.91.132
ぴぃさんこんにちわ
音大進学の目的、目標でもかなり変わると思います。
奨学生で授業料免除という場合やソリスト&プロオケで弾いて生計を立てるのが目標という例を除いて考えたいと思います。
(才能がある場合には、学費免除など費用がかからない場合が結構ありますので)
音大だったらなんでも良いというのであれば、物価の安い国の音大は、日本よりも安く済むと思います。弦楽器でアジア、極東、中東方面に留学している方も数人いると聞きます。
一般に、留学先としてイメージされることの多い、欧米の場合ならば、日本で自宅から通える音大に行く方が費用は安いと思います。
渡航にかかる費用、現地での生活費、授業料、授業以外のレッスン料です。
私は、実際には米国とフランスの例しか知りませんが、著名な先生であるほど、高額で、教えてもらい始めると、かなりの費用がかかると思います。
フランスの某先生は、日本の大学の先生の紹介で来た留学生や、著名なコンクールの入賞歴がある留学生には、廉価なレッスン料ですが、ノンキャリアだと、その能力を認められなければ高いレッスン料を請求していました。
才能・能力があれば安く、才能・能力が十分でなければそれを克服するためのレッスン料で費用がかかる。と言うのは、国に関係なく基本的には同じであると思います。
投稿者:ぴぃ 投稿日時:2005/11/09 01:20 ---0.255.251
rio様、どうもありがとうございます。
私自身は、日本の無名音大卒です。
子供は一人ですので、好きな道に進ませてあげたいと思っている
のですが、私の場合、大学に入る前も入った後も相当お金が
かかりました。
これが有名音大となれば、更にお金がかかることでしょう。
それで、海外の無名音大ならどうかと思いまして・・・。
日本の無名音大に行かせて職業に苦労するよりも、海外の無名
音大ならば教室を開く時に優位かななどど思ってしまいました。
やはり音楽をやらせるのには、お金は必要なんですね・・・。
投稿者:rio 投稿日時:2005/11/09 03:21 ---29.242.228
>やはり音楽をやらせるのには、お金は必要なんですね・・・。
少し残念です。「音大進学は、才能ではなくお金」とも取れてしまうので…
音楽教室開くときも、日本人ってブランドが好きですから、海外でも有名音大(音楽院)の方がウケはいいと思います。
音大=演奏技術
という図式を描く人が多いのですが
音大=音楽という学問の探究
という実体はないのでしょうか?
音楽好きが音大で音楽を学び、音楽史や音楽理論の研究員になるっていう道もすてきだと思うのですが…
投稿者:パピ丸 投稿日時:2005/11/10 14:41 ---15.198.130
ぴぃさん、こんにちは。
ご質問の内容から外れてしまうのですが、ワタシの音大進学観や、世相に
ついて一言言わせてください。
ご質問から察するに、お子さんは、一流音大をターゲットにできるほどの
技術をお持ちなんですね。でも、ソリストやプロオケに入る道ではなく、
音楽教室という方向なんですね?お子さんも音大に行くことに対して意欲的
ですか?でしたら、ワタシが口を挟む余地はありませんので、読み流して
下さい。
ワタシの友人は、数年前に国内で5指に入る音大をViで出ました。
ぴぃさん自身、音大卒ということで、ご存知の情報かもしれませんが・・・。
最近は、少子化とベビーブーム世代がたくさん先生になってしまったという
状況で、5指に入る音大卒でも一般企業に就職してしまうケースが
非常に多いそうです。フルートなどは、大人から始める人も多く、需要が
あるそうですが、ピアノ・ヴァイオリンでしたら、音大進学は、慎重に検討
なさった方がよいかもしれません。
音大を卒業しても、初めは楽器店の教室で先生をするケースが多いですが、
これもまた、ピンハネ率が高く、それまでの投資に見合う見返りを回収できるか
どうか分かりません。
また、こんなご時世ですから、生徒さんのマナーも悪く、ドタキャンや
なかなか月謝を払わないとか、気苦労も耐えないそうです。
そうした世相を考慮して、別の友人は、かなりヴァイオリンがうまかった
のですが、英文科へ進学しました。音大に進んだものの、一般企業に
入社する結果になるのであれば、賢明な判断だったかなと思います。
でも、一生仕事ができる技術を身につけるという点では、技術にならない
学部より、音大も考慮の余地があると思います。
ワタシも、音大を考えたことがありましたが、技術的に問題があったのは
さておき、音楽という学問に興味を感じなかったこと、演奏は好きでも
教師として教える職業は、あまり好きではなかったので、別の学部に
進学しました。
友人の話を聞いてると、苦労(練習や金銭的投資)の割りに、見返りの
少ない大変な業界なんだなぁとつくづく思いました。
投稿者:磯の珍味 投稿日時:2005/11/12 12:42 ---13.98.209
子供を音大に行かせたい、ということですが現実的に目指すレベルがどの程度かにもよると思います。このことではrioさんと同意見です。特に留学ということになるとかなり根性入ってないと厳しいと思います。(1年程度の短期留学は別でしょうが。)わたしの知人でアメリカの大学/大学院を出た人がいるのですが、最初の1年で英語があるレベルまで達しないと退学になるということで最初の1年間はすごく大変と言っておりました。(英語の授業と音楽のレッスンで)実際に知人の友人は1年経たず精神的にまいって帰国したということです。確かにレッスンを受ける際の言葉の問題は大きいですよね?(日本語ですらまともでないのに...)ちなみに知人が行っていた音大の学費は日本の音大よりかなり高かったような気がします。ただ、アメリカは奨学金制度が充実しているので自信がある方には良いのではないでしょうか?大学院レベルだとトレーニングオーケストラ(アメリカに2つあります)で仕事しながら勉強も可能のようです。ただアメリカならずとも世界的にクラシック音楽の市場が厳しい状態になっているのは間違いなく、その中で安定して収入を得るのは大変なことだと思います。「だれがクラシックをだめにしたか」(音楽之友社)という本がありますが、この本を読むと今のクラシック音楽市場の厳しさが良く分かると思います。今は日本も景気が良くなってますが景気が悪化したら音楽という趣味的要素が強い部分にしわ寄せが行くのは必然と思います。興味があれば一読をお勧めします。また、とある有名音大の教授だった人から聞いた話ですが、教える側として本当に実力があると思っているのは1学科上位5名程度で最初は定員が15名だったのですが、定員が30名に増えてもやっぱり実力あると教える側が認識しているのは上位5名だということを言われてました。厳しい世界ですね!

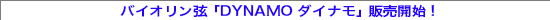
Q:ラベルの文字について教えてください。
投稿者:とも 投稿日時:2005/11/17 20:48 ---217.71.21
今使っているビオラのラベルに、印刷ではなく、手書きで、ラベルの隅の方に書きなぐり?のように書いてある文字が気になっているのですが、どういう意味かわかりません。
制作年、制作者等についての記述は別にあります。
クレモナの工房製なのでイタリア語?と思うのですが、該当する語がないらしく…
KOLLAGES''
あるいは、
ROLLAGES''
と読めます。ご存じの方がいらしたらお教えいただけませんでしょうか。
投稿者:ストラッド店員 投稿日時:2005/11/18 14:56 ---192.41.194
こんにちは、
KOLLAGES ROLLAGES 調べてみましたが解りませんでした。
申し訳ございません。
どなたか解る方いらっしゃいましたら情報よろしくお願いいたします。それでは!
投稿者:とも 投稿日時:2005/11/19 11:00 ---217.71.21
ストラッド店員さま、ありがとうございました。
ご挨拶おくれましたが、いつも楽しく拝見しておりました。
この謎の文字?については、調整に出すついでに購入店で聞いてみようと思います。
ありがとうございました。