弦楽器 Q&A
弦楽器に関するいろいろな疑問にお答えします。
2023年12月31日をもちまして、新規投稿・コメントの書き込みを終了させていただきました。
5203件のQ&Aがあります。
Q:エヴァ・ピラッツィのC線切れ
投稿者:チェロリスト 投稿日時:2005/10/31 00:23 ---179.26.108
いつも楽しく拝見しております。
私のチェロに4弦エヴァ・ピラッツィを張って半年ほどで
すが、先日倒れた魂柱の修理に出した際に、C線がおかしな
切れ方をしていたとのことで戻ってきました。
C線は全く使えなくなっていました。
何がおかしいかというと、芯は張力を維持しているのに
表面の巻きだけがフニャフニャになってしまったのです。
触ればまるで柔らかな皮のように、芯に沿って上へ下へ
と寄ってしまいます。
こんなことは、チェロ弦でよくあることなのでしょうか?
それとも、エヴァの特徴的な問題なのでしょうか?
もし後者ならば、大変高価なものでもありますし、似た
ような音色の別なものを試したいという気もあります。
ご存知の方がいらしたらぜひ教えてください。
投稿者:コメ 投稿日時:2005/11/01 00:19 ---14.148.101
エバは使っていませんが、何度か巻き線が死んだ事が有ります。大抵はボロ弦でしたが、新品を貼った瞬間になった事も有ります。他の弦でもなるので、エバ固有の問題ではないとおもわれますが。。
切れている起点が分かれば、原因も推察できるかと思います。
投稿者:チェロリスト 投稿日時:2005/11/01 23:09 ---179.26.108
コメ様
回答をいただきありがとうございました。
新品でもなることがあるのですか。
特に不良ということでもないとわかって安心しました。
またエヴァのC線を買おうかと思います。
しかしチェロ弦は高いので、こういうことがあると
〜タメ息が出ますね。
Q:バイオリンの接着について
投稿者:ベンソン 投稿日時:2005/10/30 09:51 ---110.60.48
家に以前からある、そこそこ年期の入ったバイオリンがあります。時間の経過からか、いつの間にか横板と裏板の間に隙間ができていました。部分的に膠を着け直そうかと思って、剥がしにかかったのですが、一向に剥がれません。もちろん力づくではなく暖めてふやかしながらです。そこでふと頭を過ぎったのは、接合が膠ではなく、化学接着剤なのではないかということです。そこで質問です。接着が膠なのか化学接着剤なのかを見極めるにはどうしたらいいのでしょうか。値段は不明です。使用されている板を見る限り虎目もはっきり出ていたりと、それほど悪い物とは思えません(思いこみかもしれませんが)。
投稿者:nodame 投稿日時:2005/10/31 11:51 ---205.169.122
ベンソン様
> 接着が膠なのか化学接着剤なのかを見極めるにはどうしたらいいのでしょうか?
膠は水分があると柔らかくなりますが、科学接着剤は水分では状態が変わりません。膠は単に暖めてもふやけません。水分がないと膠がふやける前にニスがふやける可能性があります。 したがって、パレットナイフのような物に水を付けて剥がれたろころに水を染み込ませて1〜2時間程放置した後に接着剤がべたついていれば膠と見てよいと思います。古い楽器だとテイッシュに水を染み込ませて接着部分に一晩乗せておかないとふやけないかもしれません。銘器の修理には一切水は使わないそうです。
現在の裏板の剥がれている部分が何センチ位かですがそれ以上剥がさずに今剥がれている部分に70度C〜80度Cで湯煎した膠液をパレットナイフのような薄いものに付けて塗りこみクランプで抑えれれば2〜3時間で付くと思いますが(応急修理)・・・・・大事な楽器であれば専門家に見てもらうべきだと思います。
投稿者:ベンソン 投稿日時:2005/10/31 18:16 ---110.61.129
nodame様、丁寧な回答を頂き、ありがとうございました。膠は時間が経過した方が接着が強くなるということでしょうか。正直なところ、逆かと思っていました。とても勉強になります。
投稿者:nodame 投稿日時:2005/10/31 20:12 ---205.169.122
ベンソン様
一概には言えません。湿気の多いところに置いておけば自然に水分が含まれて行き剥離の原因となります。保存状態の如何によると思います。ヴァイオリンの膠については美術出版社、新技法シリーズ『ヴァイオリンをつくる』ISBN4ー568ー32147−6の41〜42ページに大変詳しく記載されています。(ヴァイオリン作りを志すのでなければ読む必要は有りません。)
Q:
投稿者:奈津子 投稿日時:2005/10/24 14:44 ---186.156.55
こんにちは、また教えて頂きたいのですが。。。。
今、こちらの過去ログを見ていましたら、偶然フレンチバイオリンの事について書かれてある項目を見つけました。
そこには「JTL」というメーカーについて書かれていたのですが、それが有名なフランスの量産楽器店であると書いてあるの見てとてもショック受けました。
実は、私の楽器も「JTL]と書いてあるのです。
楽器を買うときは確か手工芸品と説明を受けたように記憶しているのですが。。。(確かではありません)
価格もそこそこでした。
そこで、どなたか私の楽器のついてお判りになる方教えて下さい。
楽器のラベルには
LE PETIT FILS DE
GERONIMO GRANDINI
PARIS JTL
と書かれています。ラベルの隣にはバイオリンと竪琴?の絵が描いてあるシールのような物あります。
宜しくお願い致します。
投稿者:rio 投稿日時:2005/10/24 17:31 ---148.53.97
(今自宅ではないので、確認はできませんが、記憶の範疇で)
バイオリンと弓の製作者辞典には
Grandini という製作者について記載しており
実在した人のようです。
(お父さんと息子の二人)
JTLの工房で製作していました。
JTLは量産楽器で有名なメーカーには間違いありませんし
そのJTLのブランドの一つがGrandiniです。
Grandiniが注力して作った楽器もあれば
JTLで、Grandini ブランドとして
他の製作者と一緒に、手作りには間違いないが
他の製作者との分業で作ったものもあるようです
私も偶然、持っている弓の1本に、Grandiniスタンプの弓があります。
英国の権威ある鑑定士に見てもらったところ
L Morizot 作の Grandini スタンプ と鑑定されました。
鑑定士からは、JTLの比較的上級グレードブランドとして、
Grandiniがあると説明を受けましたので、
同じように考えれば、JTLの比較的上級ブランドの楽器と考えられるのではないでしょうか?
分業で作ったか。一人の製作者が作ったかは。見る人が見ればわかるそうです。気になるようでしたら購入したお店に相談してはいかがでしょうか?
投稿者:奈津子 投稿日時:2005/10/25 09:59 ---186.156.55
rio様
いろいろ教えて下さいましてありがとうございます。
rio様のお返事を読ませて頂く限りでは、少なくとも機械で削り出したような板で作られた量産バイオリンではないようなので安心いたしました。
もし、Grandiniさん自信が手がけた作品の場合はかなりのお値段になるのでしょうね?
私のバイオリンは経年80年位だそうですが、Grandiniさんが活躍されていた時代もやはりその位の時代だったのでしょうか?
別に、「本人製作」という事に拘っている訳ではございません。
今まではただ練習してきただけで(初心者ですが)、余りにもバイオリンの事を知らずにきましたが、最近、ちょっとだけバイオリンそのものについて興味が沸いてきましたので。。。。
投稿者:rio 投稿日時:2005/10/26 02:32 ---29.242.228
私のわかる範囲で
ラベルの表記は、息子さんの作った楽器のようです。本人は違う表記をしています。
製作者辞典には
お父さんは、1920年にJTLの工場で働くとあり、
製作の腕前も、用いた素材も1級品だそうで
いろいろなグレードの楽器があり、5〜17ポンド(1973年出版の本)の値段帯とのことです。
と表記されています
1920年と考えれば80年ですが
息子さん作のラベルのようですので
ラベルを信じれば、10〜20年若いかもしれませんね。
いろいろなグレードの楽器があるようで、値段も幅があるでしょう。
無責任発言をお許しいただけるならば
フランス1900年前後の製作者JBCMのコピーモデルを作ったJBCが35ポンドと記されていますので
今JBCの相場が60〜80万円ぐらいと考えれば
幅のあるGrandiniは10万〜40万円ぐらいが相場と見ることもできるかも知れません。
WEB検索するとe-bayで数万円だったり、楽器売ります買いますコーナーで3/4をUS$2,500で売りますとかありますので、だいたい近い線なのではないかと思います。
投稿者:奈津子 投稿日時:2005/10/27 12:18 ---186.156.55
rio様ありがとうございます
そうですか、息子さんが手掛けた作品だったのですね。
楽器としての価値はともあれ、ご本人の作品という事が何かとても嬉しいです。
私自信が製作をお願いし、
直接手渡しされた様な錯覚に陥ります。
もしかしたら、本物を持つ喜びというのはこんな所にあるのかも知れませんね?!
いろいろ教えて頂いてありがとうございました。
また宜しくお願い致します。
投稿者:rio 投稿日時:2005/10/28 10:40 ---148.53.97
JTLのGrandiniは、フランス製バイオリンの中で
日本では比較的なじみのない製作者だと思います。市場でもあまり人気のあるメーカーではありません。値段も人気がない分お手頃な値段が付いています。
JBCM(コリンメゾンと呼ばれている有名なフレンチ)は、メジャーなフランス製楽器として人気を博したため、私の知る限りでは、贋物も横行してます。贋作はニーズがあるからこそ生まれますが、Grandiniは著名なさっかではあるものの贋作のニーズがある製作家ではないと思いますので、ラベル標記が正しければ、99%本人の手の入った本物だと思います。(実物をみていないので、多少無責任なコメントですが…)
量産品といっても。1900年台前半は、NCマシンなどなく、人の手ははいっています。またJTLと言う工房は有名な工房であり、腕の立つ職人さんがたくさんいたと思います。また、Grandiniは製作者辞典に載るぐらい著名な製作者です。
ぜひ仲良く弾いてやってあげてほしいと思います。
機会があれば、行きつけの楽器屋さんで、黒い表紙の「製作者辞典」のGrandiniの部分をコピーさせてもらったらいかがですか?
きっと より一層 楽器に対する思いが深まると思いますよ
投稿者:奈津子 投稿日時:2005/10/31 15:14 ---186.156.55
rio様
お返事が遅れまして申し訳ございませんでした
rio様のお話、私のような初心者にもとても判りやすく勉強になりました。
『楽器としての価値は兎も角』だなんておこがましい書き方をしてしまいましたが真意は決してそのようなものではありません。
むしろ、製作者社辞典に載る程の著名な方の作品を弾けることが出来るなんて震えてしまいそうです。
私には十二分過ぎるくらいの楽器だと思います。
これからはGrandiniバイオリンの良さを引出せる様一生懸命練習したいと思います。
ありがとうございました
Q:ケースについた汚れ
投稿者:coco 投稿日時:2005/10/28 11:22 ---22.69.86
いつも掲示板を拝見しながら、勉強させていただいています。今回はバイオリンケースについた汚れについて、質問させて下さい。
最近、バイオリンのボディの下側(エンドピン側)が触る部分のケースが黄色く汚れているのを見つけました。バイオリン自体は1921年製ですが、まだニスがはがれることがあるのでしょうか?それともケースが悪いのでしょうか?ちなみにGEWA社のStratoひょうたん型を使用しています。夏は冷房をつけた部屋に
置いていたので、暑さや太陽の光に当ったせいとは考えられないのですが・・・。ケース内の気密の問題でしょうか?ケースは昨年11月に買いました。
どなたかご教示をお願いします。
投稿者:ろーたす 投稿日時:2005/10/28 19:11 ---4.187.178
こんにちは、cocoさん。
アゴアテやエンドピンに柘植(ボックスウッド)製をお使いではありませんか?そして、変色しているところはそれらのパーツの当たるところではありませんか?(柘植は本来もっと白いもので、パーツとして使う時に私たちの知っているあの茶色に染めるらしいです。)
上記のような状況であれば、柘植の色がケースの布に移ったのではないかとおもい、私は特に問題ないのではないかなと判断してしまいます。
楽器に気をかける心がすばらしいと思います、見習いたいものです。
投稿者:つばさ 投稿日時:2005/10/28 20:17 ---190.175.193
こんばんは!cocoさん
ボクも同じGEWA社のヴァイオリンケースを使っています。
(角型ですが。。)
変色しているのは、アゴ当ての止め金の当たってる
あたりではありませんか?(違っていたらすみません)
ボクのケースの場合、アゴ当ての金具の部分にあたる
ケースの所が黄色く変色しています。
アゴ当ての金具のメッキも変色している感じですが、
原因はよくわかりません。
ヴァイオリン自身が当たってる個所には変色は
無いんですが。。。
多分同様の現象が発生してる方がいらっしゃるのでは?
と思います。。
投稿者:COCO 投稿日時:2005/10/30 16:51 ---22.68.209
ろーたすさん、つばささん、ご回答ありがとうございます!お2人の話を拝読しながら、お思いあたるふしが・・・。
実は今年6月にあごあてをローズウッドから柘植に変えたんです。ケースにはあごあての部分だけではなく、かなり広範囲に色がついていますが、楽器が揺れるからなのかもしれませんね。
それにしても色落ちするとは・・・。パーツがあまりいいものではないのでしょうか?みなさんのケースもそんな汚れがついているのでしょうか?驚きでした。
Q:バイオリンの製作者・ルーツ
投稿者:さあや 投稿日時:2005/10/28 22:16 ---7.152.127
コンラッド様、こんにちは。大学生のさあやと申します。
ご丁寧なQ&Aに心惹かれ、私もぜひお聞きしたいことがあり、
書き込ませていただきました。
約6年ほど前に小遣いをためて、
予算90万円でバイオリンを購入しましたが、
その楽器のルーツがわからないので
ぜひ教えていただきたいと思いました。
ラベルには
Leicht Albert
Geigenmacher anno 19
とあります。
ラベルのスペースから、19の後には年代を書くためのようで、
かつ何か書かれているような感じもあるのですが、
今は薄くなって読める状態にはありません。
当時は高校生で、楽器にもそれほどこだわっていなかったため
先生に選んでもらったのですが、
その先生が先日亡くなったというお話を聞いてから、
先生に選んでいただいた楽器のことを知りたいと思ったのです。
わかるようでしたら、教えてください、
よろしくお願いいたします。
投稿者:さあや 投稿日時:2005/10/28 22:19 ---7.152.127
ストラッド様、ですね。
店名を間違えてしまうなんて本当に申し訳ありません。
最近洋書やらたくさん読んでいて混乱していました。
本当にすみませんでした。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/10/29 17:35 ---6.34.162
ちょっと調べて見ましたが、それらしいヴァイオリン製作者の名前は楽器製作者事典には見つかりませんでした。
ヤロベックの事典で、1892年に生まれHohendorf(Brambachの近く)で1922に工房をおこした弓の製作者、にその名前があったくらいです。
Leichtが名字でAlbertが名前ですので、弓への刻印はAlbert Leichtとなっています。Leichtは親兄弟でヴァイオリン・弓を製作していた一族です。
Hohendorfはどこにあるかは知りませんが、言葉の響きと、ラベルの言語(多分ドイツ語)からして、ドイツではないでしょうか。
ラベルは直訳すると、
Leicht Albert
ヴァイオリンメーカー 19**製作
なぜ、名前と名字を一般的でない順番で書いたのかは不明です。
Webの検索エンジンでもひっかかりませんので、あとは購入した楽器店に聞くことをおすすめします。
Q:チェロピッコロを作るには?
投稿者:かわせみ 投稿日時:2005/10/26 11:01 ---71.62.137
いつもお世話様です。
チェロピッコロという楽器が昔あったそうですが、どこにも売っていません。製作していただくことはできるのでしょうが、私の腕ではどこまで弾けるかわからないので、既存の楽器でシュミレートできないものかと質問をしてみました。
ボディの大きさは65センチくらいだったようですので、ヨーロッパ1/2サイズの分数チェロにGDaeという弦を張れば、いちおうそれらしくなるのでしょうか?
某所で1/2を弾いてみましたが、あまりグレードの良い楽器ではなかったためか、ちょっとなさけない音でした。
バロックボウを持っていますので、ガットかナイロンを使うと多少似てくるのでしょうか。ただそもそもチェロのE弦というのはあるのでしょうか?あと、ピンは抜くとして、かなリ小さいのでふくらはぎで支えると弓先が足に当たります(^^;
ロングのピンを作ったほうが良いのかも。
この楽器をお持ちの方がありましたら仕様を教えていただけますか?
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/10/26 21:43 ---6.34.96
チェロではありませんが、先日ブランデンブルグ協奏曲1番のヴァイオリンピッコロのパートを弾きました。ヴァイオリンピッコロは、3度調弦が高くなっています(A線はCに調弦する)ので、そのパートに対し普通のヴァイオリンを使うとソロの重音が超絶技巧になってしまうため、最終的にはサイズがほぼ一致する1/4のヴァイオリンを使いオリジナル調弦で演奏しました。手を加えたのは、上ナットと駒の溝を若干広げたぐらいです。
3/4のヴァイオリンで3度上げれないかもチャレンジしましたが、見事にE線が切れました。一方1/4の場合、もともとテンションが弱いため。4/4サイズ用の弦を張り3度高い調弦をすると、切れる事もなく逆に張力がよい方向に働き張りのある強い音がでました。
私は知らないのですが、チェロピッコロの調弦は、普通のチェロより5度あがっているのですか? またボディーサイズは65センチだったのでしょうか?
昔の方が弦はずっと切れやすかったことを考えると、特殊な弦を使うことなく、大きさと張力がマッチする調弦にて使っていたように思うのですが...
もし、高い音が必要なら、サイズを考えるとヴィオラ・ダ・ガンバの弦などを使うのがよいかもしれません。
これも専門ではありませんが、ヴィオラ・ダ・ガンバは、チェロのような大きさだけではなく、テナー、アルトなどと呼ばれる小型のものがあり、それも顎に挟むのではなく大型のものと同じような構え方で弾きますので、そのあたりの構え方を参考にされてはいかがですか。(Webで検索すれば、ガンバのアンサンブルなどで弾いてる姿は見つかると思います。)
投稿者:CABIN 投稿日時:2005/10/27 00:35 ---135.201.120
Elizabeth CowlingのThe Celloという本にチェロピッコロの解説がありましたので,引用致しますと
ヴィオロン・チェロピッコロは4弦または5弦の小型のチェロで,普通G d a eまたはC G d a eと調弦される。
ヤコブ・シュタイナーの作ったヴィオロン・チェロピッコロは,胴長が59cmである。(写真も載ってました)
バッハの無伴奏チェロ組曲・第6番はヴィオロン・チェロピッコロのために書かれたと考えられている。
(ヴィオラ・ポンポーザ説もあるが,ヴィオラ・ポンポーザはヴィオロン・チェロピッコロより1オクターブ高く調弦されるので音域的に違うだろうと)‥以上抜粋
第6番を弾く場合には4弦ではなく5弦(C線があるもの)が必要ですね。
さて,チェリストの鈴木秀美氏は5弦のチェロピッコロをお持ちで,バッハの無伴奏チェロ組曲・第6番もチェロピッコロで演奏されております。 また,ガット・カフェ・スペシャルというレクチャー&コンサートを行われています。東京近郊にお住まいであればそこに出かけてお尋ねすることもできないことはないでしょうし(但し,毎回チェロピッコロで演奏されているわけではないので),Webサイトもありますのでお問い合わせされてみてはいかがでしょう。
投稿者:かわせみ 投稿日時:2005/10/27 09:10 ---71.62.137
みなさん、いろいろ、有益な情報をありがとうございます。
「チェロを語る」(ウィリアム・プリース)のなかでノーナ・パイロンという人が17世紀のヴァイオリン属は低い音域から順にヴィオローネ・ヴィオロンチェロ・テノールとあって、このテノールが胴長約65センチで、独奏用としては4弦のGdae、五弦のCGdaeとされた、と述べています。18世紀にはこのテノールは約70センチと大きくなるそうです。
ただこのテノールは現物が残ってないらしく、不明の点が多いので、ロウエル・クレイツという人がウィスコンシン大学でこのテノールの研究をしているそうです。
>ヤコブ・シュタイナーの作ったヴィオロン・チェロピッコロは,胴長が59cmである。
これはずいぶん小さいですね!ヨーロッパの1/4(鈴木サイズでは1/2)です。大きいヴィオラくらいかも。
ヨーロッパ人は体も大きいので、かなり持ちにくそうですね。
http://www.damianstrings.com/cello.htm#piccolocello
というガット弦をヨーロッパ1/2の楽器に張っておられる方をwebで発見しました。
何か教えていただけるかも(^^)
投稿者:ゆうこ 投稿日時:2005/10/28 08:56 ---233.197.226
ヴィーラント・クイケン氏がバッハのCDで弾いている中に、チェロピッコロを使ったのが収録されています。
楽器はご子息のフィリップ・クイケン氏の製作です。
埼玉県に工房を持ち、昨年に引き続き今年も弦楽器フェアに出展されるようなので、ご相談されてはいかがでしょう。
投稿者:かわせみ 投稿日時:2005/10/28 11:37 ---110.62.241
ありがとうございます。
弦楽器フェアは毎年顔を出しているので、今年はクイケンさんのブースに行ってみます(^^)
Q:Va弦の張替えについて
投稿者:枢 投稿日時:2005/10/21 20:17 ---151.111.222
こんにちは、お久しぶりです。
本番を一週間後に控えている学生アマオケ奏者です。
ここ何日かの猛練習で今まで保っていてくれた(つもりだった弦が)急にへたってしまいました。
張り替えたいのですが、本番一週間前に張り替えるというのはやはり危険でしょうか?
ちなみに弦は全てヘリコアで、今年の6月頭からかえていません。
演奏時間は平均で1日3時間前後、ここ数日は4〜5時間は弾いています(今後も本番まではそのくらい弾きます)。
また、早めに弦を安定させられる方法などご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。
よろしくお願いします。
投稿者:いし 投稿日時:2005/10/21 20:51 ---159.29.241
ヘリコアなら1週間前でもまず大丈夫でしょう。
本番前にそれだけ弾くのであれば、安定するかどうかも心配することはないと思います。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/10/21 23:26 ---6.35.232
ヘリコアであれば3日あれば充分安定すると思います。
それだけ弾くのであれば、ドミナントでも大丈夫でしょう。
また、上ナットの溝、駒の溝に濃い鉛筆や乾いた石けんを塗る事で、張力が均等になり、安定が加速します。(何を塗ればよいかについては、過去ログに関連のQ&Aがいくつもありますので、適当にキーワードを入れて検索してみてください。)
投稿者:もーりん♂ 投稿日時:2005/10/22 18:29 ---5.113.82
私はヴィオラには以前はスピロコアを使っていましたが、本番直前にすべてヘリコアに替えて軽くチューニングを済ませてそのまま舞台の袖で待機、そして本番、なんてこともありましたが、別に問題はありませんでした。が、あまりにも直前に替えるのはやはり危険ですね。弦喜さんのおっしゃるとおり、本番の3日前ぐらいが安全でしょう。
ちなみに、なぜ私が本番直前に弦を替えるという危険(?)なことをしたかといいますと、私のヴィオラはサイズが43センチと大きいためか弦が切れやすかったからです。スピロコアは定演の2日前に替えたのに、定演のわずか2日後にD線が切れてしまいました。それを教訓にして本番直前にヘリコアに替えたのですが、いくらなんでも直前過ぎましたね(笑)。
投稿者:トゥルバン 投稿日時:2005/10/23 02:01 ---109.80.40
弦喜さんが書かれているとおり、弦の滑りを良くすると、弦の伸びが収まるまでの時間(ブレーク・イン・タイム)を短縮できます。伝統的な方法としては、弦のとおるミゾに、4B程度の濃い鉛筆やロウを塗る方法があります。最近使われるようになった方法としては、油性の銀の色鉛筆や、ライト・ナットソース(半固体の超潤滑剤)があります。特にライト・ナットソースの効果はダントツで、通常は安定するまでに(たくさん練習しても)3〜4日かかるドミナントを2日で完全に安定させてしまいます。もちろん前提としては、弦のとおるミゾが適正に整備・調整されていることです。あと、糸巻きの調子の良し悪しも弦の伸びの安定化に多少影響します。あと、ライト・ナットソースをミゾに塗ると、調弦の安定度が高まって演奏中に調弦する回数が激減するほか、駒が指板側に傾いてくる現象を防止できるなど、多大なメリットがあります。ではでは。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/10/23 10:13 ---6.34.228
>>枢さん
トゥルバンさんの書き込まれた情報で、
「伝統的な方法としては、弦のとおるミゾに、4B程度の濃い鉛筆やロウを塗る方法があります。」は、多くの工房においても知られ行われていることであり一般論です。
一方、「最近使われるようになった方法としては、」以降は、一般論ではなく、このようなネットで誰かが書き込みを始めその書き込みを見て始めた人、およびトゥルバンさんの周辺の賛同者において、ローカルに行われている方法であり、まずはトゥルバンさんの私見であるとご認識ください。
>>トゥルバンさん
この掲示板は、まだ楽器をはじめたばかりの方や楽器に対する知識をお持ちで無い方も多く見られていますので、一般論と、私見あるいはローカルな話とは、明確にわかるように切り分けて記載すべきだと、私は思います。
またその内容については、以前のQ&Aでさんざん議論され、この会議室においては書き込みをやめましょうというのが、大勢の意見&結論であったと認識しています。(故に、私は先の書き込みで、過去ログ検索をおすすめしました。)
投稿者:トゥルバン 投稿日時:2005/10/23 16:40 ---109.80.46
弦喜さんが書かれているとおり、銀の色鉛筆とライト・ナットソースについては、まだ一般論としては定着していません。しかしながら、その効果は絶大でメリットが大きく、一方で、その害については悪い噂を聞かないので、今後徐々に一般化していくものと思われます。
あと、弦の伸びを早く収めたい(弦を早く安定させたい)場合には、次のようにするといいですよ。自分はヴァイオリン弾きなので、ヴァイオリン曲を例に出しますが、G線だけで弾くG線上のアリアを、G線→D線→A線→E線という具合にそれぞれの弦上で弾きます。このとき、なるべく大きな音で(=最初から最後までフォルテッシモで)おおげさなぐらいヴィブラートをたっぷりとかけて弾きます。音がつぶれるかつぶれないかギリギリまで追い込むようにして、弓は駒寄りをできるかぎり強く弾きます。
G線→D線→A線→E線のそれぞれの弦上で弾き終わったら、正確に調弦して、また、G線→D線→A線→E線のそれぞれの弦上で弾きなおします。2セットもやれば、弦が十分に伸びて、音程が安定するはずです。足りなければもう1セットやると良いでしょう。1弦上での2オクターヴの音階なども効果的ですが、G線上のアリアのような美しい曲で弦を伸ばしてやった(ストレッチしてやった)方が楽しくできていいですよ。ではでは。
投稿者:枢 投稿日時:2005/10/23 19:42 ---151.111.222
たくさんのアドバイス、本当にありがとうございました。
参考にさせていただき、昨日すべて新品に張り替えました。
やっぱり新しい弦はいいですね…!
>いし様
そうなんですね。おかげさまで安心して張替えることができました。
>弦喜様
弦が切れにくくなる、という話はきいたことがあったのですが、そんなメリットもあるとは…!
次はナイロン弦を張る予定でしたので、4Bの鉛筆で早速実践させていただきました。
>もーりん♂様
スチールでも大きい楽器だと切れやすいのですね。
もーりん♂様のお話で安定性がわかりました。今後はもう少しあせらずにかえられそうです。
>トゥルバン様
やはりしっかりと弾きこんでおいたほうが安定するのですね。
これからやってみようと思います。
投稿者:のんちゃん 投稿日時:2005/10/24 08:23 ---223.144.130
トゥルバンさん
1.大きな音で
2.大げさなくらいビブラートをかけて
弦をストレッチするのですね。
大きな音やビブラートはそんなにストレッチ効果があるのでしょうか。あまり実感がないのですが教えてください。特にビブラートはあまり関係ないようにも思いますが。
普通に4弦均等に弾く曲やスケールなど普段の練習のままでも変わりないような気がしますが。
また、G線上のアリアはあまり大きな音でひくのは美しくない気がして、せっかくなら一番音楽性の高い弾き方が気分も良いように思うのですが。すみません。なんか、ちょっと抵抗がありまして、質問させてください。
投稿者:トゥルバン 投稿日時:2005/10/26 00:06 ---109.81.92
たくさんヴィブラートをかけて弦の伸びを早く安定させる方法は、最高級ガット弦「オリーヴ」を愛用する先生から教えてもらいました。弦をちょっと強めに押さえて、かなり振幅の大きい(幅の広い)ヴィブラートをかけて弾くと、弦が安定するのが早まるように思います。弦を早く伸ばすのに、音階でもG線上のアリアでも曲は何でも良いのですが、強い圧をかけて大きな音で弾くとより効果的なのは間違いないです。ではでは。
投稿者:セロ轢きのGosh 投稿日時:2005/10/26 12:25 ---83.39.162
トゥルバンさんの話は面白いですけど、とりあえずは、「まぁ、そうやっている人もいる」くらいに受け止めておくのが無難でしょうね。 オリーブ(ガット弦)しか使わない人の習慣・感覚論をなんの検証もせずにスチール弦まで敷衍するのは如何なものかと思います。 実害が無い、という点も、「たまたま彼の知る範囲では」という条件がつきますし、その「知る範囲」がどの程度の広がりを持っているかも全く分かりません。
弦を張り替えて直ぐに弾きこみを始めたら、弾いてるうちに音程はドンドン狂いますね。 そうすると、こまめに調弦し直すことになるでしょう。 一方、弾きこみをしなければ、調弦の頻度も低い訳ですね。 「弾きこむと早く安定する」のメカニズムは案外この辺にもあるのかも知れません。 そうだとすると、弾き方はあまり関係ないかも。 この辺を検証した上で「間違いありません」と言っているのでしょうか?
あと、「弦の安定」というときに、実は楽器・弦の物理的な状態変化もさることながら、弾き手が新しい弦に慣れる、という要素も大きいのではないか、と思います。 そういう意味でも、「弾きこみが重要」という結論には賛成です。
だた、「圧力かけて」というのは誤解を招きそうな表現ですね。 一般には、「必要以上に圧力をかけてゴリゴリ弾くのは、典型的な悪い弾き方の一つ」とさているのではないでしょうか? 大きなビブラート(程度問題ですが)も含めて、わざわざ変な弾き方の練習をする必要は無いように思えます。
「実は私もそうしてます」という方が他にもいれば御意見伺いたいものですが。
投稿者:のんちゃん 投稿日時:2005/10/26 13:26 ---104.43.40
セロ轢きのGosh様
私の便乗質問に答えていただきありがとうございます。
私も同様に感じております。やはり、弦の伸びを修正する回数が重要な気がします。
ただ、物理現象として納得できない事も、実際にやってみると違うものなのかなと思って質問いたしました。違ったご意見の方はいらっしゃいますでしょうか。
投稿者:のんちゃん 投稿日時:2005/10/26 13:35 ---104.43.40
すみません。メールが途中で終わってしまいました。
トゥルバン様
そうですか。揚げ足を取るようで申し訳ないのですが、やはり『気がする』程度の事なのですね。私自身、比較してみた事がないので何も意見は言えないのですが、私などは弦を引っ張ってのばしながら安定させているので、そのような性急なやり方は弦をいためてしまうのでしょうか。引っ張ると言っても駒やナットのところに過度に力をかけすぎないようにはしています。
でも、やっぱり弦を張ったその日は安定するまで気持ち悪いので、練習時間を多めに取るようにしています。
投稿者:杏 投稿日時:2005/10/26 20:33 ---147.50.102
ガット弦なら、速く安定させるために思いっきりビブラートかけながら弾くのは常套手段ですよ。ハイポジションまで押さえ込む方が(弦高の都合で)よく伸びること、押さえつけている伸ばし方と振動させたときののび方が違うので、普通は大きくビブラートをかけながら6度重音で押さえ込んで10ポジションくらいまで弾いていきます。15分くらい弾けば、張り替え直後のヴィオラでもどうにか使えるくらいになるかな。翌日にはまた伸びてきますけど、、レッスン中に切っちゃったときなどは、便利な方法です。
しごいたり、引っ張ると巻き線が乱れてしまうので、あくまでも弾くのと同じ条件でやります(ピッチカートしながら弦をこまかくしごいて行く方法もありますけど、あまり力かけると弦が潰れる)ま、思いっきりそんなことしたら、潰れるだろう、と言われれば、そりゃ弦は痛みますが、弾いているときだって傷むもので、、
で、ヴィオラの話では、ドミナントでもC線だと同様に伸ばしてやる方が安定が速いです。トニカくらいだと差が判らない。クロムコアなんかは論外。でも、ヘリコアとかスピルコアのような金属ロープが芯になっている弦のC、G線では気持ち効果あり、です。でも、ヘリコアいしろスピルコアにしろ(あとザイエックスも速い!)、張って30分もすれば、アマオケで十分なくらいにはなっちゃいます。なので、本番中に切って替え弦を用意してなかった!!というときでもないと、使わない技ではあります(ヘリコア、曲間休憩中に張り替えてる強者もいますから、、)
ヴァイオリンは弦が細いので、もう少し鈍感だと思います。。
杏@Va
投稿者:セロ轢きのGosh 投稿日時:2005/10/26 21:21 ---83.39.162
のんちゃん様、
先のコメントは、内容の当否ではなく、混乱を招きそうな表現(論理展開)に対する批判のつもりです。 小生自身はガット弦など触ったこともないので中身について具体的に言える立場ではありません。 誤解を呼んでいたら申し訳ないです。(人の文章を批判している場合じゃないですね)
杏 様、
セカンド・オピニオンを、それも非常にすっきりした形でを出して頂きありがとうございました。
「大きなビブラート」の物理的な意味は素人の想像の範囲ではよく解りませんが、複数の方が実践しているということは、きっと経験的に何かあるのでしょうね。
投稿者:nodame 投稿日時:2005/10/26 22:47 ---205.169.122
もーりん♂ 様
43センチのヴィオラで弦が切れ易いのであれば、既に調整済みかとは思いますが、振動弦長を短くすれば良いと思いますが如何でしょうか?テエイルガットまたはスチールを伸ばして、弦の振動が楽器にマッチするようにすると良いと思います。切れるくらい弦を強く張るのがが一番マッチすると言うこともあるかもしれませんが・・・・
投稿者:もーりん♂ 投稿日時:2005/10/27 08:52 ---13.221.222
nodame様こんにちは。私のヴィオラの弦が切れやすいことについては、過去にこちらの掲示板で質問させて頂いたことがあります。「ヴィオラ 切れやすい」のキーワードで検索していただくとその当時の投稿がヒットします。私のヴィオラの弦の遍歴についてはこちらをご覧ください。
当時、弦が切れやすかったのは、楽器が大きいことに加えて駒のセッティングが高かったからかも知れません。その後、駒を弾きやすい高さに調整してもらい、弦をヘリコア(標準スケール)に変えて、1年半が経ちましたが未だに四弦とも切れておりません。音色も気に入っているのでしばらくはこれを使うことになりそうです。
投稿者:nodame 投稿日時:2005/10/27 11:02 ---205.169.122
もーりん♂様
お返事ありがとうございました。過去のログを見てからコメントしようと思いますと、恐らく見てるうちにその気がなくなるような気もします。 悪しからずご了承ください。駒のセッテイングで解決した事大変勉強になりました。ありがとうございました。
以上便乗コメントで失礼致しました。
投稿者:のんちゃん 投稿日時:2005/10/27 14:20 ---223.144.130
セロ轢きのGosh 様
ありがとうございます。私は誤解はしておりませんのでご安心ください。なんとなく、お考えには共感をおぼえます。
杏@Va
ありがとうございます。そうですか。私は弦をしごいたりはしないのですが、弦を持ち上げて均等にのばします。弾くのと同じ条件というのはなるほどと思います。でも逆に弾くのと同じ条件というのは、弦にとってみれば均等でない気もします。頻繁に重音、ビブラートが行われているというのは収穫でした。
ありがとうございました。
投稿者:のんちゃん 投稿日時:2005/10/27 18:38 ---223.144.130
杏@Va様
すみません。敬称を付け忘れてしまいました。訂正します。
私は理系なので何でもモデル化して単純に考えようとしてしまいます。でも、時には複雑に起っている出来事を複雑なものとしてとらえる事をしないと、真実を見逃してしまうのかもしれません。反省。
御意見いただいた皆さん。ありがとうございました。
Q:ROAZZI UMBERTO
投稿者:AKIRA 投稿日時:2005/10/25 12:09 ---44.34.45
上記ラベルのあるバイオリンを所有しています、ROMA1954の文字があります、此の楽器はモダンイタリアと考えて良いでしょうか、時価標準価格(楽器店、店頭価格}でいくらぐらいする物でしょうか、又此の作者の情報がありましたらお教え下さるようお願いします、尚ラベルの下部にVIA S,MAURA 69
の小さい文字がありますが何を意味しているでのしょうか、お教え下さるようお願いします。
投稿者:Vn. 投稿日時:2005/10/26 02:14 ---1.109.75
お尋ねのバイオリンと同様のものが、10日ほど前に某オークションに出品されており、そこに(正確な情報か否かは不明ですが)説明の記載があったので、参考になるか分かりませんがURLをお伝えします。
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n24457433
投稿者:rio 投稿日時:2005/10/26 11:20 ---148.53.97
アムステルダムにS. MAURA という港町があったと思います…
webサーチでクリーンヒットしない製作者名の場合、購入したお店で聞くのが一番てっとり早いと思います。
オークションではコンテンポラリーと書いてましたね。ならばそう理解しておくのが適当なのではないかと…
投稿者:AKIRA 投稿日時:2005/10/26 18:49 ---44.30.58
御解答有難うございます、さらにお尋ねしますが、ヴイオリンのモダン、コンテンボラリの区別は何で決めるのでしょうか、又オールドは通常100年以上経年の物といわれていますが、私は以前1,800年代製作のバイオリンを持つてましてオールドを自称していましたところ或る知人に、名器以外は古くてもオールドではないとアドバイスを受けたことがあります、その辺りの正確な見解がありましたらお教え下さい、宜しくお願いします。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/10/26 22:02 ---6.34.96
● 過去ログ検索にて
オールド モダン コンテンポラリー
の3つを同時にキーワードにして検索してみてください。
ヒットしたものを読めば、ある程度イメージはつかめると思います。
●現在イタリアの新作が名工の作品に限らず120万円は下らないということを考えると、イタリアの著名製作者による50年は経った状態のよい楽器は、それ以下になることはないでしょう。物には物の価値があり、法外に安いものは、まず疑ってかかるべきです。(ヴィトンのバックしかり、掛け軸しかり...)
また「個人名のラベルはまずは単なる飾りと見なすべし」。これはヴァイオリン選びの鉄則です。量産系のメーカーのラベルでさえ、偽ラベルが使われる事のあるご時世ですので... ですから、ラベルをもとに、この楽器はどのようなものですか、と質問されても、そのラベルに書かれた名前の人/メーカーはどのようなものか、しか答えられず、それはその楽器がどのような楽器かとは別次元の話となります。
Q:ヴィオラ製作者 Klaus Heffler について♪
投稿者:びよりすと 投稿日時:2005/10/25 21:59 ---251.81.23
わたしは今年4月から大学のオケでヴィオラをはじめた初心者です。そろそろ楽器を買おうと思って楽器を見にいったのですが、Klaus Hefflerという楽器がすごく響いて気に入りました。良かったらこの製作者について教えてください。おねがいします♪
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/10/25 23:49 ---6.34.123
インターネットの検索エンジン(Googleなど)で、Klaus Heffler をキーワードに検索すると、日本の楽器屋さんで扱っているところがいくつかあり、その中でどのような生い立ちのメーカーかの記載がありました。
弦楽器店のストラッドさんのページに、別の楽器店のURLを書くのもどうかと思いますので、ご自分で探してみてください。

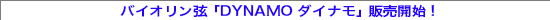
Q:楽譜について。
投稿者:tan 投稿日時:2005/11/01 11:38 ---52.128.154
チェロを弾いている26歳で始めたものですが、ピアノで出ている譜面(j-popなど)をチェロ用に作ってくれるお店ご存知あるかたいますか?
投稿者:CABIN 投稿日時:2005/11/01 16:04 ---114.112.42
「楽譜工房クレセント」のWebサイトをご覧になってください。
私もチェロアンサンブルの楽譜ではお世話になってます。
但し,著作権には注意しましょう。
投稿者:tan 投稿日時:2005/11/04 02:12 ---52.128.154
CABINさんへ
今までまさにこのようなことをやってくれるお店を探してきましたが、やっと出会えました。ありがとうございます!!