弦楽器 Q&A
弦楽器に関するいろいろな疑問にお答えします。
2023年12月31日をもちまして、新規投稿・コメントの書き込みを終了させていただきました。
5203件のQ&Aがあります。
Q:高価そうなフィッティング
投稿者:ゆきこ 投稿日時:2005/10/06 01:14 ---106.200.243
CrowsonやOtto Tempel、 Bogaro & Clementeなどの高級そうなフィッティングを、直に手にとって(できれば顎当ては実際に、その場でつけてみたいです)確認できるお店をご存知でしたら教えて頂けませんか?ストラッド様の掲示板で、このようなことを聞いて良いのかわかりませんでしたので、もし問題があるようでしたら、削除してください。
投稿者:rio 投稿日時:2005/10/06 20:39 ---188.30.21
なじみの楽器屋さんで断られたのでしょうか?
まず、直に手に取ることは、
ほとんどの楽器屋さんでできると思います
そのお店で買うことを前提に話しをすれば
たいていのお店で
その場でつけてもくれるでしょう
でも
ただ試すだけで、
実際は通販で安く買うための
試着だということが
お断りされるかもしれません
商品の試着は、
そのお店で買う検討行為だと
私は思います
投稿者:ゆきこ 投稿日時:2005/10/07 21:08 ---96.27.243
rioさま。御返事、ありがとうございます。
馴染みといえるほど楽器屋さんと付き合いがあるわけではないので、ネットのキーワード検索をしてみたのですが、Crowsonの通販が一件、ヒットしただけでした。それで、きっとOtto Tempel、 Bogaro & Clementeなどのフィッテングはどこの楽器屋さんでも在庫では置いていないのかと、思いまして・・。ついつい横着をして、こちらの掲示板で情報を頂けたらと思ってしまいました。
価格の見比べや試着だけの冷やかしをするつもりは、もともとありませんでした。試着をさせていただけるなら、その楽器店で購入するつもりです。
私の説明が足りなかったようです、すみませんでした。
投稿者:セイジ 投稿日時:2005/10/08 02:19 ---151.3.240
クローソンなどは品薄の上、高価なパーツですので、どこの楽器屋
さんにもあるとは限らないでしょう。東京なら銀座の大手楽器店に
クローソンが置いてあったと記憶してます。
その場で装着できるのは顎当てだけで、テールピースを付けた時の
音色の変化やぺグの操作感は、そういうものを装着済みの楽器を
試して想像するしかないでしょうね。
クローソンの顎当てには、ガルネリタイプのほかに
ルジェッリタイプのような相性が合うかどうか人によって
微妙な形状のものもあるので、実物を確認する必要はあります。
フィッテイングについては、この掲示板でも過去にいろいろと
言われていますので検索されてみたらいかがでしょう?
Q:
投稿者:優子 投稿日時:2005/09/26 13:45 ---14.185.109
こんにちは。いつも勉強させて頂いています。ヴァイオリンのE線で困った現象が出てきたので助けて下さい。
症状;E線を弾くとマイクのハウリングの様な雑音がする。
試行錯誤した結果、アジャスターでピッチを上げた時このような現象が起きるみたいです。駒から指板側とテール側の弦の張力が違うとハウリング音が出るような印象を持っていますが、こまめに張力が一定になるように弦を微調整しておけばいいのでしょうか?それとも、他に原因があるのでしょうか?ちなみに、駒のE線の部分には、紙か皮みたいなシールが貼ってあります。最近アジャスターを替えましたが、前のに戻しても変な音がします。(弦の新旧は両方試しましたが変わらなかったです)10月の中旬に遠方より、先生の所へ工房の方がフェアと称していらっしゃるので、その時に見て頂くつもりです。なので、工房の方に見て頂く際の留意点も教えて頂けたら幸いです。(先生もよく分からないみたいでした)
どなたかご教授ください。よろしくお願いします。
投稿者:ろーたす 投稿日時:2005/09/28 13:17 ---4.187.178
なんとも不思議なことがあるのですね、正直良くわかりませんが私の意見としてよろしかったら参考にしてください。本当の原因は職人さんがおしえてくれるとおもいますので。
E線だけが、楽器を弓で弾いた時に雑音が発生するのですよね?ということは、弓でE線を振動させたときに関わる部分のどこかが不具合を起こして音が発生しているのだと思います。
ひょっとするとなのですが…私の楽器は、A線にオブリガートを張るとナットの溝が弦の太さに対して大きすぎるために変な振動をしてしまうためか?ハウリングまではいきませんが、バリバリ?というような似た持続音系の雑音が発生します。それで思うのですが、Eの溝がスゴク大きいということはありませんか?
それでアジャスターを回しますと弦の位置が高くなるため、駒からテールピースまでの弦の角度が浅くなり症状が発生しているのではないでしょうか?
もしくは、もともとEの弦が裏返りやすい楽器で本当に裏返っているだけなのかもしれません。それでしたら裏返りにくい弦を張るといいと思います。
(先生が解らないというのでは裏返りではないと思いますので、この可能性はないのですが一応書かせてください)
工房の方に見ていただく留意点といいますのはよく分かりませんが掲示板でお書きになられたように、実際に起きている客観的な症状(どのような状況でどのようにすると雑音がするのかなどです)をしっかりと伝えることであると私は思います。
以上私の考察です、わかりにくい表現などが多々あるかと思いますが何かの参考にしていただければ幸甚の限りです。
投稿者:優子 投稿日時:2005/09/28 22:29 ---11.143.170
ろーたすさん、ご意見ありがとうございました。わかりにくい表現だなんて、とんでもないです。こちらこそわかりにくい質問をしてしまったにもかかわらず、ご親切に教えていただきありがとうございます。
ご指摘いただいたE線の溝ですが、スゴク大きいという事はないように感じています(普通がよくわからないもので、ごめんなさい)今日も試してみましたが、E線側の駒をハウリング音が出る時に押さえるとおさまります。あと、E線をアジャスターで調弦しなければハウリング音はしないようです。アジャスターを使わなければハウリング音がしないとわかったのは、調度駒の部分でE線が演奏中にパンと切れたので、なんとなくそうなのかな?と思ったのです。
今年の6月に初心者用のヴァイオリンから、中級者用に代えた(安物ですけど)ばかりなので、いくら安物でも私にとっては宝物ですので、少し焦ってしまいます。治ってほしいです。治るかな〜(;;)
先生は裏返りやすい云々とかも話してみえませんでしたので、音が裏返りにくいE線ってどのようなメーカーなのか支障がなければ、教えて頂きたいのですが…
投稿者:ろーたす 投稿日時:2005/09/28 23:45 ---4.187.178
音が裏返りにくいE線のことなのですが、簡単に言ってしまいますと巻き線がひっくり返りにくいと思います。
http://silver-tone.com/というサイトの日記帳というコーナーに“E線選び”というタイトルで非常に解りやすくまとめられているように私は思いますのでよろしければ参考にされると良いかと思います。(このようなサイトやBBSが開かれていることは非常にありがたいことだと思います)
バイオリンの先生が弦自体の話をしなかったのは、なりました音がひっくり返りの音でなく雑音であるからそのような話をしなかったのだと思います。
それとなのですが、e線の駒の溝が大きすぎるのというのは大体、弦が駒の中に完全に埋め込まれたような状態になってしまっている物かな?と私の中では思っています。
すごく楽器を大切にされているようで、お気持ちお察しいたします。海の中に沈んだバイオリンや畑の中から出てきたバイオリンを修理したら弾けるようになったというような驚くべき話をどこかで聞きしましたことがありますので、きっと職人さんが直してくれると思います、大丈夫だとおもいますよ!!
(楽器の不具合についてはスミマセンが解りません)
アジャスターなしで調弦というのもなかなか大変かとは思いますが、がんばって下さい。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/09/29 00:48 ---6.34.107
E線の交換は、いままでも何回もやられていて、今回アジャスターを交換して初めて、この現象が出るようになったのでしょうか?
E線がらみの雑音で一番多いのは、駒に食い込むのを防ぐための細いビニールパイプがはずされていない、あるいは固定されていない、ために振動で共振して雑音を発するものです。E線には必ず上記ビニールパイプがついており、特に駒のE線の部分に保護の皮紙がかぶせられているときは、そのパイプ不が要なためういた状態になることが多いです。一度ご確認ください。
もしそうでない場合、E線なら解放弦だけでなく、どの音を押さえてもその変な音は出るのでしょうか?
(ある周波数での共振かどうかの判断材料になります。)
投稿者:優子 投稿日時:2005/09/29 16:25 ---14.185.135
ろーたすさんの教えて頂いたHP拝見いたしました。とてもわかりやすく参考になりました。海や畑からのヴァイオリンの蘇生のお話を伺って、焦りも和らぎました。ありがとうございます。又弦喜さんには過去にもご助言を賜っています。今回もご意見を頂き嬉しく思います。ありがとうございます。
さて、お2人のご助言を熟読し、駒の部分を眺めた所、紙のようなものが貼ってある上にE線が食い込んでなくて乗っかっている感じでした。ビニールのパイプははずしてあります。(指板の上の方のナットと勘違いしていてのでそちらばかり気にしていました)E線の開放弦のミから始まってミとファ、その次のラとシだけが弾くと正規の音の影にプオ〜ンっといった感じのへんな音がするようです。(不思議な事にシャープ、フラットをつけるとそうなりません)雑音の音程はよくわかりません。
アジャスターはどんなタイプを使っても同じ現象がでます。弦は3回替えましたが、同じでした。ただ、始めは弦が古いからかな?と思って様子を見ていたのですが、古くても新しくても変な音がでます。
職人さんに伺うにしても、ある程度の原因がわかっていたほうが良いかと思い皆様にご質問させて頂いた次第です。(滅多に会える方ではないので、このチャンスを有効に使いたくて)
お2人にご意見を頂いて、大変参考になりましたし、どうやって職人さんに説明するべきか、考えもまとまってきました。ありがとうございました。
投稿者:ギター弾き 投稿日時:2005/09/30 00:52 ---150.132.229
こんにちは。
E線の駒の皮が張っている溝の1mmぐらい左にカッタで少しキズをつけて、そこにE線を乗せて鳴らしてみたらどうでしょうか。この皮の部分が怪しい感じがしますね。
また、駒そのものに固有の周波数特性があるようですから、駒そのものを変えてみるのも1つの方法かもしれません。もう一台バイオリンがあれば、その駒を付けてみるとか、、
あと、ナットのところの調整が悪いと、弦が溝に微妙に触れて、変な音がする場合があります。
それと、ハウリングを起こすポジションの指板が凹んでいないか、他に共鳴する物がないかとか、色々チェックしてみるといいかもしれませんね。
投稿者:優子 投稿日時:2005/09/30 07:31 ---14.185.94
おはようございます。ギター弾きさん。ご助言ありがとうございます。なるほど、駒があやしいですか。直らないかも〜っとパニックになっていたのですが、皆さんからご助言を頂いて、直る見込みが見えてきたのでうれしいです。私の力では、カッターで切り込みを入れるのも、駒を替えるのも無理ですが、職人さんがそのようにして直されるかもしれません。
指板の凹は物差しを当てて調べてみましたが凹んではいないようでした。いろいろチェックしてみますね。ありがとうございました。
投稿者:teku 投稿日時:2005/10/04 13:26 ---12.30.77
ひさひぶりですが、いつも楽しく読まさせて頂いております。
最初に質問のところで、マイクによるハウリングのような雑音とありますが、これは一般的には周波数の近い2つの音が出ているとき発生するのもですよね。
アジャスターは何型をお使いですか?ヒル型に交換したら発生しない場合もありますよ。逆にヒル型をお使いなら別の型にしたらどうでしょうか。もしくはテールガットの長さが不適切という場合もあると思いますが。
私の場合は、ハイポジションでうなりが少しでたことがあります。調整に出したらきれいに消えました。
的外れなら無視してください。
投稿者:nikotaro 投稿日時:2005/10/04 14:33 ---71.62.137
E線の駒とアジャスターの間の部分の線を触ると唸りが消えるならば、ウルフですね。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/10/04 19:49 ---6.35.149
複数の音程にて現象が発生しているので、ウルフの可能性は低いと思います。
>>優子さん
やはり書き込みだけでの説明では判断がつかないので、工房の人に実物を見て対処してもらってください。
また、原因については非常に興味がありますので、修理・調整後に、その原因と対応方法が何であったか、書き込んでいただければ助かります。
原因として、今までに述べられたもの以外で考えられそうなのは、
・テールガットの端がボディに触れている
・テールピースと顎当てが触れている
・パーフリングがどこか浮いている
・f字の細い部分にゴミがたまっている
・クラック(ヒビ)がありそこが共振する
いずれも普通は低音弦を弾いて発生することが多く、高音弦ではあまり起こらないのですが...
投稿者:優子 投稿日時:2005/10/05 15:11 ---14.182.69
こんにちは。ご意見を賜りました皆様、ありがとうございます。tekuさん、アジャスタは、代表的な2つのタイプを両方試していますが、変わり無かったです。テールガットは金具のようになっています。tekuさんの楽器は調整で直ったのですね!という事は私のも期待できるので、コメントを嬉しく拝見させて頂きました。nikotaroさん確かに駒からテール側の弦を触ると変な音はしません。ただ、1人では開放弦でしか試せないので今度レッスンのとき、先生に弦を押さえてもらうつもりです。弦喜さん、確かにこの件については、実物を見て頂かないとなんとも言いようがないですよね。にもかかわらず、あらゆる可能性をまとめていただいてありがとうございました。よ〜く頭に叩き込んで、職人さんに見て頂きます。10月の中旬に見て頂くので、皆様へのご恩返しのつもりで、原因と結果をご報告させてください。スレが大きくなってしまったので、新たに後日結論のみご報告させて頂きます。ご心配して頂いた皆様、大変ありがとうございました。
Q:モダンイタリアンの作者について
投稿者:岩田 レイ 投稿日時:2005/09/29 11:23 ---96.65.104
Luigi Varola の表記があるヴァイオリンですが、作者、またはメーカーについて何かわかる事があるでしょうか?ラベルの記載は「Luigi Varola faciebat Milano-Anno 1999」となっています。よろしく御願い申し上げます。
投稿者:ストラッド店員 投稿日時:2005/09/30 16:38 ---39.17.247
こんにちは、
Luigi Varola
イタリア語の資料に載っていました。
1923年生まれのイタリアの方のようです。ストラディヴァリウスモデル。G,Bモラッシーの文字があるので、お知り合いなのでしょうか?
ごめんなさい、何せイタリア語の為ほとんど訳せません。
どなたか情報お持ちの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。それでは!
投稿者:岩田 レイ 投稿日時:2005/10/05 13:01 ---96.65.104
さすがストラッド様!ありがとう御座います。まあ、ラベルなんて一片の紙切れですので、音さえ良くて気に入っていればいいのですが......。実在の製作者とわかっただけでも何か安心のような。
Q:暗譜について
投稿者:YAMA 投稿日時:2005/10/03 12:53 ---23.191.32
10歳から14歳ぐらいまで嫌々ながらバイオリンのレッスンを受け、その後はまったくバイオリンに触らず、40年後にあらためて一所懸命バイオリンを習っている者です。若いときからもっとやっておけばよかったという後悔ばかりです。
ところで、バイオリンでは暗譜で弾くこともありますが、皆さんはどのようにして暗譜されているのかをお聞きしたくて、投稿いたしました。長い曲になると、暗譜するのはこの歳ではやっぱり無理なのかなぁと思ってしまいそうです。
何回も何回も練習をしているうちに徐々に憶えていくというような方法でいいのか、あるいははじめからそのつもりでしっかりとがんばって憶えないといけないのか、そのあたりのことをお教え願います。プロの方はどうされているのでしょうね。
投稿者:いし 投稿日時:2005/10/03 22:35 ---159.3.214
私はアマオケのヴィオラ弾きです、とお断りした上で書きますと、
オーケストラでは当然、譜面を見ながら弾きます。ただし、時として指揮者やコンマスを見ながら弾く必要が出てくるので、その部分は暗譜する必要があります。
ですから、練習を重ねつつ「どの部分を暗譜すればいいか」と考えて、重要性の高い部分から少しずつ覚えていけば良いと思います。少なくともいきなり譜面を全て覚え込もうとするよりはるかに能率的です。
同じ曲の同パートでも、「どこから暗譜していくか」ということについて、メンバーで意見が分かれることがありますが、こういったことを積極的に意見交換していくと学ぶところが大きいです。
暗譜するために練習するのではなく、演奏をより良くするために暗譜するということは忘れないで下さい。
投稿者:元 投稿日時:2005/10/03 22:50 ---102.83.253
はじめまして。
何回も何回も練習をしているうちに徐々に憶えていくというような方法が一番自然なやりかただと思いますよ。
しかし例えばリサイタルなどソロの曲を暗譜で演奏する時などは、必要に迫られて暗譜するので徐々に頭にたたきこんでいたら間に合わないこともあります。
なぜ暗譜するのかというと楽譜を見ながら演奏するより暗譜して音楽に集中して、音の響きや弓の配分など気にしながら演奏した方が良い結果を得られるからです。
1.楽譜を見ながら演奏した物をテープ等に録音して何回も聴く。(他人の演奏したCD等では、解釈が物まねになってしまいます)
2.音楽の構成、例えばソナタ形式などを理解する。
3.和音の進行をおぼえる。
4.ひたすら繰り返し練習して身体に覚え込ませる。
5.楽譜の風景を画像のままおぼえる。(楽譜の書き込みやシミなども一緒に)
私の場合3〜5を一番使用している感じがします。
最初は慣れないかも知れませんが、短い曲などを鼻歌を歌っている気分で(これは実は大事。リラックスした脳の方が覚えが良いそうです)何曲か覚えられれば、次は大曲なんてのが良いんじゃないでしょうか?頑張ってくださいね。
投稿者:よが 投稿日時:2005/10/04 07:51 ---109.222.142
おはようございます.
私もアマチュアですが,ソルフェージュして音名歌詞付きにすると,
漫然と聞いたり弾いたりするよりは速く覚えられる気がします.
あとは,曲の構成を意識して,1回目はこうで2回目は調が属調に変わるとか,ここは第2主題を短調にしてトレモロだな,みたいなことを知っていると覚えやすいと思います.
Q:エレクトリック・バイオリンについて
投稿者:虹の彼方へ 投稿日時:2005/09/25 11:52 ---110.59.1
この度、ライブで電気楽器と一緒にバイオリンを演奏することになりました。いつも使っているアコースティックの愛用にピックアップを付けることには躊躇があって、エレクトリックのバイオリンを購入しようかと考えています。ヤマハのエレクトリック・バイオリンを試奏しましたが、ペグがギタータイプで何かしっくりいきませんでした。自分の予算内で購入可能な範囲にR&Bellのエレクトリックバイオリンがあると知り、サイトを見ると確かにいかにもエレクトリックという顔をしてて、中途半端さがない分、逆にいいかなと思いました。それほどこの楽器が流布してるとも思えないので、ご存知の方はあまりいないのではないかと察しますが、もしも何か善し悪しの情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お教えください。
投稿者:いし 投稿日時:2005/09/26 06:09 ---159.51.55
弦喜様へ
2系統の信号をミックスする場合、
マイク=より自然な音
ピエゾ=他の音が回り込まない、エコーなどが掛けやすい。
という特徴がありますから、会場や編成、曲によってブレンドの比率を変えていくことになります。
(マイクで拾った音は会場へ、ピエゾで拾った音は演奏者向けにモニターから出力、という使い方もあります。)
一般的にピエゾはマイクに比べてハウリングを起こしにくいので、大音量の中で弾く場合はどうしてもピエゾの音を多めにすることになります。それでもスピーカーから出た自身の音をピックアップが拾えばハウリングが生じます。
逆に言えば、スピーカーからの音が楽器に戻ってこなければハウリングは生じないのですが、そうすると演奏がやりにくくなります。
ハードロックバンドと一緒に演奏したとき、マイクだけで音を拾うことにしたのですが、マイクの角度調整を念入りに行い、かつモニターを使わなければハウリングは生じませんでした。ただし弾いている自分にもほとんど音が聞こえない状態なので演奏していると不安な気持ちになりました。このような状況では上記のように、ピエゾからの音をモニターのために最小限聴けるようにすると弾きやすくなるようです。
ただしマイクを使っても楽器本体に近づけすぎているため自然な響きになりません。やはりアンプの方で音色補正する必要があります。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/09/26 17:22 ---6.35.22
>>いしさんへ
情報ありがとうございます。詳しい説明いただきよくわかりました。
>マイクで拾った音は会場へ、ピエゾで拾った音は演奏者向けにモニターから出力
という使い方はまったく想定していなかったので、役に立ちました。
やはり返り(モニター)がないと弾きにくいと思いますので、そのような工夫が必要なのでしょうね。
質問の商品は、肩当て内で2つの信号をミキシングし、出力としては一系統にまとめることになると思いますので、そのような使い方はできませんが、単品同士を組み合わせれば確かに可能ですね。
>>虹の彼方へさんへ
どのような音を求めるかによって手段がかわってきますので、アコースティックの愛用楽器+肩当て集約型マイク&ピックアップという選択肢も、是非検討ください。
エレクトリックヴァイオリンの音は、隣の弦およびボディーの共鳴・共振による色づけ・倍音成分がありませんし、ハイエンドまで音は伸びていませんので、魅力ある音を得るために音色的に味付けするためには、イコライザと、リバーブ、コーラスなどの空間系のエフェクトは基本的には必須で、好みによりひずみ系などのエフェクトを使うことになると思います。
投稿者:いし 投稿日時:2005/09/27 22:00 ---159.63.143
お返事が遅れました。
弦喜 様
>質問の商品は、肩当て内で2つの信号をミキシングし、出力としては一系統にまとめることになると思いますので、そのような使い方はできませんが、
実は、御質問の商品はマイクとピエゾの信号を専用ステレオケーブルで分離して出力できます。2つの信号のブレンド比を決定するのは演奏者よりも、客席側のミキサーやエンジニアですから、このような仕様になっています。
虹の彼方へ 様
>アコスティックの駒にピックアップを付けて・・・何とも音にめりはりがないというか
後付けピエゾの場合、駒の隙間に挟み込んだり、両面テープで貼り付けたり、といったやり方が多いのですが、ピエゾは振動体にしっかりと固定しないと低域が拾いにくく、結果として音が痩せ細ってしまいます。ですから一番良く響く場所を見つけたら強力接着剤で完全に固定してしまうのが良いのですが、これは勇気がいるでしょうね。
自分で(魂柱や表板に悪影響を与えずに)駒を交換出来る人なら、(1)ピエゾを内蔵した駒を購入する、もしくは(2)駒を別に用意し、それにピックアップを貼り付けるなどして、必要に応じて駒を交換して使うのが一番でしょう。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/09/27 22:50 ---6.35.22
>>いしさん
>実は、御質問の商品はマイクとピエゾの信号を専用ステレオケーブルで分離して
>出力できます。2つの信号のブレンド比を決定するのは演奏者よりも、客席側の
>ミキサーやエンジニアですから、このような仕様になっています。
それはなかなか優れものですね。ためになりました。ありがとうございます。
投稿者:はふへ〜 投稿日時:2005/10/03 21:37 ---110.59.78
楽器について記載されているサイトを見つけました。 http://home.d07.itscom.net/kanamori/music/gears/gears.htm#violin
Q:バイオリンの残音
投稿者:aya 投稿日時:2005/10/01 09:13 ---14.109.17
こんにちは。いつも拝見している、バイオリンの初心者です。
バイオリンの残音について教えていただけませんか。
決して高くない2本のバイオリンですが。
一つめのバイオリンは、開放弦を弾くと、一つの波のようにさーっつと音が消えていきます。もう一つの方は残音が長く残って、耳を澄ますと、音が消えていくときに、ビブラートのような波を感じます。(私には心地よく感じますが、これがウルフですか?)どちらかのバイオリンがおかしいところがあるのでしょうか?
音を言葉で書くのは難しいのですが、よろしければご意見を聞かせてください。
投稿者:ろーたす 投稿日時:2005/10/03 07:03 ---4.187.178
残音の発生の仕方でビブラートのような感じは1つの弦だけで発生するのですか?それとも他の弦を使っても発生するのですか?もし他の弦でも発生するのでしたらウルフの可能性は低いように思います。
ちなみにウルフ音とは、私の理解ですが簡単に表現しますと、楽器本体の持つ音程が弦で弾いた音程と近いために楽器本体の音として発生してしまい、弾いている弦の音とブツカリ短2度の音程を酷くしたような状態になっている事であると思っています。(間違えておりましたらスミマセン)
それでウルフ音でないことを前提として考えますと、ウワンウワンなる原因になりうるのは弦の両端の溝(駒とナットです)がゆるくなっているために自由に動いてしまうからではないでしょうか?ビブラートのようになるということからは可能性として1番高い気がします。
(残響音の多い楽器ではイロイロな弦をお試しになられてはいませんか?そして今はとても細い弦を張っておられませんか?そうでないのでしたら多分私の溝調整説は違う気がします、変なことを聞いてスミマセン)
ところでなのですが、波のように音の消える楽器と残響の長い楽器では残響の長い楽器のほうが音が長く残るのですよね?それでayaさんがそちらのほうが好みならそれでいいのではないのかと思います。(あくまで素人意見ですのでよろしくおねがいします。)
ひょっとするとなのですが弦の両端が少しゆるいから音の残りが良いという可能性もあるかと思います。
以上が私個人の思いましたことです。
投稿者:QB 投稿日時:2005/10/03 12:48 ---9.46.177
異音でないならば、単純に残響が長い(つまり良い?)楽器であるというだけだと思います。
「ビブラートのような波」ですが、そのとき弦の振動の方向を見てください。
弓による強制振動が終わると(つまり弓を放すと)、弦はそのまま弓の動きと同じ方向に振動を持続し続けるわけでは有りません。
よーく見ると振幅が最大になる方向が変化していませんか?
駒から見て駒を横方向に振動させる(つまり弓の動く方向に振動している)場合と、駒の縦方向(つまり先ほどと直交する方向)とでは、同じ振幅であっても、音は違います。
このようにして振動の方向の変化が、音の変化を生み、それが「波」に聞こえるのではないでしょうか
投稿者:aya 投稿日時:2005/10/03 14:35 ---14.107.122
ろーたすさま、QBさま、分かりにくい説明文に対して、ご意見を頂きありがとうございました。
楽器は、残音が短くて、すーっと音が退いていく方で、ドミナントを張っています。楽器は、残音が長く、波のように感じる方で、いま、オイドクサを張っています。そんなに耳に自信がないのでよく分りませんが、違う音程の波でなく、強弱の波のような感じです。E線以外で感じます。ビブラートなんて書いてしまって、申し訳ありません。
楽器は駒にシールのようなものが張ってあり、溝がありません。楽器の方は駒の溝がふかく、E線はかなり深く入っています。 その反面ナットの溝は浅いです。
ナットの溝と駒の溝との関係もあるのかもしれませんね。
振動の方向はよく分りません。丸く見えます。
良く聞くウルフという単語。実際に聞いたことがない音なので、もしかしたらと不安を感じおうかがいしました。安心しました。ありがとうございます。
投稿者:QB 投稿日時:2005/10/03 17:13 ---9.46.177
一般的な話なので、出ないかもしれませんが、、、
G線の9〜11ポジションあたりを(つまり高いドの音の近辺を)少しずつ音程をズリ上げ(下げ)しながら弾いてみてください。
突然うなり声や悲鳴みたいな音に変わったら、「それ」です。
投稿者:aya 投稿日時:2005/10/03 19:00 ---14.107.122
QBさま、ありがとうございます。
私の耳では探せませんでした。まだ、ラまでしか弾いたことがありません。今度から気をつけてみます。
悲鳴みたいな音のこともあるのですね。ウオンウオンだと思っていました。勉強不足ですみません。ありがとうございました。
Q:チェロを購入したいのですが・・・
投稿者:渡邉 投稿日時:2005/09/25 11:55 ---3.136.225
こんにちわ、学校の音楽部でチェロをやっています。高校も続けるつもりで、購入しようと思い、探しているところです。 将来は、音大のピアノ課を目指していますので、チェロは趣味になってしまうのですが、音色の良いもがほしいと思っています。 インターネットのオークションで
「COPY of AntoniusStoraDivariusCremonenlisFaciebatAnno1719Made in WesternGermany」西ドイツ製、スチューデントモデル、ペグは黒檀製(エボニー)
というのを見つけました。どうでしょうか?
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/09/26 00:33 ---6.34.221
ということは、今中学生ということですね。それを前提に回答します。
(「」の中はラベルの表記として回答します。)
・Made in WesternGermany = 西ドイツ製 と書かれているということは、普通は15年前〜60年前の間に作られた量産品であることを示します。西ドイツの場合は戦後であれば、楽器工場で作られたものである可能性が高いです。
なお、ヴァイオリン族の楽器の場合、100年たったものでもまだ若造ですので、戦後に作られたものはまだ若い(青い?)楽器です。
・「COPY of Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 17**」というラベルは星の数ほど使われ、これはほとんど意味をなしませんので、飾り程度に思ってください。有名なストラディヴァリウスのチェロのコピーということになりますが、量産楽器においては、困った時のおまじないのようなものです。
・スチューデントモデルというのは、一般にはそのメーカーでの一番下のクラスを指します。
・ペグについては、黒檀(エボニー)・ローズウッド(紫檀)・柘植(ボックスウッド)以外の場合は気にしてください。たまに量産楽器ではもっと安く強度のない木を着色したものが使われている事がありますので、そのような楽器は避けるべきです。
従って、その楽器の説明は、車で例えれば「5年経った中古車のセダン、日本製、1300cc普及クラス、アルミホイール付き」と言った表現に近いですね。それで、その車がバリバリ走るかどうかわからないのと同様に、そのチェロが良い音色かどうかは分かりません。下の方のグレードのものであろうことだけはわかります。
楽器を見て善し悪しを判断できない場合、まずは信頼できる売り手を探す事が先決です。
投稿者:CABIN 投稿日時:2005/09/26 18:04 ---114.112.42
おそらく安価に楽器を購入されたいのだと思いますが,私見かつ参考まで...
某オークションのそのチェロには,ネック折れがあるようですが,もし修理部分がダメになった場合,恐らく修理には相応の費用が必要になるでしょう。ほぼ完全な修理を望むなら,ネック交換となりますがその費用は20万程度です。
先ずは,このようなリスク(ネック折れと,折れた時に楽器にかかったと思われるストレス)を持った楽器だと思われるということです。
但し,素性が良く分からない楽器ながら,現在の価格で買えるような楽器では無いのかもしれません,即修理部分がダメになるかどうかは分かりませんし,案外これから使う期間で問題ないのかもしれません。
それ以上の情報が得られそうに無いので,これもひとつのカケですね。
私見ですが,そのチェロについてのコメントとしては,もし現在の価格で落札できるのであれば,壊れても勉強代と割り切る,意外と良い楽器で壊れなければラッキーだったというところではないでしょうか。
茶化したり冗談で言っているのではありません,念のため。
投稿者:渡邉です。 投稿日時:2005/09/30 19:25 ---3.246.89
メール有難うございました。チェロのことは全く知らなかったので、勉強になりました。あのチェロは、結局最初の倍以上の値段で他の人が落札されました。またこれからも探すつもりなのですが、やはり、元の値段(定価)が20万以上のものがいいんでしょうか?
投稿者:cello 投稿日時:2005/10/01 03:44 ---177.83.221
弦喜さんのアドヴァイスにあるように、「まずは信頼できる売り手を探す事が先決」ではないでしょうか。
購入後の調整・修理(の長いお付き合い)を考えると信頼できる楽器店・工房で、予算を明確にした上での購入が結局は賢い買い物となるように思います。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/10/01 08:29 ---6.34.243
以下、私見です。
信頼できるお店の目利きが選び、そのお店が責任をもって調整を行った、中国製の手工業・半手工の楽器は、チェロで言えば50万円以下、ヴァイオリンで言えば30万円以下の中ではもっとも注目すべきおすすめの楽器の一つと言えます。
「ガラス玉もものすごくたくさんあるけれども、ダイヤの原石もその中にはある程度含まれており、ちゃんとそれらを選びだし磨き上げれば、安価でとてもよいものとなる。」というのが、私の今の中国製の楽器に対するイメージです。
ガラス玉を「安いよ!、安いよ!」といって表面だけ光らせて売るようなお店もあるかもしれません。またそれが意図である場合と、見る目と技術がないので悪意なくやっている場合の両方のケースがあります。
従って、そのお店の楽器を見る目と、調整・アフターサービス含めたそのお店の経営方針が非常に重要であり、まずは信頼できるお店探しからスタートするのが安心して楽器を購入するための基本です。
投稿者:プレスト 投稿日時:2005/10/01 21:24 ---121.63.231
相談とは関連がないのですが、偏見があるようなので敢えて…。
「Western Germanyだと普通は量産品」
「西ドイツの場合は楽器工場で作られたものの可能性が高い」
確かに、この相談の件についてはその通りと思われます。しかし一般論としてはどうでしょう。旧西ドイツにも優れた製作者は数多く存在しました(そして現在も存在します)。
「ドイツ、イコール量産」というイメージが先行している傾向があり、その偏見にしばられている方が多い感があります。しかし、「普通は量産」とみるのは、誤りと言わざるを得ません。
これは、日本の場合と同程度に言えることだと思われます。
なお、信頼できる売り手を探すのが先決という弦喜さんの見解に、まったく同感です。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/10/01 23:53 ---6.34.134
>>プレストさん
あまり反論はしたくないのですが、下記、質問と私の考えです。
Made in Western Germany と自分のラベルに書く優れた製作者をご存知でしたら、お知らせください。
COPY of AntoniusStoraDivariusCremonenlisFaciebatAnno1719Made in WesternGermany とだけ書く製作者でも結構です。
自分の名前を書かず、Made in WesternGermanyと書く製作者を私は知りません。
Franceというラベル、Made in Italy と書かれた楽器も見ていますが、このように都市名あるいは地域名ではなく国名が書かれた楽器は、いずれも、手工含む量産楽器(名の知れた量産工房含む)でした。
個人製作者の場合、普通は名前とその地名(ミッテンヴァルト、マルクノイキルヘン、ベルリン、ライプチッヒなど)が書かれると思ってます。
私は本物のオールド楽器は別にして、イタリア志向はまったくありませんし、地域による偏見はもっていないつもりです。
先の発言が説明足らずで誤解があってはいけませんので、若干説明を加えます。
私の論理は、
「Made in Western Germany と書かれた楽器のほとんどは西ドイツの量産品。
西ドイツという表記は第二次世界大戦以後のことであり、それであれば量産品の多くは機械化を伴う工場で作られている。」ということです。
ドイツには優れたマイスターはたくさんいて、精緻な作品を生んでいますし、いろいろなコンクールでも賞をとっていることはわかっています。また古い量産工房で、まったくあなどれない楽器を生み出しているところをいくつも知っています。
ただ、そのような楽器で「COPY of Antonius Stradivarius Cremonenlis Faciebat Anno17** Made in Western Germany」などというラベルが貼られたものを見た事がないのも、私にとっての事実です。
投稿者:プレスト 投稿日時:2005/10/02 09:21 ---121.63.231
いつも論理的な弦喜さんらしくない、筋の通らない反論に驚きました。
>Made in Western Germany と自分のラベルに書く優れた製作者をご存知でしたら、お知らせください。
→ たくさん存在します。もちろん、「書く」ではなく「書いた」ですが。
>自分の名前を書かず、Made in WesternGermanyと書く製作者を私は知りません。
→ これは私も知りません。
>Made in WesternGermany = 西ドイツ製 と書かれているということは、普通は15年前〜60年前の間に作られた量産品であることを示します。西ドイツの場合は戦後であれば、楽器工場で作られたものである可能性が高いです。
→ この記述が適切でしょうか。これに対する見解として、「確かに、この相談の件についてはその通りと思われます。しかし一般論としてはどうでしょう。」と前置きした上で申しました。
今、彼らドイツの製作者達が、マイスター制度の法的変更などによる苦境にあることはご存知かと思います。そして先だってのドイツ総選挙の結果…。そのような中において、到底容認しがたい表現と思った次第でした。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/10/02 09:48 ---6.35.151
プレストさん
上記ご指摘の件が私の単なる思い込みであり、一般的な話でないならば、私の考えを改めたいと思いますので、下記ご教授いただけますか?
>>Made in Western Germany と自分のラベルに書く優れた製作者を
>>ご存知でしたら、お知らせください。
>
>→ たくさん存在します。もちろん、「書く」ではなく「書いた」ですが。
具体的には、誰でしょうか? 数名挙げていただければ結構です。
(ドイツ語でもなく、イタリア語でもなく、英語でMade in Western Germanyとラベルに記載した製作者です。)
現在、Made in Germany と書く製作者でも結構です。
(私はMade in Western Germanyは、ドイツ外への輸出を強く意識した商品に付けられる表現のように思っておりました。)
プレストさんとは根っこの部分では考え方にずれはないと思っていますが、ラベル記載に対する認識は違いますで、それをはっきりさせたいと思います。(コンテンポラリのドイツ製作者の楽器はラベル含めあまり見ているわけでなく、私の思い込みであれば是非この機会に勉強して改めたいと思います。)
投稿者:プレスト 投稿日時:2005/10/02 10:20 ---121.63.231
>具体的には、誰でしょうか?
私の周囲にも数点あります。具体的な名前を挙げることは私の素性を明らかにすることになりかねませんので、ここでは控えます。
ヤロベックの辞典はお持ちですか? お持ちでしたら、巻末のラベル集をご覧いただければ、参考になるかと思います。
なお、「ドイツ外への輸出を強く意識した、ドイツ(ないしドイツ語圏)職人による手工ヴァイオリン」は、戦前より存在していました。
投稿者:すじこ 投稿日時:2005/10/02 12:47 ---2.10.217
プレストさんのご意見に賛成です。
私も個人製作家の楽器でMade in Western Germanyと書かれた楽器は見たことがあります。
それに、現代でも弓製作家の中にはフロッグの後ろのスティックの部分にGermanyと刻印する方がいます。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/10/02 14:16 ---6.35.151
お二人の方から、経験に基づく意見をいただきましたので、先の下記の発言については、言葉足らずかつ断定しすぎた発言として、取り下げさせていただきます。
>・Made in WesternGermany = 西ドイツ製 と書かれているということは、
>普通は15年前〜60年前の間に作られた量産品であることを示します。
>西ドイツの場合は戦後であれば、楽器工場で作られたものである可能性が
>高いです。
文頭に、「製作者名も製作地も書かれておらず、」を記載しておくべきでした。
プレストさんのご指摘に基づき、2時間ほどかけて製作者ラベルを調べてみましたので、参考のためその報告をさせていただきます。
・R.VENNESのユニバーサル・ディクショナリにあるラベル2600点の中には、Made inと書かれたものは見当たらず、またGermanyと書かれたものも見つかりませんでした。ドイツのものはほとんどドイツ語であり、名前および地名が書かれています。ドイツ製作者での英語表記は、E,Martinがmade by 名前、Copy of, と使っているくらいでした。
・ヤロベックのドイツ・オーストリアの製作者事典文中には、Western無しの、Made in Germany と書かれたラベルは5点ありました。すべてマルクノイキルヘンの地名の後に小さくMade in Germanyが書かれています。1点は工場といってよいメーカーであり、あとは楽器製作の一族の中の一員というべき製作者に見えます。多分20世紀初頭に米国用の輸出楽器を製造・販売していたのでしょう。ただ数千人の中の5名ですので、主流ではなく少数派とは言えるでしょう。
Made in Westen Germany については、多分資料が古いため載っていなかったのでしょう。これについては、コンテンポラリのドイツ製作者の事典・資料は、ほとんど流通していないので、やはり実物を数見ないとわかりませんね。それ故、経験者の方の意見に従います。
投稿者:プレスト 投稿日時:2005/10/03 06:02 ---121.63.231
弦喜さま、詳細な調査されたとのこと、真摯な姿勢に心打たれます。訂正されたところ以外に関し、まったく異論なしなのは言うまでもありません。
なお、言わずもがなとは思いますが、蛇足として以下。
1.ヤロベックは17世紀以降の作品を掲載、そして「Made in …」の記載が始まったのは20世紀初頭と思われます(前後するかもしれません)。となると、殆どが戦前までの掲載であるヤロベックの辞典において5点というのは、決して少なくないわけです。
2.件の記述は「輸出を強く意識した製品」になされるものなので、当然ヨーロッパにおいてよりここ日本でのほうが、見かける割合が高くなります。
Q:バイオリンのダブルケースについて
投稿者:どらねこたま 投稿日時:2005/09/28 12:23 ---166.55.94
バイオリンのダブルケースの購入を考えております。
購入の際,考慮すべき点や推薦できる商品がありましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。
投稿者:いし 投稿日時:2005/09/28 22:52 ---210.9.72
私が使用しているのはヴァイオリンとヴィオラ用のダブルケースですが、購入時の注意点があるとすれば、
「小物入れが小さい」
ということです。
せいぜい松脂とミュートが入るくらいで、肩当てなどはまず入りません。チューナーも難しいでしょう(私は音叉を使うので入れられますが)。
ですから本当に2挺持ち歩く必要があるのかどうかも含めて、何を持ち運ぶのかをじっくり考えて選ぶようにして下さい。
投稿者:QB 投稿日時:2005/09/29 02:02 ---175.176.2
可能な限り、実物を持っていって、実際に入れてみることをお勧めします。
私が以前に使用していたダブルケースでは、当時持っていた楽器の一つがロワーバウツがスリムだったため、意外なほどケース内で動き、もう一つの楽器と布越しに緩衝する可能性があることがわかり、ちっちゃなクッションを入れて予防していました。
また、一般的に裏板面に当たる部分のクッションや曲線が1台用のケースに比べて無い(殆ど無い)ものも多いですから、その点も確認されたほうがいいと思います。
私自身それほど多くを試したわけでは無いですが、自分の買ったダブルケースの反省点もふくめて、今まで見た中で「これを買えばよかったな」と思ったのはBAMでした。
http://www.bamcases.com/string_instrument_cases/double_cases/index.php?l=en
投稿者:スチールラヴァー 投稿日時:2005/09/29 08:55 ---25.150.62
bobelockの物を使ってます。
造りはシングルのものと同じで、頑丈です。サスペンションもしっかりしてます。
肩当は入りません。
http://www.bobelock.com/specialtyCases/1015.html
ダブルケースの注意点としては、一方の楽器のペグと、他方の楽器のCバウツの角が当たらないか確認すること、かな。
投稿者:どらねこたま 投稿日時:2005/10/01 21:49 ---44.30.126
皆さま 貴重なご意見ありがとうございました。
いただいたご意見を参考に検討いたします。
ダブルケースを購入する目的は,保管用が主です。
ただ,肩当が入るスペースはほしいかなと思っています。
ムサフィアのダブルケースがあると聞いていますが,使用されている方はいませんか?(今使用しているものがムサフィアで気に入っているものですから。)
>QBさんへ
バムのケースのよい点はどのようなところでしょうか?
差し支えなければお教えください。
Q:楽器の調整はどこで・・・
投稿者:パピ丸 投稿日時:2005/09/27 14:40 ---15.198.130
ヴァイオリン本体と弓を別々の店で買った場合、楽器の調整や毛替えは、それぞれ買ったお店で行いますか?私の場合、ヴァイオリンを日本弦楽器製作者協会正会員の方の工房で買いました。ただし、その方の作品ではなく、海外のメーカー製です。そして、弓は、弦楽器専門店で購入しました。なんとなく、弦楽器製作者協会の方の方が腕がいいように思われますが、弦楽器専門店で、とてもよくしていただいたので、このまま縁切れでは申し訳ない気がします。
お聞きしたいのは
・買ったものは、買った店で、それぞれ調整するのがよいのか?
・楽器店の職人さんって、日本弦楽器製作者協会正会員の方と比べて、どれくらいの腕なんでしょう?(こだわるほどの楽器ではないのですが・・・)
・そもそも、日本弦楽器製作者協会正会員とか準会員というのは、どうやってなるものなのですか?試験とかあるのでしょうか?
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/09/27 21:44 ---6.35.22
>・買ったものは、買った店で、それぞれ調整するのがよいのか?
店によります。アフターサービスのために職人をかかえている老舗は、市販のパーツを使わない修理・調整は、安価あるいは無料でやってくれますので、自分の楽器の主治医として末永くおつきあいするのが正しいと思います。(大阪北浜の老舗で購入し私が20年使った楽器は、ネック上げ、駒の新調、ペグのためのブッシング含めて学生や新入社員の身で高いと思う修理代を払った記憶がありません。多分無料だったか、1万円以内だったのでしょう。)
販売した楽器に対ししっかりと修理代をとり、また腕も今イチと思われる場合は、もっとよい主治医を探した方がよいです。
>・楽器店の職人さんって、日本弦楽器製作者協会正会員の方と比べて、
>どれくらいの腕なんでしょう?(こだわるほどの楽器ではないのですが・・・)
これに人によりけり。ただ言えることは、キャリアの長い職人さんは調整のプロであり、数多くの調整の経験に裏付けされた調整の技術があります。楽器製作者の方は製作のプロであり、食べていくためには調整も行わなければいけませんが、軸足は製作にあります。どちらがたくさんの楽器に触れるか、ということを考えると、普通は職人さんに軍配があがります。
最後の質問は、わかりませんので、詳しい方の回答を待ちます。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/09/27 23:49 ---6.35.22
↑
誤:これに人によりけり
正:これも人によりけり
失礼しました。
投稿者:ストラッド店員 投稿日時:2005/09/29 12:42 ---102.18.200
こんにちは、
>そもそも、日本弦楽器製作者協会正会員とか準会員というのは、どうやってなるものなのですか?
日本弦楽器製作教会のホームページです。
http://www.jsima.jp/indexjp.htm
お問い合わせ下さい。
上記ページでも書かれていますが、準会員は完全に独立して現在は「日本バイオリン製作研究会」になりました。
http://www.geocities.jp/violinmakerjp/index.html
ちなみに、当店店主もこの会の会員です。それでは!
投稿者:パピ丸 投稿日時:2005/09/29 15:40 ---15.198.130
弦喜さん、ストラド店員さん、回答をありがとうございました。
弦喜さんの説明、納得できました。
弦楽器製作者協会の会員であるかどうかは、あまり関係ないんですね。
ストラド店員さんが貼ってあったリンクを見ると、楽器店も会員だったりするんですね。
ということは、弦楽器製作者協会の会員と弦楽器専門店の工房という肩書きでの比較自体、意味がないということが分かりました。
ありがとうございました。

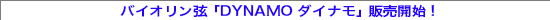
Q:ひどり手塗りよりは・・・
投稿者:ギブソン&ヘッジス 投稿日時:2005/10/06 07:45 ---110.60.169
前々から抱いてた疑問があります。量産品と完全手工業品では板の形成などで後者以外に選択の余地がないことはよく分かります。そこでニスについてです。部分的に厚く塗る、重ね塗りを感覚で調整する。手作業ではこういうことが実に丁寧にできます。しかし、廉価な手工業品(ホントかどうかも分かりませんが)の場合、手塗りのニスが吹きつけのコンプレッサーに劣るということはないのでしょうか。こういうことを言い出せば、接着でも何にでも該当するかもしれません。結構酷い手塗りのニスを目の当たりにすると、これなら吹きつけの方がマシなのでは?と思ってしまいます。あらやる状況において、量産品が一部の手作業の物に必ずしも劣るとは限らないことは事実だと確信しています。特にニスにそのことが目立つと思って書かせて頂きました。コンプレッサーによるニスの塗装は、使う材料やその方法などで、やはりそれなりに問題があるのでしょうか。
投稿者:かめ 投稿日時:2005/10/06 19:12 ---196.107.130
有名クレモナ新作製作者の中にもコンプレッサーによるニスの
吹きつけを行う作者が数名います。
結構酷い手塗りのニスということですが、ニスの仕上げ段階の
方法の違いでニスが荒々しく見える場合もあります。
要は塗る方法がどうだとか言うことよりも使われているニスの
材質が重要なのではないかと思います。
投稿者:ギブソン&ヘッジス 投稿日時:2005/10/06 19:43 ---110.60.169
知りませんでした。ありがとうございます。ところで比較的伝統を重んじると思われるバイオリン作りの世界で、この機械を使った吹きつけは異端と映っていないのでしょうか。それからオイルニスなどはイメージとしてコンプレッサーには不向きのようにも思えるのですが・・・全く無知なことばかり言っていると思いますが、もう少し勉強させて頂けると嬉しいです。
投稿者:セイジ 投稿日時:2005/10/08 02:30 ---151.3.240
>結構酷い手塗りのニス
刷毛の跡をわざと残して、それが味わいになっているモラッシ(父)
のような作家もいますので、コンパウンドでつるつるに磨きあげた
ものがよいとは、必ずしもいえないでしょう。
モラッシの子供のシメオネはつるつるに磨き上げていて、父親とは
まったく仕上げの印象が異なりますが、それも好みの違いということ
で、技術の上手い下手ではありません。