弦楽器 Q&A
弦楽器に関するいろいろな疑問にお答えします。
2023年12月31日をもちまして、新規投稿・コメントの書き込みを終了させていただきました。
5203件のQ&Aがあります。
Q:ネック
投稿者:ベルリン・フィルのファンです 投稿日時:2005/09/20 18:48 ---110.59.1
基本的なことを質問させてください。学生になってからバイオリンを初めて数年が経ちましたが、そこそこ古いバイオリンを使っているせいか、最近、バイオリンのネックのニスが消えてしまったように思います。はじめからかなりニスが薄くてないような状態でした。ネックの部分はニスが違うとか、薄いとかと友達は言います。私にとっては大事な楽器なので、ニスを塗った方が良いのであれば、そうしたいと考えています。何かヒントになるご意見を頂けると嬉しいです。
投稿者:hill 投稿日時:2005/09/20 21:44 ---166.28.239
ネックは普通作った時点で他とは違っています。
一番手が触れる部分ですので綺麗に仕上げてもすぐに痛んでしまいます。
ですから薄いニスを塗るか、オイルフィニッシュなどで仕上げます。
低価格帯などではそのまま何も塗らないものもあります。
ネックのニスがほとんどない状態でも特に問題は起こりません。
ですがその状態で使っていると汚れが染み込んできますので気になるようでしたら薄くニスを塗ってもいいかもしれません。
(汚れが染み込んでもよほど酷くなければ落とすことはできます)
その場合手触りなども変わってきますので少し感覚が変わる可能性はあります。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/09/20 22:32 ---6.34.41
hillさんの意見に同意します。
以前、ネックにも本体と同じようなニスが塗られた新作手工楽器を入手したことがありましたが、なんとなく滑る感じがするというのか、厚ぼったいというのか、とても違和感があり、手放したことがあります。
個人的には、上質の木材を使い表面をきれいに磨いた上で、オイルフィニッシュで仕上げたネックの手触りが好きです。
投稿者:nodame 投稿日時:2005/09/21 11:47 ---205.169.122
ベル・フイル・ファンさんへ
イタリア製の楽器にはよくニスが塗ってありますが、すべりが今ひとつ良くないとおもいます。 弦喜さんのおっしゃるようにオイルフィニッシュが一番だと思います。日本のプロプレイヤーは大体オイルフィニッシュにしていると思いますが如何でしょうか? 若しご自分でやりたいのであれば、具体的には先ずネックの親指の動く部分のニスをスクレッパーではがし(ナイフの背でも良い、アルコールで拭いても良いが他の部分のニスをいためるといけないのでお勧めできません)次にネックに水をつけて600番のサンドペーパーで磨くこの水と600番ペーパーの作業を3回くりかえす。すると水をつけてネックを手で擦っても垢のような物が出なくなる。此れが乾いたらリンシードオイルを布切れにつけて塗ります。リンシードオイルはハンズに売っていると思います。リンシードオイルは時間が経つと木の中で固まりますのでそれ程汚れは染み込まないと思います。DIYがお好きな方であれば自分でやれる程度のことですが・・(RESTORERでも秘中の技だと思います)
投稿者: ベルリン・フィルのファンです 投稿日時:2005/09/21 16:11 ---110.59.240
いろいろ情報をありがとうございます。大変勉強になりました。気に入ってるバイオリンなので不器用な私がDIYする気はありませんが、教えて頂いたように工房にオイルフィニッシュのことを伝えてお願いしようと思います。他に何かリペアの時に工房の方に伝えた方がいいことはないでしょうか。
投稿者:nodame 投稿日時:2005/09/21 20:29 ---205.169.122
ネックの汚れを取ったり、ニスをはがしたりすると古い楽器でも木の地肌は結構白く新しく見えるようになりますので磨いた後オイルフィニッシュの前にステインをかけてもらった方が良いと思います。虎もくがついていればオイルだけかけるよりずっと見た目が映えます。色は古金茶(altgoldbraun)か茶色いろを適当な薄さでかけるのですが細かい事まで指図すると仕事を引き受けてもらえませんね!! ”出来れば楽器の古さに会ったステインをかけて頂くのはどうでしょうか””位のことを言えばよいと思います。どちらに転んでも致命的なことは有りません。気にいらなければ其のうち他の工房に持ち込めば何とでもなることです。
Q:バイオリンケースについて
投稿者:ryu 投稿日時:2005/08/30 15:19 ---249.70.98
bam のHIGHTHCH という軽量ケースの使用感はどうなのでしょうか?今はGEWAのケースを使っていますが、移動には少し重いので、移動用として購入しようかと思っています。多少なら雨に濡れても平気なようですし、デザインも斬新で気になるのですが、ケース内の温度変化などについては心配です。
投稿者:rio 投稿日時:2005/08/30 15:47 ---9.121.163
ハイテックは知人が使ってます。
雨には確かに強そうです。
温度変化というのは、結露ということでしょうか?
それとも、保温(外気温度から、内部の楽器を守る)という意味でしょうか?
市販され、使っている方もいるので
一般的な使用環境下では問題ないと考えて
良いと思います
軽いケースの、メリットデメリット
重いケースの、メリットデメリット
上手く理解して、使い分けする方が良いと思います。
移動で軽くならば、
所謂だるま型ケースが一番だと思います。
投稿者:セイジ 投稿日時:2005/08/30 16:29 ---151.3.240
行きつけの楽器店でこのケースの構造部材を
輪切りにしたものを見せてもらったことがあります。
炭素繊維のような硬い表皮の下にスポンジか発泡スチロール
のようなもの(厚みは5mmぐらい)をサンドイッチ状に
挟んでありました。断熱効果が高い素材だそうです。
衝撃の吸収は楽器を支えるスポンジ製の枕で受けるそうです。
木製のケースと違って内部空間がたっぷりあるのが特徴ですね。
投稿者:ryu 投稿日時:2005/09/09 18:41 ---249.70.98
参考になりました。先日お店で見せてもらいました。ちょっと内装がシンプル過ぎて安心感に欠ける印象を受けましたが、バイオリンにとっては、内部空間が広いほうが良いとも聞くので実際にバイオリンを入れてみて、収まりが良い感じであれば購入してみたいと思っています。
投稿者:スチールラヴァー 投稿日時:2005/09/09 19:38 ---25.150.62
ケースの素材、さらに銀色の外装、ということで、直射日光にも結構強いんじゃないかと期待していましたが、期待はずれでした。断熱効果という点では、他のBAM製品のほうが強いのではないかと思ってます。
投稿者:ベルク 投稿日時:2005/09/10 06:32 ---110.59.125
バイオリン・ケースに関して便乗させてください。バイオリンについてはほとんど知識がないので教えてくださるとありがたいです。現在、使用しているケースはもともと付属してきたいかにも安いという感じの物です。そこで少し(あまり高いのは無理なので)はマシな物をと考えています。たまたま店で目に入ったケースはGEWA、GATORという二つのメーカーでした。GEWAはドイツの弦楽器を中心とした会社、GATORはアメリカの楽器ケースの総合メーカーらしいみたいですが、この2つのメーカーのケースについて何かご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
投稿者:momo 投稿日時:2005/09/11 12:32 ---6.141.230
私が使用した感じでは熱には強いほうだと思いました。
私が今までに使用していたのは
東洋の紺・ゲバの黒・スーパーライトの黒でどれも角ケースですがこれらよりは耐熱性においてよかったです。
ただ、私が直射日光に触れる時間はいつも20分程度で、これ以上となるとわかりません。
また、バムの他のケースは知らないので何とも言えませんが私的には満足しています。
投稿者:便乗娘 投稿日時:2005/09/19 22:18 ---1.45.91
便乗します。
たぶんトピ主さんは角形の方のHitechのことを言われているように思われますが、同社の小型版の↓をお使いになった方いらっしゃいませんでしょうか。
素材的には角形と同じと本家サイト(英語)にはありますが、内部の詳細など使用者の方の感想が聞きたいです。安いものじゃないので...
http://www.violinsupply.co.jp/Link/items/BamForme.html/bamforme.html
投稿者:むーみん 投稿日時:2005/09/20 22:36 ---116.63.98
このケース現在使っています。
軽くて持ちやすい形状です。
おしゃれで目立ちます。ただし,傷は目立ちます。
内装についてですが,主にネックとテールピース付近で支える構造になっているので,ふくらみがある楽器には負担がかからず良いと思います。ただし,以上の二点でしか支えていないので,小さめの楽器ですと不安定感があります。
肩当を入れる専用の場所がありません。私はネックの横に入れてます。また,小物入れも小さいです。弦が入りません。だから,これもネックの横に入れています。
中敷がないので,これらのものが楽器に直接当たらないように,楽器をシルクの袋に入れています。
私はシルクの袋に楽器を入れてからケースいれ,その周りに楽器を拭くクロスをつめて中で楽器が動かないようにしています。
楽器の止め具が2箇所しかありません。蓋と本体の間はパッキンのようなものがありますが,雨など大丈夫かなぁと思います。劣化が心配ではあります。温度変化に対しても,特別に良いとも悪いともいえない感じです。
要は,買ったそのままの状態で使うと,二つの止め具を止め忘れたら,ばこっと蓋が開いて楽器が丸出しになるのです。忘れなきゃいいのですけどね。
不安要素を結構書いてしまいましたが,普通に持って運ぶには,丈夫で軽くて,持ちやすいので気に入っています。
落としたときは…?落としたことがないのでわかりません。
長文失礼致しました。
投稿者:便乗娘 投稿日時:2005/09/21 12:20 ---1.45.91
むーみんさん
ていねいなレポありがとうございます。たいへん参考になりました。
特に肩当てなどの入れ方など実ユーザさんならではのきめこまかな視点で語って頂きためになりました。深くお礼申し上げます。
Q:購入を考えている楽器の事ですが,
投稿者:KH 投稿日時:2005/09/21 09:54 ---8.53.111
どなたか,何かご存知なら教えてください.子供達のチェロとバイオリンのフルサイズを探しています.予算内でいろいろ試して一番のお気に入りが,
1)チェロ Konrad KRC 1958
2)チェロ弓 Cuniot−Hury
3)バイオリン V.F. Cerveny &Sons 1862
4)バイオリン弓 Charles Bazin
です.子供達が良いと言うのなら,素性は二の次とも思うのですが,貧乏人にとっては大きな買い物なので,値段が妥当かどうか気になるというのが正直なところです.
ネットで検索したところ,チェロと同一の制作者のバイオリンが海外で売りに出されており,値段的に納得がゆきました.
気になるのはバイオリンの方で,V.F. Cerveny &Sons はどうやら金管楽器で有名らしく,そのmakerのバイオリンは購入予定の1/4位の価格で売りに出されているのを見つけ,迷っているところです.もちろん楽器の状態により値段は大きく左右されるのでしょうが.先生に弾いていただいたところ,渋めの個性的な音色らしく,先生ご自身は第二希望のフランス製の明るい音色の方が良いかもとおっしゃるのですが,娘はどうしてもこの楽器の音色に固執してます.
それからバイオリンの弓ですが,楽器店ではオールドを薦められたのですが,先生の持っておられるほぼ同じ値段のギオーム(ギョーム?)とか言う新作が,娘は一番弾きやすかったそうです.楽器店に問い合わせたところ, このmakerの弓を注文することは出来るけれども,試奏なしで必ず購入することが条件のようなので,これも悩んでいます.
バイオリンの第二,第三希望に,Didelotフランス製,Josef Kreutzerチェコ製,などもあがっています.
もし,これらの楽器や弓に関して情報,体験などを教えてくださると,大変ありがたく思います.
STRAD様,掲示板だけの利用でごめんなさい.もし,関東に住んでいたら,必ず訪れてみたい楽器店です. うちから遠すぎて.
Q:ラベルはどうやってつくるの?
投稿者:rio 投稿日時:2005/09/19 02:57 ---29.242.228
楽器の中に貼っているラベル
あれはどのような紙を使い
インクはどのようなものを
一般に用いて作られるのでしょう?
(紙は?)
まさかPPC用紙ではないでしょうし
長持ちするように中性紙を使うのでしょうか
それとも、お札に使われるような丈夫な紙?
昔ながらの習字の半紙のような紙?
それとも羊皮?
(インクは?)
年号は時とともに薄れてきているのを見ますので
万年筆のインクだと思うのですが
それ以外の印刷になっている部分は
日本画のような顔料なのでしょうか?
それとも油彩のような絵の具系?
それとも習字の墨?
自分の所有する分数楽器の
右側のF字から
ラベルを追加で貼ってしまおうと
画策しているのですが
どうすればいいのかわからず
ご相談するしだいです
よろしくお願いいたします
投稿者:M 投稿日時:2005/09/19 16:24 ---15.206.247
近所の工房にご相談を。
ホームセンターで厚和紙、墨汁なんてのはどう?
投稿者:rio 投稿日時:2005/09/20 00:22 ---29.242.228
M様ありがとうございます
電話で工房に聞いてみました…
お勧めは、
三椏(みつまた)でつくった紙
&
鉛筆
とのことでした
rioさんが生きている間は
たいていの、染料は退色しないので
何使っても大丈夫って
仕方なく、和紙専門店で
25種類紙を買ってきて
検討してみます
ありがとうございました
投稿者:rio 投稿日時:2005/09/20 11:28 ---148.72.231
訂正です
誤
>25種類紙を買ってきて
正
25種類の紙を買いました
Q:弓の持ち方
投稿者:通行人 投稿日時:2005/09/19 13:45 ---181.148.110
弓の持ち方って3種類くらいありますけれど、
みなさんはどうされていますか?
曲によって使いわけるものでしょうか?
投稿者:M 投稿日時:2005/09/19 16:20 ---15.206.247
曲によってどころかその曲のフレーズによっても変えます。
ちなみに私はロシア流です。
投稿者:通行人 投稿日時:2005/09/19 19:40 ---181.148.110
M様、ご回答ありがとうございます。
ロシア流、ドイツ流、フランス・ベルギー流が主流と考えてよろしいでしょうか?
フレーズごとに持ち方を変える(人差し指の持ち方を変える)
ということでしょうか?
小指の位置も弱冠、先生によって違うようですね。
投稿者:たこちゅう 投稿日時:2005/09/19 22:17 ---188.212.162
フレーズによって弓のもち方を変えるって、どういう風にでしょう?
ロシア流は主に肩から肘の筋肉を使って弾きますよね?弓の持ち方も深いし、フレーズごとに浅くしたりするのって可能なのでしょうか? 私は以前フランコベルギー流で弾いていましたが、ロシア流に変えた時期もあります。また、ドイツ流の先生についていたこともありますが、今私は自分で一番持ちやすい形にアレンジしています。(フランコベルギーとロシアの中間くらいです)
ロシア流は、音が力強いですが硬い気もします。あと細かい表現ができにくいようにも思います。フランコベルギーだと長時間練習すると手が疲れます。 イツァーク・パールマンも腱鞘炎に悩まされてるとききました。(本当かどうかは疑問??ですが)
同じスタイルのボウイングでも先生によって若干違いがあります。手の大きさ、指の長さなど、個人差があるせいでしょう。
Q:バイオリン弓について
投稿者:迷弓 投稿日時:2005/09/19 18:43 ---124.72.95
地元の楽器店でE.Sraviero−Cremonaの焼き印が押してある弓を気に入り商談中です。40万円弱なのですが、これって適性な価格と考えていいですか。ネットのお店でも余り出てないような気がします。またこの作者に関する情報をお持ちの方、何かアドバイスをお願いします!
投稿者:かめ 投稿日時:2005/09/19 18:52 ---196.107.130
適正な価格っていうのは、買い手が決める物ではないでしょうか。
あなたが40万円払ってもその弓がほしければ、それは適正価格
っでしょう。
楽器はひとつひとつ出来が違いますし、価格も製作者と販売者が
比較的自由に付けることができますから、ほしい人がたくさん
いるような楽器(製作者)は必然的に高くなりますし、売れない
製作者は価格を下げないと売れません。
投稿者:迷弓 投稿日時:2005/09/19 19:24 ---124.72.95
ありがとうございます。適正価格に関するアドバイス、まさにその通りと思います。ただ限られた予算、というかけっこう背伸びしての購入になりますので、庶民感覚で言うと、どうしてもだいたいの相場というものが気になってしまいます。済みません!それから銘は「E.Slaviero」の誤りでした。引き続き皆様の情報お願いします。
投稿者:かめ 投稿日時:2005/09/19 19:47 ---196.107.130
店によっては63万程度の価格を付けているので、40万くらいの値段でも良いんではないでしょうか。私も過去に2本見たこと
がありますが、私は購入には至りませんでした。ちなみにその時
の値段はもう少し安めでしたが、5年ほど前なのであまり参考に
なりませんね。
投稿者:迷弓 投稿日時:2005/09/19 21:17 ---124.72.95
ありがとうございます。参考にさせていただき、いましばらく熟慮します。
Q:ご報告:パリの楽器店&蚤の市
投稿者:窓際のVn弾き 投稿日時:2005/09/19 20:11 ---149.69.196
先日,パリのRue de Rome沿いの楽器店と蚤の市について質問させて頂いた者です.仕事の帰りに立ち寄り,今帰ったばかりのところです.
Rue de RomeのLe Canu-Millantで工房製の弓を1本買いました.Le Canu氏の息子さんが英語で応対してくれましたが,大変親切な,感じの良い方でした.値段は,ここで教えて頂いたとおり日本の価格に較べると信じられないくらい安価です.ご本人の弓は修行を終えたと言うことでしょうか,すでに高価になっていました.お母さんらしき女性も出てきましたがこの方も大変親切にDETAXの手続きについて説明してくれましたし,かわいいわんちゃんも出てきて立ち上がって歓迎してくれました.また試奏用に借りた楽器は百数十年くらいたっているフランスの工房製とのことでしたが,ビックリするほど良い音でした.ストラッド店主様の言及されていたのはこんな楽器のことなのでしょう.ただし値段は結構高いです.
Rue de RomeとRue de Madridの交差する当たりに店を構えているAtrier AllienorではBAMのケースを買う予定でしたが残念ながら在庫がありませんでした.ここも英語で親切に対応してくれました.値段を聞いてみたのですがバーゲンではないので日本の,3〜4割引といったところでしょうか.
蚤の市へは,時間がなくていけませんでした.しかしこのようなところでより楽器を見つけるには,何年も時間をかけて日参するような覚悟で行かないとだめなのかもしれません.
いずれにせよ,この掲示板でご教示下さった方々の情報はきわめて詳細かつ正確で本当に役に立ちました.改めて御礼申し上げる次第です.
Q:ビオラ楽器購入
投稿者:びよりすと 投稿日時:2005/09/18 19:20 ---251.2.248
はじめまして。私は大学のオケに所属し、ビオラを演奏しています。そろそろ楽器を購入しようと考えています。弦楽器はオールドの方が良い楽器ということでオールドがいいかなと思っているのですが、予算の問題がありまして・・・。予算30万くらいのビオラでしたら、オールドと新しいものとどちらがよいでしょうか??というか30万のオールドってあるんでしょうか(汗
投稿者:かめ 投稿日時:2005/09/18 19:37 ---196.107.130
>30万のオールドってあるんでしょうか
残念ながら、30万円ならオールドどころか新作の購入も
かなり限られてしまうと思います。
ただし、大学のオケに所属していると言うことなので、
大学の先輩などから30万で譲ってもらうという手は
あるかもしれません。
投稿者:いし 投稿日時:2005/09/18 22:44 ---10.195.31
ヴィオラはチェロ以上に選択肢が少ない楽器なので、中古(この価格帯ならUsedでOldはありません)か新品か、製作された国、サイズ、といったことにこだわらず、予算の範囲内の楽器を片端から試奏して選んでください。
まだ購入されていないのなら、弓についても同じです。こちらも予算に幅を持たせて、いろいろと試してください。
かめさんの仰るとおり、「オケの先輩から譲ってもらう」というのは一番経済的かもしれません。「量産メーカーの上級機種」を使っていた人は、下取りに出すと「量産品」ということで買い叩かれる(もしくは買い取り拒否の)ため、とりあえずセカンド楽器として持っていることがあります。こういった楽器を譲ってもらえれば良品が格安で入手できると思います。
投稿者:かめ 投稿日時:2005/09/19 07:41 ---196.107.130
ヴィオラの購入を考えていらっしゃるのなら、楽器の選択の際に
楽器の大きさにも注目してくださいね。
量産品のヴィオラだと、どうしても小さめのサイズの物が多いの
ですが、できれば40.5cm以上くらいの大きさの物を
選んだ方が、ヴィオラのふくよかな音色を楽しむことができると
思います。
ちなみに、私のヴィオラは41.8cmともう少し大型です。
投稿者:いし 投稿日時:2005/09/19 09:03 ---217.37.202
胴長のヴィオラのほうが低音が豊かなものが多いとは思いますが、胴厚にもかなり差があります。作りの良し悪しでも低音の出は違いますから、胴長だけを重視することはないようにして下さい。
私が最初のヴィオラを購入したときは15万円前後のものを試しましたが、410mm前後でも低音が物足りないものがあり、結局395mmのものを選びました。少しでも選択肢を多くするという意味で400mm以下の楽器も試してみてください。
ただ当初は「良い音だけど今の楽器より大きいので弾きにくい」と思っても、これは想像以上に簡単に慣れます。
私が後で楽器をアップグレードしたときは420mmのものにしたので、店頭で弾いているときはかなり難しいかと思いましたが、1週間もしないうちに慣れてしまいました。
「大きいから弾けないだろう」という理由でせっかくの良品を逃さないように気をつけてください。
投稿者:びよりすと 投稿日時:2005/09/19 11:31 ---90.7.130
かめさん、いしさん、さっそくお返事していただいてありがとうございました!!!!
楽器のサイズによってもだいぶ差があるんですね。400mm以下にしようかと考えていましたが、やっぱり大きい楽器も試奏してみようと思います。先輩から譲っていただくのはちょっと厳しいですので、いろいろお店を回ってみようと思います!!
かめさん、いしさんのアドバイスとても参考になりました。本当にありがとうございました。
Q:ヘフナーについて
投稿者:ドイツ製品好き 投稿日時:2005/09/18 19:09 ---167.167.144
ヘフナーのバイオリンの購入を検討していますが、
#167, #201, #203のどれにするか迷っています。
何かアドヴァイスをお願いします。
#203は裏板一枚とありますが、これの効果はどのようなものでしょうか。
投稿者:クロ 投稿日時:2005/09/18 21:55 ---189.79.51
こんばんは、ドイツ製品好きさん。
<#167, #201, #203のどれにするか迷っています。>との事ですが、
最終的には自分の好みによるんではないでしょうか。
単純に考えて、値段が高いものの方が作りが丁寧です。
ヘフナーは量生産品ですが、元は木で出来ているので、同じ品番でも差があると言う事もあると思います。
買う事になれば、同じ品番で2〜3本用意してもらい、引き比べをした方がいいと思います。
その中から自分が気に入ったものを選べばいいのではないでしょうか。
ヘフナーではないのですが、同じ量生産メーカーでは
「当たり」と「はずれ」の差がかなりありました。
同じ値段ならば、「当たり」を買ったほうが勿論得です。
裏板一枚の効果は、私は「響き」だと思っています。
二枚と一枚では、やっぱり弾いた感じの響きが違うように感じます。
一枚の方が高級感がありますが、その高級感に捕らわれない事も大切です。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/09/18 23:25 ---6.34.149
カタログを見ればわかるように、ヘフナーのグレードとしては、#167はオーケストラ, #201, #203はコンサートと違うグレードに属し、コンサートグレードから、分業でしょうが職人によるハンドメイドという言葉が使われるようになります。
持った時の満足度からすれば、 #201, #203が買える予算があるならそちらにすればよいのでは。私の楽器は「ハンドメイド」と言えますよ。
ターゲットの楽器のグレードからみると、まだ弾いただけではすぐに楽器の違いは分からない腕である可能性が高いと思われますが、それでもクロさんがおっしゃる通り、同じ品番でも何台か弾き比べ、一番しっくりくるものを選ぶのがよいでしょう。(先生や本当に上手で楽器が分かる知人がいれば、一緒に選びにいってもらうことをおすすめします。)
よく知られたメーカの量産品ですので、最低限の品質は確保されていると思いますが、中には合格すれすれのものもあれば、大当たりのものもあります。
また指板の削り方、駒の削り方、魂柱の立て方、ペグの擦り合わせなども、当たり外れの組み合わせという感じになりますので、まんべんなくある程度の水準を満たしたものを選んだ方が、後々いらぬ調整費用がかからずにすみます。
一枚板を選ぶかどうかは、デザイン的に一枚板が好きで、少し余分なお金を出してでも一枚板を持った方が満足度が高いのかどうか、で決めればよいのではないですか。音は一枚板でも二枚板でも変わらないという意見が一般的だと思います。
私は何台か楽器をもっていますが、結果的に一枚板のものが多く残っています。個人の趣向として若干一枚板をデザイン的に好む傾向があるものの、デザイン重視で選んだのではなく、音と楽器の作り重視で選んだ結果です。しかし一枚板=良い音とは思っておらず、主たる原因は、一枚板で虎杢もきれいに出ている欧州材は貴重かつ少し高価であり、そのようなものを使って作られる楽器は、丁寧にきちんと気合いを入れて作られる可能性が高いため結果的にはずれの楽器が少ないし、演奏者も大事に使うので状態もよいということ、ではないかと理解しています。
投稿者:ドイツ製品好き 投稿日時:2005/09/19 00:41 ---167.167.144
クロさん、弦喜さんお返事ありがとうございます。
良く調べてみたら、#A100も、なんとか手が届くことが分かりました。
#203(裏板1枚)204,750円と
#A100 236,250円 の一騎打ちになりそうです。
裏板1枚にこだわるなら#203、そうでないのなら#A100といったところでしょうか。
#A100は、オーケストラ、コンサート、マスターヴァイオリンの
どの分類になるのでしょうか。
情報不足で困っておりますが、よろしくお願いします。
最終的には、ショールームで試し弾きさせていただき、
購入する予定です。

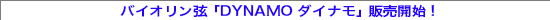
Q:ヴァイオリンの大きさ
投稿者:あり 投稿日時:2005/09/19 11:02 ---66.101.168
ヴァイオリンのサイズは355mmが一般的だと思うのですが、もう少し大きい360mmくらいの楽器もありますよね。
過去ログを検索したところ、ストラッドさんではサイズにこだわっていらっしゃるようですが、大きい楽器だと何か問題があるのでしょうか。
投稿者:M 投稿日時:2005/09/19 16:18 ---15.206.247
355mm誤差3に名器が多いだけの話じゃ。
投稿者:ストラッド店員 投稿日時:2005/09/21 16:29 ---39.18.213
こんにちは、
サイズについては下記ページをご参照下さい。
http://www.strad.co.jp/navi/point7a.html
>大きい楽器だと何か問題があるのでしょうか。
これといった問題はないと思います。
コラムのページはかなりシビアな数値ですが、360ミリは許容範囲だと思います。古いフランスの楽器などは比較的大きめで360ミリを超えるサイズのものをよくみます。
確かに名器と言われて楽器は355mm誤差3に収まっている事が多いですね。それでは!
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/09/21 20:28 ---6.35.206
以下、私見です。
ストラッドさんのコラムで、重要な順にA,B,Cと書かれている項目ですが、私はC,B,Aの順ではないかと思っています。
駒を立てる位置は、Bのストップ位置に完全に合わせる必要はないため、Bがよっぽど狂っていない限り、C:ボディー上端から駒位置までの距離=2:3となる位置に駒を立てれば、弦の長さの関係はほぼ同じになります。どの楽器でも同じような指間隔で弾くためにはこの条件が重要です。
一方Cの長さを変えるためには、ネックを外して改造をする必要があります。
ボディーサイズの5ミリの違いは、ボディーの厚みの違い、C字のくぼみ方の違い、肩の部分の形状の違い、顎当ての違い、などと比べて大きな違和感を感じる材料とはならないように思います。
投稿者:てつ 投稿日時:2005/09/22 07:11 ---168.167.64
個人的には、大きい楽器の音色的はビオラに近く、どちらかと言えば太い音になるように思います。音量はあると思いますが。。。。
バイオリンらしい音と言った時、どちらかと言えばシャープさがあるべきなのでしょうね。その辺のバランスがいいのが355mmというサイズなのかもしれません。
ただ、そのサイズをはずれたからと言って、良い楽器が沢山あるのも事実ですね。一般的に、我々は名器など手にいれることはありませんし。
投稿者:ks 投稿日時:2005/09/22 08:28 ---98.106.243
この問題は私も興味を持ちましてご教示いただきました。弦喜様が言われるように私もCの寸法が重要だと思います。私の持っている楽器もCの寸法は全て130ミリですしかしf字孔の下部の位置が190ミリから195ミリまでバラツイています。何故製作者がこんな決まりごとを知らないとは思えませんのでこんな作りにするのか疑問です。いま私は全て195ミリにしています。全長については360ミリのものもありますがあまり違和感はありません。参考までに。
投稿者:あり 投稿日時:2005/09/22 12:23 ---121.92.149
皆様のご意見、大変参考になりました。
サイズについてのページもわかりやすくて勉強になりました。
ありがとうございました。