弦楽器 Q&A
弦楽器に関するいろいろな疑問にお答えします。
2023年12月31日をもちまして、新規投稿・コメントの書き込みを終了させていただきました。
5203件のQ&Aがあります。
Q:イギリスの新作弓
投稿者:jorio 投稿日時:2005/08/15 23:30 ---86.125.206
ヴァイオリン弓のグレードアップを考えています。(現在は国内メーカーのスチューデントクラスのもの使用)そこで候補として色々と調べてみたのですが、イギリスの新作弓には現在どのような評価が与えられているのでしょうか。かつてのヒル商会プロデュースのオールド弓が高い評価を得ていますが、現在のイギリスでの工房、個人作家製作の新作で性能が良く、日本でも入手可能な弓では、どのようなものがありますでしょうか。ご教示願えれば幸いです。
投稿者:ストラッド店員 投稿日時:2005/08/17 15:16 ---171.127.5
こんにちは、
ヒル商会亡き後、ヒル商会で働いていた職人たちは独立した方もいらっしゃったようですが、現在も製作しているかどうかは未確認です。ごめんなさい、あまりよく解りません。
どなたか解る方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。それでは!
Q:バイオリンの材料は現在ではどこの国」の材料でしようか
投稿者:ks 投稿日時:2005/08/17 14:22 ---98.106.243
バイオリンの音質は材料につきるとおもっております。日本の製作者はどこの国の材料で作っているのでしょうか、製作者をしりませんのでおしえてください。現在バイオリンの製作技術は過去のクレモナにひってきするとおもいますので材料が全てとおもいます。あとは年代経過しかないとおもいます。ご教授ください。
投稿者:rio 投稿日時:2005/08/17 14:56 ---9.121.163
私が信頼している東京に工房を持つG氏は、スプールスとメープルについてはイタリー、中国、北米の材料を使っています。
バヨリンの楽器としての資質は
1.製作者の技量
2.素材
できまり
その楽器が生きるか死ぬかは
1.弾き手との相性
2.弾き手の楽器管理能力
3.弾き手と相性の良いかかりつけの工房の存在
にあると思います
Q:分数楽器の買い替えについて
投稿者:T 投稿日時:2005/08/16 21:02 ---113.222.60
子供の分数ヴァイオリンの買い替えで、悩んでいます。今、国産の10分の1の、グレードの低い楽器を、弦を張り替えて、使用していますが、コンクールで優勝して(もちろん幼児部門ですが)、レッスン曲もコンチェルトを始めて、音量や表現力が、今の楽器では限界があるから、1サイズアップして、価格ももう少し、高い楽器を使用する方が良いと言われました。もし、買い換えることによって、子供が弾きやすく感じてくれれば、と思って、グレードアップするつもりで、何件かヴァイオリンショップに問い合わせましたが、まだ、楽器が小さいから、グレードを変えたところで、さほど違いが無く、今と同じように、国産の楽器を改良すれば充分とか、今後の為に予算を残す方が良いと薦められたりします。1店だけ、工場生産の分数楽器よりは、少し金額を上乗せして、中国の手工品を購入した方が良いと勧めてくださったのですが、どうなのでしょうか?ちなみにオールドを購入するのは、予算的にためらっています。最終的に決められなければ、先生も探して下さるそうですが、私の方でもいろいろ勉強しておこうと思って、質問させて頂きました。アドバイス、よろしくお願い致します。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/08/17 02:29 ---6.35.166
1/8以下は本当に選択肢が少ないですね。
お子様がかなり弾けるのであれば、いっしょに何店か楽器店に行き、実際にお店のおすすめの楽器をお子様に弾かせてみれば、ある程度答えは見えてくると思います。
「これが好き」という楽器が出てくるでしょうし、お子様が弾くその楽器の音を客観にきいて、音量や音色含めて、親御さんも「これいいかも」と思った時、それが出会いだと思います。聞くのではなく、聴く/弾くのです。
同じメーカーの同じ型番でも、当たり外れはあります。
これが1/4になると、量産楽器の中でも格段に選択肢が増えますし、また古い楽器も見つかりやすくなります。楽器店で試奏して決めるというのが基本となるとは思いますが、Yahooオークションなどで、1/4の古い楽器何点かのレンタル権が出品されているので、短期間しか使わないと考えるのでしたら、そのようなものや一部の楽器店で行っているレンタル品を借りるのも手です。
中国製の分数楽器ですが、最近バッハのピッコロヴァイオリンパート演奏のため、自分用に上記オークションの1/4サイズのものを3万円程度で入手しました。外観も綺麗ですし、見た目より音量もあり、悪くないなと思いました。(豊かな低音を望む事は所詮無理なので、そこは割り引いて、全体的な鳴りからの判断です。)
中国の楽器を多数扱い試奏も歓迎という業者の出品ですので、そういうところに連絡した上で、直接出向くか楽器を借りて試奏して決めるのも一つの手です。(1/8などもあります。)
1/8では、値段の高いものを探す方が困難ですので、値段に惑わされず、お子様が弾きやすく好きで、また音量・音色に満足できるものをまず選び、できれはそれを借り持参するか、お店に来ていただくかして、先生に意見をきいた上で、最終判断すればよいのではないでしょうか。
投稿者:T 投稿日時:2005/08/17 14:37 ---113.222.60
弦喜さん、ありがとうございました。なんとなく、工房やヴァイオリンショップは、敷居が高く思えて、行きづらかったのですが、下調べをして、子供と一緒に訪れて探してみます。この先、何度も買い替えがあるのを、覚悟してましたが、サイズが大きくなるに連れ、選択肢が増えるということ、いろいろなヴァイオリンに出会えるのが、楽しみになって来ました。
Q:弦
投稿者:rika 投稿日時:2005/08/14 09:29 ---97.143.53
今オブリガードを使用していますが、次は違う弦を試してみたいと考えています。ドミナントは私の楽器には合わないようですぐに辞めてしまいました。
このサイトでのおすすめのヴィジョン系の弦について3種類の違いなど感想を教えていただきたいです。
またどんなタイプの楽器に合うのか教えてください。
投稿者:ストラッド店員 投稿日時:2005/08/16 14:56 ---144.180.226
こんにちは、
弦の種類の交換は冒険ですよね、、
張ってみないと解らないのが弦です。(楽器との相性、奏者の好み等)
普通のビジョンですが、私の張ってみた感想ではメーカーの説明通り、「ドミナント」の雑音部分を軽減した感じでした。私の使っていた楽器では、優しい音がしました。ただドミナントと似ているといえば似てるので、ドミナントが合わない楽器の場合はかなりの冒険になると思います。
Vision Titaniumは最初張った時に、「この楽器こんなに大きな音がするんだ!」と素直に思いました。けして嫌な音の大きさではなくすっきりした感じの音でした。
Vision Titanium orchestraですが、すいませんこれはまだ使用しておりません。現在使用しているビオリーノ結構私の好みの弦なので、この弦が劣化したら変える予定でおります。それでは!
Q:バイオリンの音質はなにが一番利くのでしょうか
投稿者:ks 投稿日時:2005/08/15 00:44 ---98.106.243
こんなことが簡単にわかるわけではないですが一般論のご意見をご教授ください。私は最初裏板の木目がきれいにあるものが良い音のするものと思っていました、現実にある製作家は値段が違いました。最近裏板は土台であって木目には何も関係がないことをしりました。しかしストラデバリの名器の写真をみると素晴らしい木目ありますよね。もし同じ製作者ならニス、作りは同じレベルと考えた場合表板の材質が一番音質に影響するのでしょうか、ご教授ください。
投稿者:かめ 投稿日時:2005/08/15 01:30 ---196.107.130
おっしゃるとおり、表板の材質が一番音質に影響します。
極端な話、新作の工場製楽器の表板だけ、オールドの物に
替えると、全く別の、オールドの音になります。
もしも同じ製作者の楽器を数台見比べて、そのうちの1本を
購入する立場になったのなら、表板を丹念に見比べて一番材料の
良い表板を使った楽器を選べば間違いないと思います。
投稿者:セイジ 投稿日時:2005/08/15 02:27 ---151.3.240
知人の製作者から聞いた話では、虎杢のような木目の
模様は、音にはあまり関係ないらしいです。
しかし、見た目重視のお客さんもいるので、そういうリクエスト
がある場合は、音が良くなるわけではないけれども
木目の見栄えの良い(値段が高い)材料を使うそうです。
楽器の値段の相違は、材料費の違いによるものと言えるでしょう。
表板の材料も作家によって好みが違うようで、
ガルネリは樹脂のしみが入った材料を使ったという
話を聞いたことがあります。その材料で作った楽器の評判が
いいことを聞きつけたストラディバリが、ガルネリから
少し分けてもらったとか。見栄えで選ぶとしたら、しみの
ある材料は選外になるでしょうか。
ところで、表板にマスキアート(ハーゼ)が入っている材は
よいという人と、音には関係ないという人がいますが
実際はどうなんでしょう?
下記のようなPRをしているところもありますが、見栄えで
考えると、マスキアートはない方が無難でしょうか。
>マスキアートとは木目とは関係なく材料に 蚯蚓腫れの様な
>筋が入っているもので外観も 美しく硬いのが特徴、削出す
>前の木材その物を叩いても "カーン、カーン"と鐘の様に音
>色が通る弦楽器製作に 最上の材料です。
投稿者:かめ 投稿日時:2005/08/15 08:59 ---196.107.130
マスキアートが音に関係するかどうかは、その人それぞれだと思います。
ヴァイオリンの材料として上質な物は、木目が深く均一でまっすぐそろっている物のようです。木目は広すぎても狭すぎてもいけません。
このような材料にマスキアートが入ると、縦方向の木目に対して
横方向への筋が加わるので材料の強度がより強くなります。
強度が強くなると言うことは、より板を薄く削ることができるということです。薄くなれば板の振動特性が高まりますので、音量
が増すなどの効果が考えられます。
ただ、材料は硬ければ硬いほど良いわけではなく、ほどよい硬さと繊維の粘りの強さ(結局、板が自由に振動できる範囲での硬さ)が必要です。そのような材料は、マスキアートがあろうが
なかろうが、高価です。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/08/15 10:39 ---6.35.103
>裏板の木目がきれいにあるものが良い音のするもの
これは、間接的には正しいでしょう。
製作側の気持ちや値付けを考えると、美しい虎杢の材料は普通はとっておきの楽器に使われます。従って、他の材料もよいものを使い、また製作・仕上げも丁寧に行われる可能性が高い。また使う側としてもできるだけ傷つけないように大事にするので、よいコンディションが保たれます。
ヴァイオリンは、当初物乞いや旅芸人の楽器として扱われ、一方上級階層が使っていたヴィオラ・ダ・ガンバなどは装飾が施された実に美しいものでした。ヴァイオリンにおいても、美しい虎杢を備え象嵌や絵付けも含めた美しい外観の楽器を作ることは、時代の要求で大きな音が求められる追い風に乗って、宮廷・上流階級で楽器として認めてもらうためには必須条件だったと思います。
完全に私見ですが、ストラディヴァリ工房でも、宮廷から依頼された楽器と、近所の子供のために頼まれた楽器では、材料も値段も大きく違っていたと思います。また仕上げにかける時間や気の配り様(もしかしたら誰が作るかも含め)も違ったでしょう。素杢の材料などは、有名になる前の貧乏な頃と、上記安価な楽器を発注された時に使ったのではないかと想像します。
これも私見ですが、裏板において、木の堅さ/密度だけでなく、杢ではない本当の木目(表板と同じく縦方向に入ったもの)は意味を持つように思います。繊維を分断しない板取りのものの方がなんとなく素直に音が響きそうだし、またよく響く裏板を選ぶためのヒントになっているように思います。(これについては、まだ自分なりの結論は持っていません。)
私は、底鳴りというのか、裏板側からしっかり音が放射される楽器を好んでおり、またそのような楽器がホールを駆動できるものと思っていますので、裏板も楽器の音を決める非常に重要なファクターだと認識しています。
投稿者:ざむぱ 投稿日時:2005/08/15 15:25 ---166.28.208
たしかに裏板も重要だと思います。
表板がしっかり振動するためにはしっかりした裏板が必要ですよね。
だからこそメイプルのような硬い木を使うのでしょう。
ギターでも裏がメイプルというのは珍しくありませんし、やはりそれらのような硬い木を使います。
昔、裏と横を黒檀で作ったギターがあったそうですが音は良かったようです。
もちろん硬さだけあればいいというわけではないでしょうが…
バイオリンではメイプル以外ではポプラとカーボンファイバーぐらいしか知りませんが、特殊な材を使ったものも見てみたいです。
投稿者:ks 投稿日時:2005/08/15 16:23 ---98.106.243
大変参考になりました。ありがとうございました。裏板の木目がきれいな楽器は表板の材質も良いモノを使っているのですねだから同じ製作者だったら木目がきれいな楽器のほうが高いのですね。昔ある製作者は木目のうすい楽器の3倍ぐらいの価格差がありました。ストラデバリも裏板のきれいな楽器が大事され多く残っているのですね。でも自分の楽器は木目のきれいな楽器のほうが鳴りますね、裏板の木目の一つ一つが振動するようにかんじます。
投稿者:セイジ 投稿日時:2005/08/15 20:06 ---151.3.240
>かめ さま
マスキアートの件、ご教示ありがとうございました。
誤解がないよう補足しておきますが
知人の製作者はXXXクラス(音響的には最上)の材料を使うそうです。
しかし、その上にもう一つ上級のランクがあって、それが木目の見栄
えのよいものなのだそうです。値段は高くなりますが、音質的には
XXXと変わらないと言ってました。木目の綺麗な材料が高級素材で
あることは間違いないです。
投稿者:ほけけ 投稿日時:2005/08/15 23:51 ---150.185.38
表板のハーゼの話が出たのでつい質問してみたくなりました。
あれは天然のバスバーと呼ばれるものですよね。
ハーゼではなくて、波打ち際の波模様みたいなのが表板に
入っているのを時々見かけますが殆どと言って良い位、
そのような模様のある楽器は音が良いのを思い出しました。
表板の波模様みたいなのは特別な呼び名があるのでしょうか?
Q:コントラバスについて教えてください
投稿者:makky 投稿日時:2005/08/05 01:24 ---52.116.128
こちらには3度目の質問になります。
前回は息子のバイオリン購入にあたってアドバイスいただきとても助かりました。お蔭様で素敵な完全手工品バイオリンを購入できました。
今回は長女のコントラバスの購入に備えて、いろいろ教えてください。
高1の長女は中学からコントラバスを始め、高校になって音楽の道を考え始めました。今は、学校から部活を終えて帰るとピアノの練習さえもままならない日々ですが、いずれコントラバスでその道に進むのであれば買ってあげなくてはと思っています。お世話になっている先生からは、大学に入って自分で聞き分けられる技術と音ができてから買えばいい。とも言われていますが、家でも練習なければならない日はそう遠くなくやってくるでしょうから、買うだけの準備はお金だけではなくしたおかなければというところです。
どのような視点で楽器を選んでいったらよいのか、本当に初心者向けの基本的なところを教えてください。
また、大体のお値段の相場も教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
投稿者:いし 投稿日時:2005/08/05 22:07 ---159.48.67
他の弦楽器と同様に、「表板・裏板ともに単板削り出し」を選ぶ際の最低条件とすれば、中国製や東欧製の30万前後からがそれなりの製品とは思います。ただ、趣味であればこれで良いかもしれませんが、音大からプロを目指すとなると、どうしても「完全手工品」が欲しくなることと思います。そうなると何百万円レベルにはなるでしょう。
ところで、今は学校の楽器をメインに使っていると察しますが、この楽器はきちんとした楽器なのでしょうか。何年も調整に出さず、弦は切れたときのみ交換、などというコントラバスがおいてある学校は少なくありません。もしそうであれば、自己負担になってでも、新品の弦(2万円くらい)に交換したり、点検・調整をお願いしてみて、良い状態の楽器にして練習するというのも一案と思います。
先生の仰るように「楽器は大学に入ってから」、というのであれば弓だけ先に買っておくことをおすすめします。手元のカタログで見る限り、コントラバス用の新作弓は高級品でも30万円台です。同じ30万円なら買い換え前提で練習用楽器を買うよりも、上質の弓を入手する方が経済的ですし、良い弓だと上達も早いといわれていますから。
投稿者:makky 投稿日時:2005/08/05 23:44 ---52.116.128
早速のアドバイスをありがとうございます。
弓は中学ではじめた時に16万程度のものを買いました。値段の割りにバランスもよく腰も強いようで、本人は気に入っています。
学校の楽器はご指摘の通り、調整は定期点検的にしているらしいのですが、弦はそれほど気にされていないようです。
・・・うーーん。やっぱり高価ですねえ、完全手工品・・・
よい情報がありましたらまた教えてください。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/08/06 07:35 ---6.35.118
>高校になって音楽の道を考え始めました
>学校から部活を終えて帰るとピアノの練習さえもままならない日々
>お世話になっている先生からは
と書かれていますが、現状がよくわかりません。
音楽の道ということは、コントラバスで音大を目指すということを意味するのでしょうか。
そうであれば、コントラバスのプロの先生に師事してレッスンを行っているのではないかと思うのですが、上記表現からは単に高校のクラブに入っているだけのようにも見えます。
また、お世話になっている先生が、学校の先生かコントラバスの先生(プロの楽団で演奏している方)かがわかりません。
アマオケ関係ではありますが、コントラバスを購入している友人たちを見ると、個人的に師事しているコントラバスの先生のお下がりの楽器や斡旋の楽器(楽器屋経由だけでなく先生のコントラバス仲間のお下がり含む)を購入していますので、コントラバスの世界での楽器入手は選択肢が少ない故に、ヴァイオリン以上に師弟間で行っているのだとかってに解釈しています(私見です)。
投稿者:makky 投稿日時:2005/08/14 11:44 ---52.116.128
いつも、弦喜 さんのコメントを楽しみにしていました。私の書き込みにもコメントをいただけてうれしいです。
さて、娘ですが、プロの方(楽団で現役演奏していらっしゃる方)にこの春から見ていただいています。(学校のクラブのコーチの先生から紹介していただきました)ピアノやソルフェージュ、楽典等の基礎は大分やっていますので、(もう少しがんばってほしいという親の気持ちは別にして)そこそこ大丈夫かな?というところです。コントラバスという楽器を専攻して受験した場合殿程度の演奏力が必要なのか、あまりメジャーではないだけに把握し切れていないのでこれから研究の余地ありです。
まだ、高校1年生・・・・でも、音大受験となるともう高校1年生・・・とにかく情報がほしい昨今です。
*コントラバスの世界での楽器入手は選択肢が少ない故に、ヴァイオリン以上に師弟間で行っているのだとかってに解釈しています(私見です)。
この情報、とてもありがたいです。
またよろしくお願いいたします。
Q:指板は着色する?
投稿者:作ってみたい 投稿日時:2005/08/04 07:00 ---110.60.168
専門知識の豊富な方ばかりが意見を交換するサイトに、私のよう
な浅薄な者が投稿していいのか迷いましたが、笑いながらお教え
頂ければありがたいところです。
●黒檀を使うパーツ、例えば指板は本当に真っ黒ですが、木材と
しての黒檀であのような色は見たことがありません。つまり黒
で着色しているのではないかと推測するのですが、どうなので
しょうか。ただ、使っているうちに凹凸が出たら表面を削ると
いうことは・・・つまり削っても出てくるものは真っ黒という
ことになります。ということは、やはり私の見たことのある黒
檀が安物ばかりなので真っ黒ではない、こういうなのでしょう
か。
投稿者:あ 投稿日時:2005/08/04 08:10 ---23.216.123
とりあえず書きます。答えになると良いのですが・・・
黒檀はホントに黒いです。削っても黒、粉も黒です。
「真黒」とも呼ばれています。
ただ黒檀の種類や育った環境、産地によって
削った直後は濃い茶色や紫がかった濃い茶色で
しばらくすると黒く変わっていく物もあります。
もちろん濃い茶色のままの物もあります。
現在真黒は非常に少なく高価です。(ただその気になれば
バイオリン用ならいくらでも入手できます。)
均質できめの細かい黒檀であれば少々色の薄いものを
染めて使用しても問題ないと思いますが、
縞黒檀のように硬いところと柔らかいところが
交互にあるような材はやめた方が無難。
真っ黒でないものが安物とまでは言いませんが、
真黒との間には2−3倍の値段の差があります。
楽器の調整のついでに職人さんから端材などを
もらってきて観察してみてはいかがでしょうか?
投稿者:作ってみたい 投稿日時:2005/08/04 09:47 ---110.60.168
早々に回答を頂きありがとうございます。真っ黒の物がきちんと
あるのですね。バイオリンの指板の混じりけのない黒を見て、つ
いつい塗装を思い浮かべてしまいました。ところで、もしも真っ
黒の材料が入手できない場合(きっと捻出できる金額次第なのでしょうが)、染色材としてはどんな物が一般的なのかお分かりになりますか?重ねての質問で恐縮です。
投稿者:とらを 投稿日時:2005/08/04 14:55 ---100.19.68
指板は、バイオリンの製作材料を扱うネットショップで、1,300円(Avec Violon)から3,000円(ミネハラ)程度で販売されていますが、ご存じでしょうか?
または、予算的にいかがでしょうか?
(品質的には、指板用として販売されているので、問題ないと思いますが・・)
黒檀以外の安い材料は堅さが足らず、すり減る度合いが大きく、削り直し、染色の手間、などを考えると、結局、高く付く可能性があります。
※括弧内のショップ名で検索してご確認下さい。
また、「バイオリン 製作材料 指板」でも、製作に関する情報サイトも多数ヒットします。
投稿者:ほげげ 投稿日時:2005/08/14 06:01 ---4.36.122
フェルナンブーコと黒檀は似ていて中心部分と外側の色が分かれている2層構造みたくなっていたと思います。
フェルナンブーコは以前パリ在住の笹野さんが
楽器フェアで断面を展示していました。
黒檀の中心部分は黒ですが外側に近くなると
茶色と混ざったマーブル状態になります。
そのような材の指板の場合、あまり酷くない場合、
オイルで黒光させます。染色材は使いません。
マーブル状態が酷い場合、黒檀の黒い粉と接着剤を
混ぜ込んだものを表面に付着させて自然な黒に仕上げます。
割れも同様な方法で埋めます。
仕上げはやはりオイルで黒光させます。
ただ、指板は削って行くものなのであまり酷いのは交換します。
Q:イタリア製じつは中国製のバイオリン
投稿者:ks 投稿日時:2005/08/13 02:52 ---98.106.243
イタリア製といわれている楽器のなかでよく実際には中国製だという話を聞きますがそんなことが事実としてあるのでしょうか、またそのような楽器は中国の材質で作ってあるのでしょうか。見分ける方法はあるのでしょうか。変な質問で恐縮ですがご教授ください。
投稿者:フィル 投稿日時:2005/08/13 08:25 ---110.60.193
たぶんホントだと思います。実際に自分の目で見たわけではありませんが、中国でニス塗りを残して白木の状態の物を輸出したり、もっとひどい時にはラベルだけをイタリアで貼るようにしたりすると、何かの本で読んだことがあります。ご存じのように偽ブランド品のメッカと言えば中国ですが、あまり知られていない偽ブランド大国にイタリアがあります。本国で、しかも本物のブランド品の会社でタグだけを作ったりするのですから、たまったものではありません。中国においてもイタリアにおいてもこのような人たちは数としては非常に少数だとは思いますが、犯罪意識の低い人たちがいることもまた事実です。だから・・・「たぶんある」と思うのです。本物と偽物を見分けるには経験ではないでしょうか。ブランドバッグを見分けるのと同じだと考えます。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/08/13 10:18 ---6.34.61
淡々と型通りの一般論を書きます。
ヴァイオリンを、絵画のような芸術作品ではなく、道具・工業製品(手工含む)ととらえた場合、海外から材料・半分完成品を持ち込んで、組み立てあるいは最終仕上げを行い、その国の原産地表示を行って出荷することはごく当たり前の考え(というか上記の作り方をした場合、最終加工をした国を原産地としないと、規格違反となる。)です。
例えば家電の表示規定では原産国は下記のように定められています。
「第8条第1号に規定する「原産国」とは、その家電品に本質的な性質を与えるために充分な、実質的な変更をもたらす製造又は加工を最後に行った国をいう。 」
繊維・靴なども同じで。染色を行ったり、靴を接着したりするとそこが原産国となります。
品質(品格含む)さえ確保できるのであれば、最も人件費・材料費の安いところで、ぎりぎりのところまで作って、仕上げのみブランドイメージの高いところで行い、ユーザにとっては比較的安価で、メーカーにとっては利益のとれる商品
として販売するというのは、事業的な視点で考えるとごく当たり前のことです。
私は規格の専門家でないので、
・すべて海外で作って、ラベルだけ貼るのが上記加工に該当するか?
・本体はすべて海外で作って、残りフィッティングを付加し調整するのが上記最終加工に該当するか?
はわかりません。何となく後者は該当するように思えますが...
詐欺で営業停止にはなりたくないでしょうから、規格の要求範囲内で最終手を入れるのが普通のやりかたでしょう。その範囲であればまっとうな商売とは言えます。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/08/13 10:24 ---6.34.61
↑
誤 半分完成品
正 半完成品
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/08/13 10:53 ---6.34.61
以下、私見です。
中国は広大な国土を持つ国で、北はシベリア、南はベトナム、西はインドなどと接しており、ほとんど熱帯から寒帯までの地域をカバーしています。そこに生息する植物もそれぞれの地域に応じて様々な種類のものがあります。
南洋材が使われているのか、美しいが幅広で杢の浅めのメープルは、中国ヴァイオリンの一つの特徴です。これは典型的な中国楽器の裏板・側板をある程度の数見ればすぐにわかるようになります。(ヤフオクで比較的安価で美しく見える中国楽器が多く出ていますので、写真で目を肥やすのも一つの手です。)。表板側も、典型的なものとしては、夏目と冬目があまりはっきりしないものがあります。
ただし、最近中国の材料だけれども、欧州材と見た目で区別がつかないようなものを見かけるようになってきました。これは、中国の地域毎の木材の特性が研究され、欧州材に非常に似たものが見つけられ、その供給経路ができたからではないかと思います。
私がMade in Italy(/イタリアの地名)を付加する立場なら、プロでもわかりにくい上記欧州材に似たものを使わせるか、欧州材を送るかするでしょう。一目で中国製とわかる材料を使うとは思えません。結果、素人(あるいは目利きではない業者)ではまずわからないでしょう。
投稿者:ks 投稿日時:2005/08/13 14:46 ---98.106.243
大変参考になりご教授ありがとうございました。中国のバイオリン製作技術も進歩しているでしょうから、材質がヨーロッパで半製品で最後にイタリアで完成すればやはりイタリア製なのでしょうね。コストパホーマンスを考えればやはりありうることですね。参考になりました。
投稿者:ほげげ 投稿日時:2005/08/14 05:36 ---4.36.122
10年前でしたら不自由もあったでしょうけれど今は
中国でも欧州材はランク分けされて売られ、自由に買えます。
良いのは結構高値で売られています。
欧州材に似てるのは四川材ですが
見慣れると欧州材との区別がつきます。
時には欧州材をしのぐ性能を出す素晴らしい材ですが
流行便乗の違法伐採で業者が捕まったそうで
将来の流通は楽にならないかも知れません。
その上、中国元:日本円が実質10%ほど変わってしまい
日本での価格は上がると考えられます。
ところで最近はビソロッティーが雲南材を気に入って
結構仕入れたようですね。
既に雲南材も伐採禁止ですがミャンマー側から
調達されているようです。
私はイタリア生まれの製作者の楽器も好きですし、
中国生まれの製作者の楽器も好きです。
当然良く出来た楽器だったらですけれど。
Q:ご質問
投稿者:TA 投稿日時:2005/08/10 02:45 ---62.168.38
TAと申します。
いつも興味深くご拝見しています。
このほど、200年経過ぐらいのオールドチェロを検討しています。
ストラッドさんには、どのようなものがございますでしょうか。
予算かたがたご紹介お願いします。
また、一般的にどの程度の予算と考えられるのでしょうか?
特にイタリアにこだわっていません。
よろしくお願いします。
博学多識なご貴兄のご意見・情報もあれば幸いです。
投稿者:rio 投稿日時:2005/08/10 10:24 ---9.121.163
2年前に、プロオケの方が持つ、100年前のモダンのスカランペラで2300万円でどう?といわれたことがあります。当時のバイオリンだとスカランペラ個人取引600〜800万というイメージがありますので、古いチェロは本数が少ないので、バイオリンの3〜4倍という印象を持っています。
そのとき、同時に打診のあった、バイオリンのオールド ゴフリラは3500万円前後だったと思うので、少し名の知れたオールドのチェロは1億〜1億5千万ぐらいと思ってしまうのですが…
バヨリン弾きなので、想像です。
チェロ弾きの方の、コメントがあると良いですね。
投稿者:rio 投稿日時:2005/08/10 10:25 ---9.121.163
(追記です)
上記はあくまで、個人取引の値段で、楽器店経由だともっと高いと思います。
投稿者:CABIN 投稿日時:2005/08/10 13:03 ---114.112.42
超有名でない,名の知れた製作家であれば数千万円クラスでしょうね。
製作家の特定ができないもの,著名でないものはキリ〜数百万円代で購入できるかと思います。
ちなみに私のチェロは1700年代・作者不明・ベニスとかフランスだろうとは言われておりますが,1千万円を甚だしく下回っております。
先日も200年程前の作者不明・シュタイナー型のチェロを試奏しましたが,ウーンでした。(値段聞かなかったけど高くはないだろな〜)
どの程度のチェロを購入されるかが分かりかねますので,とりあえずこの程度で....
投稿者:TA 投稿日時:2005/08/10 17:49 ---165.185.102
rioさん、CABINさん早速の情報ありがとうございます。
ちなみにCABINのチェロは1千万円を甚だしくとはどの位かさしつかえなければ教えていただけませんか。
現在検討中のものは、イギリスの名のある(名鑑に載っているという意味)ものです。220年物ですが。
どの程度の相場かわからないのでよろしくアドバイスいただきたいです。
音量は、イタリアの新作以上で、音色はオールドぽいです。
投稿者:CABIN 投稿日時:2005/08/10 18:54 ---114.112.42
私のチェロは色々な方の手を経て私の手元に来たので,買値は云えませんスミマセン。
ところで,ご存知であれは申し訳ありませんが,MaestronetのPrice Historyもある程度参考になるかもしれませんね。
http://www.maestronet.com/history/makers_list.cfm?ID=4
例えば,Banks, Benjamin(英国)のチェロ(1700年代後半)は,オークションで$35,650のものと$9,480(これはラベルものでしょうか?)と表示されてます。
私は読解力がないので高い方が真作なのかどうか読み取れませんが...
過去ログを見るとBanks, Benjaminのチェロはストラッドさまでも取り扱われていたようですので....
投稿者:おせっかい 投稿日時:2005/08/11 03:02 ---2.9.182
Benjamin Banks は2人居ます。
いずれも欧州ではチェロが大体800万円前後ですから、状態が悪くない限り日本では1000万はするでしょう。
投稿者:TA 投稿日時:2005/08/11 04:11 ---117.45.93
CABINさん、おせっかいさん 有難うございます。
プライスヒストリに、おめあての人がチェロにいなく、バイオリンに載ってました。オークションプライス2000ドル程度でした。
ここの価格と市場価格はどのような関係かご存知の方教えてください。目安にはなるかなと思います。
よろしく。
投稿者:rio 投稿日時:2005/08/11 09:28 ---29.242.228
>ここの価格と市場価格
何年の情報か(1999年か1995年か)
Authenticityは?(by とか attributed to とか)
Sale Type は?
で変わります
製作者銘も関係あります。当時人気があるかないか、今人気があるかないか…
例えば、Scarampella のVn
今、真作で状態のいいものを日本の楽器屋さんで買えば$100,000-はすると思います。
これが参照されたDATA BASE を見ると
1995/5/21 $10,902- Auction (ascribed to)
1995/5/22 $12,791- Auction (Attributed to) Hammaの証明書付
1996/5/19 $42,228- Auction Sale (by) Bearの証明書付
1998/1/1 $65,000-$90,000 retail 価格
2002/5/30 $59,750 Auction Sale (by)
という風にバヨリンで 1.1倍〜10倍です
これを バヨリン → チェロに 価格変換するので
より目安が広がります。
製作者名あるいは製作会社名と製作年、楽器の真贋の程度を挙げれば、具体的な意見が出てくる可能性が高いですが、TAさんのこれまでの情報ではここらが限界かも…
参考までに、私は1920年以前の楽器のエチケットの情報は、99.99%信用していません。楽器屋さんの見立てあるいは添付された写真付証明書の発行者の名前が一番最初の真贋判断基準になります。
投稿者:ストラッド店員 投稿日時:2005/08/11 15:22 ---102.23.246
こんにちは、
200年以上経過したちゃんとしたチェロというのはなかなか日本では、見る経験は少ないですね。非常に貴重だと思います。当店の在庫でも現在は200年越えるチェロはございません。
チェロの場合は200年経過していると、状態がかなり価格に影響してくると思います。同じ作者の場合でもいくら完璧に修理されていても、やはり修理されていない楽器の方が価格は高くなります。それでは!
投稿者:おせっかい 投稿日時:2005/08/12 04:07 ---4.102.25
200年前の製作者がオークションで2000ドルはちょっとありえないような気がします。(ドイツの山中で作られたおんぼろバイオリンを除いての話です。)detail の所にschool of 〜 とか書いてありませんでしたか?
200年前のまともなチェロを購入されるのなら最低でも1000万は必要だと思います。それ以下だと贋物か致命的な欠陥があるはずです。
マエストロネットのオークション価格は余り参考になりませんが、他にネット上で無料で得られる参考資料はこれ以外にあまり無いのであえて無理して書くと、2から3倍程度にすれば市場価格になる場合もあります。それにチェロということでこれも2か3倍にする必要がありますね。まあ、製作者にもよりますけれど。
他に色んなお店のホームページの価格情報からある程度情報は得られますが、市場価格から外れた作品が殆どで写真から形や色を推測するに殆ど贋物ぽいのでさらにあてになりません。
200年前のオールドチェロという情報だけでは、これ以上情報を得るのは無理だと思います。
PS、rioさんの意見は参考になりますね。
投稿者:TA 投稿日時:2005/08/14 00:01 ---62.169.21
皆様、貴重なご意見有難うございます。
※今日旅行から帰宅しました。お礼のご連絡遅れました。
200年以上前のチェロとなるとそれだけでそれ相当の
価格になるという結論ですかね。
イギリスの3大オークションでの買い付けによるものです。
オークションを信用すればまさしく200年以上前のものと
なるようです。
再度検討したいと思います。
投稿者:rio 投稿日時:2005/08/14 02:17 ---29.242.228
>オークションを信用すれば
Authenticity
にご留意ください
それだけです

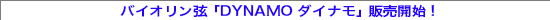
Q:テールピースの傾き
投稿者:YY 投稿日時:2005/08/17 14:12 ---24.233.66
バイオリン本体について質問があります。1ヶ月ほど前に某楽器店で購入したものです。
指板とテールピースが一直線上になくて、つまりエンドピンの位置が中心から若干ずれているらしく、テールピースが傾いているように見えるのです。テールピースの上側が左に傾いているので、E線側が短くなっています。
お店で購入するときには気づきませんでした。同じ型番のものを何点か試奏させてもらい一番音がはっきりしているものを選んだので、その音色的には不満はありません。
これは調整をして少しは改善するものなのでしょうか。それともへたにいじらないほうがよいのか、みなさんのご意見を伺えれば幸いです。こういうことはよくあるのでしょうか。
ちなみに楽器はブルガリアの手工品で定価37万ほどのものです。
投稿者:QB 投稿日時:2005/08/17 14:25 ---9.46.177
まさに「テールピースの傾き」で過去ログ検索すると同じ質問が出てきますが、通常中心線から完全に左右対称は無かろうと思います。
弦はどんなものを使っていますか?
例えばテンション弱めの弦をG~Aに張って、いきなり強いE線を持ってくると、まさにそのような感じになりますよ。
投稿者:YY 投稿日時:2005/08/17 16:19 ---24.233.66
ご回答ありがとうございます。過去ログ読んできました。私の場合と似ているようですね。
今バイオリンについている弦は購入時に張ってあったものです。
確かテールピース側が紫で、ぺグ側の色がそれぞれ違っていたと思います(今仕事場にいるので不確かです)。
初心者なので弦についてはまだよくわかりません。
予算オーバーで無理して買ったものなので、不良品かと落胆していましたが、そうではないということがわかって良かったです。
ありがとうございました。
弦もいろいろあるようなので、交換時には違うものも試してみようと思います。