弦楽器 Q&A
弦楽器に関するいろいろな疑問にお答えします。
2023年12月31日をもちまして、新規投稿・コメントの書き込みを終了させていただきました。
5203件のQ&Aがあります。
Q:駒を変えることのメリット
投稿者:弦二 投稿日時:2005/07/22 07:35 ---107.155.175
こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいています。
ヴァイオリンの駒についてお尋ねします。
AubertとかDespiauなどいろいろ出回っていますよね。
たとえばAubertですと最上のものがDeluxeだったりするわけですが。
たとえば今使っている楽器にはそんなに高くない駒(普及品クラス)が使われている場合に,いきなりAubertのDeluxeとかに取り替えて調整してもらったりすると,音は劇的に変わるものなんでしょうか?
そこまで試したことがないので何ともわからず,投稿した次第であります。ご教示いただけると幸いであります。
投稿者:名無しさん 投稿日時:2005/07/22 08:36 ---57.136.181
私はチェロですが最近駒が折れた際、AubertのDeluxeしました。
たしかに音は変わってます。柔らかい音だけど通る音になりました。
とても気に入ってます。ただしAubertのDeluxeだけじゃなく楽器屋さんの駒を削る腕にもよるとおもいます。それに自分がどんな音が好みなのかちゃんと伝えた方がいいですよ。いきなり「AubertのDeluxeに変えて下さい」なんていったって楽器屋は自分の好みにしか音を作れないですから。
p.s. そのうち魂柱もaubertにかえたいですね。駒をかえた以上に音が変わるはずです。
投稿者:弦二 投稿日時:2005/07/24 21:50 ---107.155.175
削り方にもよるんですね。
いろいろ勉強になります。
機会があったらぜひ試してみようと思います。
ありがとうございました。
Q:表板はなめらかでないとダメですか?
投稿者:まや 投稿日時:2005/07/23 02:20 ---149.210.9
購入を検討しているヴァイオリンがあるのですが
表板が木目のままにデコボコしている部分があります。
見慣れたつるつるすべすべではないのです。
お店でその楽器だけなので不安になってしまったのですが
もしかして特に問題のないことなのでしょうか?
ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿者:セイジ 投稿日時:2005/07/23 02:44 ---151.3.240
表板には、ドイツ語でハーゼ、イタリア語でマスキアートという
木目を横断して走る蝶杢が入った特別なスプルースが使われる場合
があります。
これがあると木目方向に板が割れにくくなるそうで、丈夫な良材
と言われています。この材を使うと蝶杢の部分が多少でこぼこして
仕上がることもあるようなのですが、ご覧になられた楽器が
蝶杢なら、でこぼこは心配ご無用です。
投稿者:cremona2号 投稿日時:2005/07/23 08:16 ---0.157.217
下地を塗る前の仕上げの違いによるものだと思います。
実物見ないと断言は出来ませんが、多分全然問題ないと思います。作者がツルツルだと味気無いと思ってそうしたのでしょう。
投稿者:QB 投稿日時:2005/07/23 08:33 ---37.164.70
ニスの塗り方もあるかと思います。
モラ○○系のようになるべく塗りっぱなしに近いものは、塗る重ねていくうちに、木目のでこぼこが若干強調され気味になりますし、一方ビソ○ッ○○やサン○○のように塗り重ねるたびにニス斑を取っていくやり方だと、平滑な表面になりがちです。
投稿者:あ 投稿日時:2005/07/23 08:36 ---23.216.4
表板の仕上げ段階でスクレーパーを使用すると
一見平らに仕上がった様でも春目(解りやすく
言うと木目の線と線の間)が圧縮されているので
そのままニスを塗ったり染色したりすると春目が
浮き出て表面がデコボコになります。
また、水に浸して固く絞ったウエスで表板を拭いて
春目を起こしてからニス塗りを始めることもあります。
製作家の作品であれば間違いなく意図して出来た
物であり品質にはまったく問題ありません。
(もちろんまともな製作家の作品の場合です)
もちろんつるつるに仕上げる方が手間も時間も
かかりますが、つるつるにした方が音がいいと言う
話しは聞いたことがありません。
まぁ、好みの問題かと・・・
投稿者:猫丸 投稿日時:2005/07/23 11:49 ---4.34.179
表面のカーブが連続していて、なめらかなのが一般的です。
できの悪いバイオリンとの印象を受けますが、見てみないと判断が付きません。
>蝶杢なら、でこぼこは心配ご無用です。
でこぼこにはなりません。
>表板の仕上げ段階でスクレーパーを使用するとーー
スクレーパーを使用したり、カンナでで丁寧に仕上げているのならでこぼこと言う印象にはならないでしょう。
ニスを刷毛で重ねぬりしていくと、刷毛のあとが若干残って、小さなうねりが残りますが、でこぼこという感じには見えません。
新作の楽器でしょうか?
いい加減な削り仕上げに、スプレーの薄いニス仕上げで、でこぼこと言うことも考えられます。
まず、そのお店で、なぜ、でこぼこと感じるのか、質問されたらいかがでしょうか?
そのお店の回答内容を知らせていただければ、みなさんから、もっと的確なご意見を伺えると思います。
投稿者:セイジ 投稿日時:2005/07/23 15:42 ---151.3.240
>>蝶杢なら、でこぼこは心配ご無用です。
>でこぼこにはなりません。
私が所有している楽器の中に、実際にそうなっているものがあります。
でこぼこといっても微妙なもので、ニス面に反射する光沢
の変化で、わずかに凹凸があることが判る程度のことです。
投稿者:かめ 投稿日時:2005/07/23 18:37 ---196.107.130
>表板が木目のままにデコボコしている部分があります。
この文章から判断すると、セイジさんのおっしゃっている蝶杢に
よるでこぼことは違うと思います。
恐らく、縦方向に無数に走っている木目がそのまま浮き上がって
いる塗装のことを言っているのではないでしょうか。
クレモナの有名作者の作品でもわざと木目を浮き上がらせた
塗装をしてある楽器を見たことがあります。
恐らく、「あ」さんのコメントのような楽器なのでしょう。
投稿者:まや 投稿日時:2005/07/23 23:39 ---149.212.170
> クレモナの有名作者の作品でもわざと木目を浮き上がらせた
> 塗装をしてある楽器を見たことがあります。
私が見た楽器もこのタイプだと思います。
楽器屋さんにも「そういう仕上げ」と言われたのですが
何となくつるつるした楽器との優劣を考えてしまい
質問させていただきました。
わかりにくい内容になってしまい申し訳ありません。
ご回答いただいた皆様、本当にありがとうございました。
Q:裏板のヒビについて
投稿者:そら 投稿日時:2005/07/23 21:24 ---11.162.48
はじめまして。
先日、子どもの使用している分数ヴァイオリンの裏板に
ヒビを見つけました。
工房へ持っていってニカワで処置してもらったのですが
それ以来ずっと気になっています。
聞いている分には変わりないように思うのですが
やはり買い換えたほうが良いのでしょうか?
もうすぐコンクールもあるので不安です。
よろしくお願い致します。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/07/23 22:17 ---6.35.172
裏板の周囲から始まり数センチ程度の細いヒビであれば、ニカワでとめれば気にしないでいいですよ。音にも影響ありません。古い楽器などでよく見るのは、ネックが取り付けられている裏板の出っぱった部分の両側、顎当てが取り付けられているあたり、のクラックです。
ただ、魂柱(表板側の右側F字から覗くと中に立っている柱)が立っている位置のクラックだけは、簡単には修理できるものではありませんので、買い替えた方がよいでしょう。
工房の方はそのヒビに対しどのようにコメントしていましたか? 気になるようなら直接確認してみてはどうでしょうか。
また、今使われている楽器がよいものであれば、コンクール前に慣れないものに換えるのは逆効果のように思います。
投稿者:そら 投稿日時:2005/07/23 22:49 ---11.162.48
弦喜さん、有難うございます。
ヒビは魂柱から1センチほどの場所にあり
裏板の中央付近を縦に走っています。
先生を介して修理に出したので
工房の方からは詳しいお話が訊けなかったのですが、
「第三者(聴く人?)には特に音の違和感はないだろう」と
言うことでした。
コンクール前ということで、一応その言葉を信じ気持ちを
落ち着かせているのですが、ヒビを見る度
ハァ・・・とため息をついてしまいます。
このヒビは調整時に分かったものなのですが、
調整してからは数段音がよくなっているので、今の時点では
ヒビによる影響は無いかなとは思っているのですが・・・
工房も明日は休みなので明けにでも確認してみようかと
思います。
Q:楽器について教えてください
投稿者:と 投稿日時:2005/07/15 20:38 ---165.127.185
こんばんわ。チェロ初級者の「と」と申します。
最近、楽器を購入しました。古いチェロで、お店の方によると少なくとも戦前のものでしょうとのことでした。楽器の中にラベルが貼ってあって、
Ferd. Kessler
Markneukirchen
と記されています。いつごろのどのような方だったのか、もしわかりましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
投稿者:ストラッド店員 投稿日時:2005/07/20 11:56 ---205.237.40
こんにちは、
Kesslerという弦がございますが、Kesslerというドイツの作者も何名かおります。
Ferdという名前のKesslerさんは見つけられませんでしたが
Friedrichさんというのが資料にのっていました。
もしかしたら全然関係ないのかもしれませんが・・
非常に短い文で
1774年生まれ 1850年死亡 Markneukirchenで働く
Branded C.F.K
なので、直訳するとC.F.Kの商標を付けられている。
それでは!
投稿者:と 投稿日時:2005/07/20 15:43 ---139.23.107
ストラッド店員様
お忙しい中、調べていただいてすみません。ありがとうございました。
投稿者:goett 投稿日時:2005/07/22 21:13 ---181.17.104
「Branded〜」はここでは、「〜の焼印が押されている」と解釈するのがベターと思います。
なお、Ferd.はFerdinandの略です。
投稿者:と 投稿日時:2005/07/23 13:18 ---139.23.107
goett様
情報ありがとうございました。私のチェロには焼印ではなく、小さな紙が張ってあります。いつごろ作られたものなのか興味を持ちましたので....。ストラッドの店員様が調べて下さったように、Kesslerという銘柄(とでも言ったらよいのでしょうか)は実際にあるようで、
http://violine-online.de/gesch.htm
私が購入したチェロはその類縁の工房の量産モデルなのかしら?と考えています。
それでは。
Q:バイオリンの価値
投稿者:弓削容子 投稿日時:2005/07/21 13:16 ---3.52.219
アメリカのニューヨークに住んでいる主婦です。娘が5歳からバイオリンを習い、今7歳です。先月、先生所有のバイオリンを貸して頂けることになり、そのバイオリンで毎日、練習をしています。先生のとても貴重なバイオリンだと聴きましたが言語の問題もあり詳しくは、聞けなかったので教えて頂きたいのです。バイオリンのラベルには、Rudoull Doetsch No.1519 COPY OF STRADIVARIUSU specialQuality Hand Vhrnishと書かれています。サイズは4分の1です。ジュリアード大学に入ったような子たちが今までは、使っていました。このバイオリンの価値を教えていただけるとありがたいのですが。
投稿者:rio 投稿日時:2005/07/21 14:52 ---9.138.39
>Rudoull Doetsch
Rodoulf Doetsch ならWeb検索でHITします
http://gviolins.com/pricelist/ $875 (1/4 Out Fit)
http://www.atlantastreetviolins.com/prod01.htm $1050(1/4 Out Fit)
http://johnsonstring.com/catalog/doetsch.htm#14vn $850(1/4 Out Fit)
もし、Rodoulf Doetsch なら
イメージとしては、新品・弓・ケース付で
US$1000.00 ぐらいだと想像できます
Rodoulf Doetsch というブランドで
製作年度が記載されていなければ
おそらく工業製品(量産品)の楽器ではないかと思います
投稿者:容子 投稿日時:2005/07/22 02:02 ---3.52.219
早速の返事ありがとうどざいます。大変助かりました。新品ではなくかなり、古いもので先生は、この音が結構、好きだとおっしゃっていました。古いものの価値は、どのように決まるのですか?たびたびすみません。
投稿者:ストラッド店員 投稿日時:2005/07/22 10:43 ---102.21.236
こんにちは、
>古いものの価値は、どのように決まるのですか?
価値と言ってしまうと、人それぞれの価値観がございますので、ある人には価値があっても、違う人には価値がないということもございますので、一般的な「相場」という言葉に置き換えてお答えいたします。
これは非常に単純です。古いものに限らず需要と供給のバランスによって相場は決まっていきます。
数が少ない楽器で欲しい方がたくさんいると相場は上がります。
Stradivariusやdel Geseの真作などが現在の相場になっているのもこの原理が働いている為です。
逆にいいものでも数がたくさんあれば、それほど相場は上がりません。また数が少なくても欲しがる方がいなければ相場は上がりません。
それでは!
投稿者:rio 投稿日時:2005/07/22 14:03 ---9.138.39
たびたびすみません。
以下私見を書かせていただきます。
楽器のラベルに「Hand Vhrnish」とわざわざ書かれている
ということは、楽器の製造メーカーが
「普段は機械・スプレー塗りのニスを、わざわざ手塗りにしたんですよ」と表現したいということが伺われますので、楽器そのものは何万ドルもするような楽器ではなく、量産品の上級品という感じがいたします。
経験上、1/2ぐらいからバイオリンらしい音がしますので、短期間しか使わない分数の1/4にはお金を投資することをあまり聞きません。私は、分数は、良い音がするにこしたことはないですが、それよりも、きちんとしたサイズ・作りであり、技術向上の妨げにならないというのが重要と考えています。
おそらく先生は、弓削さんのお子様の成長を確実なものにするため、これまで、The Juilliard Schoolに進学した教え子達が使ってきた、サイズ・作りが理想的で、運気の宿った楽器ということで「とても貴重だ」といっているのではないでしょうか?
古いということですから、何人ものお子様がこの楽器を弾き、目覚しく上達し、The Juilliard Schoolに入学されたのでしょう。次は弓削さんのお子様の番なのだと思いますよ。
投稿者:容子 投稿日時:2005/07/23 02:00 ---3.52.219
丁寧な回答をありがとうございます。海外にいるため色々と専門的な話になると聞くのも難しかったのでこのサイトとっても感謝しています。また投稿させてください。質問の回答、とてもわかりやすく理解できました。
Q:ドミナントが一番美味しいのは、、、
投稿者:ヤパ 投稿日時:2005/07/21 21:03 ---145.51.224
娘の3/4のヴァイオリンにドミナントを張っています。
娘が言うには、いい音がするのは3日で、あとはあまり変わらないと言います。
当方が聞いていると3週間くらいで全く生彩がなくなります。
弦を張り替えた直後は、伸びるまで調弦しにくいのですが、、、これといった日の何日前に貼りかえるのがいいのでしょうか?
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/07/21 21:41 ---6.34.147
日々の演奏時間により、結果は異なるように思います。
あくまでも参考情報として私の場合を書きます。(4/4のヴァイオリンの例です。)
私は平日は楽器に触れる状況にないウイークエンドプレイヤーです。
演奏会も大抵土日にあるので、ドミナントの場合は、本番の一週間前の金曜か土曜に張り替えます。そして一週間前の土日は大抵5〜6時間弾く場合が多いです。弦が伸びることによる音程の不安定さはその日曜時点でもまだ少し残っているように思います。そして次の週の平日は、弾く時間は持てませんが、音程が下がっているときに調弦だけします。次の土曜時点で音程はかなり安定しており、その日ある程度弾き込めば、その晩の本番は弦の伸びによる音の下がりに煩わされないで演奏できるように思います。
また、感覚的な私見ですが、日々もっと演奏する人なら、三日くらいで弦の伸びは安定するのではないでしょうか。
ですから、音色劣化と音程安定のバランスを考えた上での私のおすすめは、4日〜1週間(練習の状況に応じて)前です。
投稿者:ヤパ 投稿日時:2005/07/22 08:55 ---224.218.130
弦喜さん、ありがとうございます。
音色の劣化は、張ってある時間よりも、弾いた時間に関係するのですね。
張ってある時間が、劣化(音色劣化)と伸び(音程安定)の大きな要素かと思っていました。
勉強になりました。
投稿者:弦喜 投稿日時:2005/07/22 22:54 ---6.34.16
>張ってある時間よりも、弾いた時間に関係
というのは、ちょっと違う気がします。
張ってある時間と、弾いている時間の双方が関係します。
張っている状態では、ほぼ一定の力で伸ばされます。
弾いているときは、
・弦が強制的に引っ張られる
・弦の振動で刺激される
・ナット、駒での接点前後での圧力不均衡が上記刺激で若干是正される
・調弦を演奏の途中で行うので、伸びた分さらに巻き取られる
・駒の傾きなども、都度調整する
などにより、伸びが加速するとともに音程は早く安定方向に向かうような気がします。
あくまでも感覚的な話ですが...
Q:C. H Jin
投稿者:tara-chan 投稿日時:2005/07/21 13:11 ---41.54.148
こんにちは。私は9さいの女の子です。
兄のviolinの製作者C. H Jinについて
教えてください。ラベルには次のように書かれています。
C.H JIN in Tokyo
facitbat Anno 1969 APPoY0.11
マークもあるのですが書けません。
中国人の方らしいのですが.......。
とても興味があるのでお願いします。
投稿者:ストラッド店員 投稿日時:2005/07/21 15:12 ---102.19.162
こんにちは、
恐らくJin Chang Heryern(陳昌鉉)さんのラベルだと思います。
当店では、面識もなくお会いした事もないので詳しい事は解りませんが、自伝などをお書きになって大変有名な方です。
「陳昌鉉」さんで検索サイトで検索をしてみてください、物凄い量の情報を見る事が出来ます。それでは!
投稿者:tara-chan 投稿日時:2005/07/21 18:19 ---41.54.148
ありがとうございます。
とてもビックリしました。violinが大好きで習いたいと何年も頼んだのですが......
そんな時、兄が自分のviolinで私に教えてくれました。
大きくて、重くて大変だったけど初めて触れたviolinとtoneの
感激は一生忘れません。
今、1/2のviolinで習っています。陳さんのviolinを弾けるくらいふさわしい人になりたいです。
ところで、いくらぐらいするのですか?10数年前に100万で
譲られたそうです。
よろしくお願いします。
投稿者:ks 投稿日時:2005/07/21 19:33 ---98.106.243
数年前に某オークションで60万円で落札されていました。製作年代も同じくらいです。参考までに。
投稿者:酔いどれ船 投稿日時:2005/07/22 14:51 ---127.68.69
9歳の女の子にしては、難しい漢字も使い、(ワープロですから可能なのかもしれませんが)toneという英語まで使い、大したものですね。ただ、お嬢さん、ヴァイオリンを愛するのは良いのですが、この年齢で、余りお値段などに関心を持たない方が良いと思います。
Q:肩当ての位置と鎖骨の形との関係について
投稿者:LEMON 投稿日時:2005/07/21 13:15 ---97.106.168
こんにちわ。
肩当てと鎖骨の形に関係があるか教えてください。
こちらのサイトで構え方を教えて頂いてから、時々バイオリンを構えて鏡の前で確認するようになりました。そのあとテレビで俳優さんを見ていて気がついたのですが、鎖骨の形が人によってずいぶん違うように思いました。
私は、体の中心から肩の方に向かって鎖骨が上がっていますが、俳優さんはほとんど平行でした。それから気になるようになって、気をつけてみていると、中心から肩方向に上がっている人と、ほとんど平行の人があるように思います。そのことと肩当てをバイオリンにつける位置や角度は、関係はないのでしょうか?
私は、バイオリンの一番広いところに、左右対称につけていますが、それでいいのかも含めて教えて頂けたらと思います。よろしくお願いします。
投稿者:QB 投稿日時:2005/07/21 16:06 ---9.46.177
文章で表すのは非常に難しい問題です。
もし先生に師事されているのであれば、先生からアドバイス受けていただくのが一番です。
鎖骨の形や位置と、肩当のパッドの形状や装着の位置とが全く無関係とは思いませんが、文章で一般化できる物でもないように思います。
また、人によっては、結果的に肩の運動が抑制されても安定していることをよしとする人(肩当パッドが大きめで鎖骨の肩側の付け根に乗っている状態)や、より柔軟な肩や楽器の動きを良しとする(肩当パッドが小さめで、むしろ鎖骨の上に乗る)人、様々ですし、夫々の理論や目指すところがあります。。。
まして、3次元の話なので、、、
と言うわけで、先生にまずご相談されるのがよろしいかと思います。
投稿者:LEMON 投稿日時:2005/07/22 13:16 ---122.55.17
QBさん、ありがとうございました。
<人によっては、結果的に肩の運動が抑制されても安定していることをよしとする人(肩当パッドが大きめで鎖骨の肩側の付け根に乗っている状態)や、より柔軟な肩や楽器の動きを良しとする(肩当パッドが小さめで、むしろ鎖骨の上に乗る)人、様々>
安定感のことばかり頭のあったので、鎖骨の形と肩当てに相関関係があるのかと思いました。文章で一般化できるものではない・・・ですよね。ありがとうございました。
Q:これは何者?
投稿者:弦二 投稿日時:2005/07/19 05:36 ---107.155.175
いつも楽しく拝見させていただいています。
Nicolaus Gagliano Fasibat Cremona Anno 1837
こんなラベルの楽器があるのですが,1837年にクレモナで作られたことは推測できるのですが,そのほかについては全く見当がつきません。
見た目は相当に古そうなのですが,この作者というのはどんな人なのでしょう?単にガリアーノのコピーかな,とも思うのですが,ご教示いただけると幸いです。
投稿者:cremona2号 投稿日時:2005/07/19 08:59 ---2.36.144
確か二コラはクレモナで修行したことは無かった筈です。それにラテン語が間違ってますので余りイタリア語やラテン語に精通していた人ではないように思えます。従って弦二郎さんのバイオリンの作者を文章だけでお答えするのは難しいと私は思います。
二コラ・ガリアーノは(手元の新しい資料では)1730-1787のナポリの作家です。1837年の時点ではガリアーノファミリーはラッファエッロとアントニオが活躍していたようです。そしてもう一人の二コロも存在していたようですが、1825年までなのでこの人ではないようです。
投稿者:弦二郎 投稿日時:2005/07/19 09:48 ---227.0.250
>>cremona2号さん
そうですよね・・・。ナポリの作家ですよね?
確かにfasibatという綴りはfaciebatではないかと思います。
確か以前こちらの質問コーナーに
http://www.strad.co.jp/cgi/qasearch.cgi?mode=view&code=7271&re=&key=ガリアーノ
というのがありました。
この中に
>>ヴァイオリン製作者→分業による家内工業→楽器工場→弦メーカーと変遷?しますので....
とあったことも考えると,何だか微妙な気配...
やはりコピーと考えるべきですかね...
投稿者:弦二 投稿日時:2005/07/22 07:29 ---107.155.175
いろいろ確認してみたところ,コピーらしいことが判明しました。
cremona2号さんをはじめ,みなさんありがとうございました。

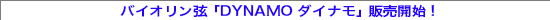
Q:これからはイタリアモダンの時代でしょうか
投稿者:ks 投稿日時:2005/07/23 00:41 ---98.106.243
オールドについてはとても手が出ないわけですが、コンテンポラリについてはクレモナ産で皆同じような音がして魅力ないです。楽器店をまわって弾かせてもらってもみな同じような鳴り方です、悪いわけではないですが。先日イタリアモダンに属する楽器を3点ほど弾く機会を得ました。非常に個性的で魅力がありました。コンテンポラリの楽器は平均的には良いのでしょうが皆おなじかんじがしました。非常に主観的な意見ですが一般論の意見をご教授ください。
投稿者:rio 投稿日時:2005/07/23 04:39 ---29.242.228
Contemporary の 製作地Cremona が 同じようで魅力がない?
確かに似ているところは私も感じます。デザインや仕上げ方が皆さんなんとなく似ている。それでも微妙に作者の個性は見えると思います。
イタリーならばメジャーな次の地域の楽器はどうだったでしょうか?お試しになりましたか?
Milano
Firenze
Mantova
Roma
Venice
Genova
Cremonaにこだわらなければ、個性的な楽器は多く見られると思います。
お試しになった、モダン3点もすべてCremonaだったのでしょうか?
投稿者:rio 投稿日時:2005/07/24 23:32 ---29.242.228
(すみません中途半端で答えになってませんでした)
現在Modernとして販売されているもので、
私たちが興味を持つものの多くは
Fagnola、Antoniazzi、Bisiach、Lecchi、Rocchi、Garimberti、Ceruti、Pedrazzini、
などなど、名工として評価されてきた方々の遺作です。楽器による差はあるにしろ、高いレベルの作品ばかりなので、個性もありかつ魅力的な可能性が高いと思います。
更に、経年変化という味付けがなされているので、魅力は倍増でしょう。
それに対し、Contemporaryの中の多くは、これから市場の評価が決まる製作家も多くいます。Contemporaryの楽器が玉石混合ということを考えれば、ksさんの感じるところは、ごく一般的な判断だと思います。
投稿者:ks 投稿日時:2005/07/25 01:41 ---98.106.243
弾いたイタリアモダンの楽器はフェラーラ、ナポリ、ミラノ、の製作かのものでした、評価もある程度きまっているもので良いのあたりまえかもわかりません。1920年代でしたので年代的にもちょうど良い年代なっているのでしょう。コンテンポラリーはすべてクレモナに工房をもっている製作かでした。他の製作かの楽器を弾けば印象がかわるかもしれません。コンテンポラリーでも良いものはいのでしょうね。私の主観的ないけんでした。