弦楽器 Q&A
弦楽器に関するいろいろな疑問にお答えします。
2023年12月31日をもちまして、新規投稿・コメントの書き込みを終了させていただきました。
5203件のQ&Aがあります。
Q:チェロの弦について
投稿者:ハンナ 投稿日時:2001/11/04 21:12 ---
チェロの弦にはいろいろあるようですが、大体色はシルバーですね。
ところが、ある弦楽器の展示会で、銅色の弦が張ってあるチェロを試奏する機会がありました。
少し、ザラザラしたハスキーな音がしてましたが、なかなか私の好きな音でしたので、自分のチェロにも試してみたいと思います。
その時に訊ね忘れてたので、どの会社の弦なのか分かりません。
もし、ご存じの方がおれらましたらお教えいただけませんか?
因みに、GとD線に張ってあって、その新作イタリアチェロは渋い音がしました。
投稿者:ストラッド店主 投稿日時:2001/11/05 16:44 ---
こんにちは、ハンナさん。ストラッド店主です。
楽器の展示会って弦楽器フェアですか?それなら私もいきました。
でもチェロの弦にはきずきませんでした。
銅色の弦ですか?トマスティック社のベルカントの弦が銅色だったかな?ちょっと自信がありませんけれど、確か昔のベルカントは銅色だった気がします。
それ以外はちょっとわかりません。誰か知っている方おりましたらお願いします。
それでは!
投稿者:ヴィヨーム 投稿日時:2001/11/05 18:26 ---
Belcantoの普通の弦は使用したことがないので、残念ながら弦の色は判りませんが、Belcanto GOLDは名前の通り、金色の弦です。カタログにAlloyと表示されているとおり巻線は合金です。とある楽器店で伺ったところ、NASAで精製方法が開発された合金とのことでした。多分、アルミニウムと真鍮が含まれているのではないかと思います。音が良いので私も昨年から使用しておりますが、難点は、上記のとおり、真鍮が含まれているためか、手に緑青のようなものが付着すること、他の一般的な弦に比べて、汗や脂のために弦の表面が特にカサカサになりやすく、こまめに弦を拭かないでいると、突然、演奏中に巻線が切れることがあります(本番中に巻線が切れたこともありました…)。私の場合、A線とD線の寿命は3〜4ヵ月といったところです。また、非常にブリリアントな音のする弦で、少し暗めの音やこもった感じのする音の楽器には効果てき面ですが、楽器の調整が良くないと、A線などが却って神経質な感じになってしまう感じもします。いろいろ難点もあるのですが、音には代えられず使用している次第です。特にオールドの楽器には合うと思います。以上、あくまで私見ですが、参考になさってください。
投稿者:ハンナ 投稿日時:2001/11/05 21:24 ---
そうですか、ベルカントというのですね。
私のチェロでどんな音がするのかたいへん楽しみです。
店主様、ヴィヨームさん、ご親切にありがとうございました。
Q:欲しいと思っている楽器について教えてください
投稿者:rio 投稿日時:2001/10/27 02:05 ---
LUCA PRIMON というイタリアのミラノに住んでいる製作者について教えてください。
たまたま、都内の楽器店で試し弾きして、音がとても気に入った製作者名です。
たまたま、その店にあったのが、スタイル・色が、典型的なデルジェス型の色も黄色っぽい色で、好みではありませんでした。
ストラドタイプで、色は赤〜オレンジが好きなので、今捜しています。
都内の楽器店を回るたび、「聞いたことありませんね、調べてみます」と必ず言われ、あまり知られていない名前のようなので、情報が欲しいのです。相場は150〜250万円ぐらいなのでしょうか?
投稿者:ぽこ 投稿日時:2001/10/29 01:42 ---
僕は弾いたことがありませんが、以下のサイトに持っている方の体験記が書いてあります。
http://www3.famille.ne.jp/~chelsea/violin/top.html
violin concertという大人になってからバイオリンを始めた体験記が書いてある、とっても楽しいサイトです。
投稿者:rio 投稿日時:2001/10/29 02:56 ---
ぽこさんへ
ありがとうございます。さっそくサイトを見ました。
1987年製製作地TRENTOなんですね。
私が試し弾きしたのは
2000年製製作地MILANOでしたので
この間に彼は引っ越したのでしょう
貴重な情報ありがとうございます
rio
投稿者:ストラッド店主 投稿日時:2001/10/29 10:58 ---
こんにちは、ストラッド店主です。
最近ダヌーツさんのコンサート関係で忙しいのでなかなかここにこれません。
申し訳ございません。
LUCA PRIMONさんですね、私も知らなかったので調べてみました。
1952年生まれのかたですね、いろいろ書いてありますがイタリア語なので意味がチンプンカンプンです。あ、ダヌーツさんが来たので訳してもらいましょう。
トレノ生まれ、彼の師匠はScrollavezzaです。違う師匠はJurgen Steitenkronです。
1979年から1982年にオーストリアに在住しいろいろな賞を獲得しました。
彼はスペシャルなコントラバスを作成しました。また弓などもたくさん作りました。
1986年には、とても大きな賞をもらっています。
彼の楽器は作りもよく材料もいい、そしてニスもいい。
本にはいいことが書いてありますね。私もコンテンポラリーはクレモナより、その他地方で作られたものが個性的で好きです。
投稿者:rio 投稿日時:2001/11/01 00:06 ---
ストラド店主さま
貴重な情報ありがとうございました
緊急に手に入れなくてはいけないものではないので
気長に楽器店回りをしようと思います
Q:私のチェロについて
投稿者:チェロ弾き 投稿日時:2001/10/29 23:09 ---
私のチェロのことで質問があります.
イタリアの新作ということで購入し,1994年のラベルが付いており,かれこれ6年弾いていますが,いまだにニスがべたべたしています.楽器の表面は指紋,服の跡,ケースの跡,ほこりなどがつきやすく,布で拭いてもあまりきれいにとれません.特に湿気の多いところにおいているつもりはないのですが,やわらかすぎるニスが使ってあるのでしょうか.そして,これは楽器が良くないと言うことなのでしょうか.音を損なうことなく改善することができるのでしょうか.教えてください.
また,ネックと本体のつなぎ目のあたりに,接ぎ木がされている線が見えます.オールドならまだしも,新作でこのような処理をすることがあるのでしょうか.楽器にとってマイナスのような気がするのですが...
ラベルにはGIANNI MOTTAと製作者が書いてありますが,この人についてわかることがありましたら,あわせて教えてください.(何歳くらいの人か,どれくらいの技術レベルの人かなど.)
楽器の音は気に入っているのですが,見た目にこのように気になる点があり,すっきりしないのです.
よろしくお願いします.
投稿者:ストラッド店主 投稿日時:2001/10/31 11:54 ---
いらっしゃいませ、チェロ弾きさん。ストラッド店主です。
GIANNI MOTTAさんですが、調べてみたのですが当店の資料にその名前を見つけることは出来ませんでした。すいません。
ニスに関してはやわらかい物を使っているのだと思います。なぜやわらかいニスを使ったのかは作った本人にしかわかりません。だからと言って楽器が良くないとは一概に言えません。まあ詳しいことは見てみないと解らないです。
ニスの塗り替えは可能ですが、音を損なうことなく改善できるかどうかは、やってみないと解らないです。
>ネックと本体のつなぎ目のあたりに,接ぎ木がされている
新作でもあります。作る過程において必要になったっと考えられます。
ただ、想像ではいろいろ考えられますが正確なところはこれも見てみないと解らないです。それでは!
投稿者:Sprungli 投稿日時:2001/10/31 12:59 ---
GIANNI MOTTA作のチェロということですが、「よしけん」さんが持っておられるものと同じではないかと思います。
http://plaza18.mbn.or.jp/~yoshiken/music/vlc/vlcinst.htm
にアクセスしてみてください。
投稿者:チェロ弾き 投稿日時:2001/10/31 22:18 ---
店主様,Sprungli様,ありがとうございました.
どうやら,無名の制作者のようですね.
でも,しっかり弾きこんで,私の子孫が自慢できるような楽器に育ててみようと思います.
Q:楽器の雑音について
投稿者:バルビローリ 投稿日時:2001/10/28 02:07 ---
こんにちは。
質問させていただくのはこれで3度目です。いつも丁寧に回答してくださり、感謝しています。
今メインで弾いているチェロに雑音が出るので心配です。
非常にややこしい話になり恐縮ですが、結構気になるので質問させていただきます。
雑音といっても絶えず出ている訳ではなくて、ある条件下で発生します。
気になりだしたのは2〜3週間ほど前からで
G弦の第四ポジションでESの音を2の指で押さえて弾くと、ビリビリという弦が指板にあたって
こすれているような雑音が出ます。ただし、2の指だけでES音を弾くときは大丈夫で1の指を
G弦の第四ポジションのDに置いたまま2の指でES音を弾くとビリビリという音を伴います。
ピッチをかえても同じ位置で同一の症状がみられ、念のため弦の種類を変えて試しても
同じでした。またG弦以外では(この条件を左右に平行移動して試しても)発生しません。
ちなみにネックの角度は正常で、指板と弦との間隔も標準の範囲内と思われます。
このときよく観察してみると、雑音が出ているのは、弓で弾いて振動している2の指から駒まで
の部分の弦ではなく、どうも押さえている指より上の部分の弦が共鳴?して雑音を発しているようなのですが・・・・・
つまり添えて押さえている1の指からナットまでの弦がビリビリと音をたてているようなのです。
楽器は新作で、弾き始めて約十ヶ月になります。
このような症状は調整で改善されるものなのでしょうか?
文章だけで状況をお伝えするのはむつかしいと思いますが、修理・調整のご経験に照らして
何か思い当たることがあればアドヴァイスいただけると、幸いです。
お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
投稿者:かめ 投稿日時:2001/10/28 08:05 ---
もしかすると、ナットの部分が高さが合っていないのかも知れません。
となると、ナットを含め指板を削る調整が必要になります。
結構、指板がきちんとした角度で削られていない楽器が多く、ナットなどの
高さも有っていない楽器もあるようです。
僕がお世話になっている工房の人などは、制作する人と調整する人は別、とまで
言っています
僕のチェロも、別の音ですが、以前似たような症状がありました。
指板などの調整をした結果、改善されています。
投稿者:シュタルク 投稿日時:2001/10/29 03:44 ---
バルビローリさん
ウルフ音ではないかと、思うのですが・・・。
ウルフ音は、
楽器本体の固有振動周波数と、G線のその音域の周波数とが
隣接するために生じる唸りです。ウルフキラーという一種の
重石をつけて、その周波数成分を減衰させたり、魂柱と駒と
の距離を変えて、目立たなくすることはできます。良くなる
楽器はウルフ音が目立つとも言われています。
ただ、
>2の指だけでES音を弾くときは大丈夫で1の指をG弦の第四
>ポジションのDに置いたまま2の指でES音を弾くとビリビリ
>という音を伴います
という現象は、ウルフ音だけでは、ちょっと説明が付きません
ねぇ。
投稿者:ストラッド店主 投稿日時:2001/10/29 11:08 ---
こんにちは、バルビローリさん。かめさん、シュタルクさん、書き込みありがとうございます。
今回の問題ですが、いろいろ想像することは出来ますが、正解は見てみないと解りません。
ちょっと文章だけでは難しいですね。もしお近くでしたら一度お持ちください。
それでは!
投稿者:バルビローリ 投稿日時:2001/10/29 22:38 ---
かめさん。シュタルクさん。書きこみありがとうございます。
ご親切に感謝します。
シュタルクさんのおっしゃるように最初はウルフ音かと思ったのですが、どうも違うようです。
ウルフ音はいままで何本かの楽器でさんざん悩まされ、ウルフキラーも幾つか購入しました。
それとは音の感じがまったく違うのです。
とにかく近いうちに一度お伺いしてみます。
家が遠いので、大変ですが、大切な楽器には替えられませんので。
ストラッドさん、よろしくお願い致します。
Q:ペグについて
投稿者:seri 投稿日時:2001/10/25 03:45 ---
こんにちは、初めまして。いつも楽しく拝見させていただいてます。
ところで、先日思い切って二十万円台のヴァイオリンを購入しました。その
楽器のメンテナンスについての質問なのですが、ペグが固くて困っています。
買ったばかりの新しい楽器だからかな、と思うのですが、本を見ながら調弦
をしようとしたところ、とても動きません。(壊れてしまいそう!)
前回のレッスンで先生に回してもらいましたが、自宅に帰った後、今度は逆
にペグが巻き戻ってしまって、ゆるゆるです。先生は「固いから、大幅に音
が狂ってなかったら無理に回さなくていい」とおっしゃっていたのですが、
家に帰ってちょっと回してみたら、ぐるぐると巻き戻ってしまってビックリ!
やっぱり触らないほうが良かったのか! と後悔しています。グスン。
次のレッスンで直してもらえるだろうけど、一週間このままではちょっと気
が落ち着かないです。(当然、練習もできないし……)自分で調節できる様
になりたいのですが……。
固いペグは、どうすれば柔らかくなるのでしょうか。
また、柔らかくなりすぎて固定不能なペグは、どうすれば元に戻るでしょう。
あまりに初歩的な質問で申し訳ないのですが、ペグの良い扱い方をご存知の
方、ぜひアドバイスをお待ちしています。
投稿者:ぽち 投稿日時:2001/10/25 08:48 ---
自分でいじる方法としてはコンポジション、または
チョークと石鹸で調整するのが一般的のようですね。
動きにくいペグは古くてかちかちになった石鹸を
ペグの回る部分にチョンチョンとつけてすべりを
よくします。逆にすべってしまうときはチョークを
チョンチョンとつけます。
ペグ調整の道具としてあるのがコンポジションです。
茶色い、クレヨンみたいな物で楽器屋さんで売って
ます。1000円ちょいぐらいだったと思います。
コンポジションは1本で石鹸とチョークの役をする
ものらしいです。
それでも駄目なら、やっぱり調整に出した方が
いいかも知れませんね?
投稿者:ストラッド店主 投稿日時:2001/10/25 10:58 ---
いらっしゃいませ!seriさん。ぽちさんもご回答ありがとうございます。
後半の答えはほとんどぽちさんが答えていますね。
調弦は最初の内は難しいですよね。でもご自分で楽器を扱っていってなじませる事によってだんだん使い勝手が良くなると思います。ぽちさんが答えてくれた方法などももちろん有効です。
ただ先生が調弦できるのですから、調整が必要だとは思いません。先生も出来ないとなるとこれは調整が必要です。
調弦もバイオリンのテクニックのひとつです。どんどん身についてくると思いますので頑張ってください。それでは!
投稿者:seri 投稿日時:2001/10/28 07:38 ---
ぽちさん、店主さん、お答え有難うございました!
>チョークと石鹸
全く知らなくて初耳でした。どうにも勉強不足のようです。
昔の人も、こういう身の回りにある道具でヴァイオリンの調節をしていた
んでしょうね。なんだか、とっても意外で、かつ納得いたしました。
チョークはなかなか手に入らないので、コンポジションというのを探して
みようと思います。ありがとうございました。
>なじませる事
使っているうちによくなるのですね。あまり心配しなくて良さそうで、
ほっとしました。初歩的な質問にお答えくださり、ありがとうございました!
Q:教えてください。
投稿者:ミミ 投稿日時:2001/10/24 00:11 ---
私の持っている楽器の製作者のこととその作風の特徴などについて教えてください。
製作者はvincenzo cavaniで1967年製のものです。
1年程前、こちらのホームページでこの製作者の1930年代?くらいの楽器が200万前後で販売されていたように思うのですが、そこから考えると私の楽器は晩年の作品ということになりますよね?
同じ製作者が作った楽器でも作られた年によって、楽器の値段に大幅に違いはあるのでしょうか?もし、違うのであれば参考程度にどの程度違うのかを教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
投稿者:ストラッド店主 投稿日時:2001/10/25 10:44 ---
いらっしゃいませ、ミミさん。
ストラッド店主です。vincenzo cavaniさんですね。当店にあったvincenzo cavaniはとにかく音色が素晴らしかったですね。
>同じ製作者が作った楽器でも作られた年によって、楽器の値段に大幅に違いはあるのでしょうか?
大幅な値段の違いというのは無いと思います。また「作られた年」、というよりもやはり楽器の個体差の方が値段に反映すると思います。
私の感じ方では、全ての作者の晩年の作品の方が「音色」がいいものが多いと感じています。若い頃の作品は作りは綺麗ですが晩年の物に比べると音がちょっと落ちる印象があります。例外はもちろんありますが。
やはり経験が大切大切なんですね。
投稿者:ミミ 投稿日時:2001/10/27 11:58 ---
ありがとうございました。
言われてみれば、私の楽器は全体的に決して綺麗とはいえないですが、いたるところに
手作りらしさが出ています。
音も、深みがある音色がすると思います。これも、やはり製作者の経験や集大成が
作り出したものなんですね。
Q:楽器購入についてちょっとした質問です。
投稿者:T.O. 投稿日時:2001/10/26 03:19 ---
弦楽器について質問させてください。楽器の購入を考えています。
3つほど
・パーフリングというのはやはり削ってあるものの方がよいのでしょうか?
・杢がおおいと音がいいものが多いというのは本当ですか?
・今使ってるバイオリンの指板の弦のあたる部分が白くなってます?これは
安物だからでしょうか?
楽器は自分が気に入った音ならいいかなと思っているのですが、ちょっと気になったことです。
同じ質問があったら申し訳ございません
投稿者:かめ 投稿日時:2001/10/26 09:32 ---
1.パーフリングというのは、装飾の目的の他に、楽器の縁の部分の保護の
役割も持っています。ですので、ただ書いてあるだけの物よりかは
きちんと削ってある物の方が良いと思います。ただし、オールドの楽器の
中には書いただけの物もたまに見ることが出来ます。
2.杢のおおさと音は基本的には関係ありません。杢は美観としては楽器をきれいに
見せますが、音はやっぱり、最終的には材料の質と職人の腕で決まってきます。
杢がきれいだからと言って音が良いというような単純な結果にはならないと思います。
ただし、杢がきれいな楽器ほど買い手を惹き付ける部分はあると思うので、良い楽器に
仕上がっている可能性もあるかもしれません。
3.指板が白くなっていると言うことは木の地肌が見えていると言うことでしょうか。
そうしたら、その指版は木を黒く染めてあるという事ですので、黒檀以外の材料で
作られたか、もしくは材質の良くない黒檀で作っているということだと思います。
安い楽器の場合はコストを下げなければならないので、それも致し方ないことでしょう。
ただ、楽器を引きこんでいるうちに、汗や弦の巻線の参加などにより、弦が当たる部分だけ
少し変色してくる場合があります。この場合は、指版を削り直したりと言うことでまた
黒い指版に戻すことが出来ます。
投稿者:ストラッド店主 投稿日時:2001/10/26 10:58 ---
いらっしゃいませ、T.O.さん。かめさん。
かめさん完璧な答えありがとうございます。
特に補足する事はありません。
オールド楽器で確かに「書きパーフリング」のものを見ることがありますね。
それでは!
投稿者:T.O. 投稿日時:2001/10/27 01:13 ---
かめさん、店主さん返信ありがとうございます。
1.パーフリングは楽器保護の目的があるので削った方がよいが、音には
関係ないということですね。
2.杢があまり美しくない、少ないものでも最高級の材料というものはあるのですね。
ただ、美しい模様の方が売れやすいから作家もより丹精に作っている可能性があるのですね。
3.弦のあたる部分だけ少し白く変色?脱色?した感じなのです。安物でなければいいなあと
思ってます。
本当に丁寧に返信してくださって感謝です。もし間違った理解を私が書いていたら
直していただけるとありがたいです。
Q:私の楽器
投稿者:いちご 投稿日時:2001/10/19 19:47 ---
友人が思うように音が出ないので手放したいというので、譲り受けました。楽器のことがわからないので、どんな人が作ったのか教えてほしいのです。もう5年くらいひいてますが、私は結構いい音だと思うのです。気に入っています。ヴァイオリンはIginius Sderci 1973と書いてあります。弓はW.E.HILL&SONS ENGLANDと書いてあります。どんな情報でもいいので教えてください。ヴァイオリンには写真入りの保証書がついてます。弓は友人の昔の先生がイギリスでオークションで落としたそうで、保証書はついてません。どこのどんな人がつくったのだろうといつも思っています。よろしくお願いします。
投稿者:ストラッド店主 投稿日時:2001/10/20 17:19 ---
いらっしゃいませ、いちごさん。ストラッド店主です。
Iginius Sderci さんですね。この人はモダンイタリアンでも最高峰の方ですね。
1884年生まれイタリアのフィレンツェで活躍した方です。
1973年にこの方がご存命だったかは調べましたがちょっとわかりませんでした。
HILL&SONS の弓ですがこれはロンドンの有名な楽器商です。HILL&SONS ブランドは一本一本職人さんが手作りで製作した大変質のいいものを扱っております。ブランド名なので誰が作ったかはわかりません。当店にもありますが非常にい弓です。
それでは!
投稿者:いちご 投稿日時:2001/10/21 21:25 ---
ご親切にありがとうございます。
もしかしたらすごいお爺さんが作ったかも知れないですね。
友人には相性が悪かったようですが、私は気に入ってます。
教えていただき、幾重にもお礼申し上げます。
投稿者:ぽこ 投稿日時:2001/10/24 09:04 ---
sderciのはなしは以下のサイトに詳しくかかれています。
http://web.tiscali.it/hiraharaviolin/bn-koboroku.html#11sderci
これによると、1982年98歳まで生きていたようです。
今クロサワ楽器お茶の水店にsderciの楽器が390万で出ていました。
色は黄色の楽器であまり見た目はきれいでないのですが、とてもいい音がしました。
高くて買えませんでしたが。
投稿者:いちご 投稿日時:2001/10/25 19:13 ---
ぼこさん、ありがとうございます。
私の楽器は黄色っぽい色です。
保証書にはIginius Sderciと書いてあるので、お知らせいただいた情報(Igino Sderci)とは違うなあと思ったのですが、念のため楽器をもう一度見ました。
そうしたら、ラベルはIginiusなのに、その奥にヨタヨタしたボールペンらしき字で、Igino Sderciと書いてありました。(本体に)。
で多分これは、お爺さんの筆跡と思ったので、急に嬉しくなりました。
「欲のなさそうな、控えめな態度の人」
「年老いてからも自分の楽器を作るのを息子に手伝わさせるようなことをしなかった」
お人柄が、目に浮かぶようです。
これからもしっかり練習して、十分ひきこんで行こうと思いました。
本当にありがとうございました。
Q:ツゲの糸巻き
投稿者:rio 投稿日時:2001/10/22 01:23 ---
ツゲの糸巻きを糸倉に差し込む部分は、削って調整するので、
ツゲ本来の白い木地が出るので着色する人がほとんどです。
でも私は、着色しないほうが楽器本来の性能を発揮すると考えています。
これ正しいですか?
30年程前(小学生の頃です)、
当時の私にとって超高級なフランス製
J.B.Collin-M(多分裏板にラベルとは別のところに
サインがあったので本物?)
を使い始めたころ、
工房の人に、「糸巻きをツゲにすると糸巻き本体の寿命は短いけれど、
楽器本体をいためないし、調弦も楽だからから」
という理由で(せこい!)
糸巻きをツゲにしたとき、
工房の人から、
「着色は見た目は良くなるが
強度面・使いやすさで
マイナス要素が多いので木地が出たままにします」
といわれ、その後ずっと信じてました
最近の技術で糸巻きの性能を落とさずに、着色できる術があればぜひ教えてください。
投稿者:ストラッド店主 投稿日時:2001/10/22 16:25 ---
こんにちは、rio さん。ストラッド店主です。
>着色しないほうが楽器本来の性能を発揮すると考えています。
>これ正しいですか?
正しいと言われてますが、私自身はなんとも言えないです。私は何本も楽器を扱っておりますがほとんど差を感じた事はありません。明らかに違いが出ればそうするのですが、ほとんど一緒なので白木のまま使うという事はありません。
強度面、使いやすさも、正直申しましてほとんど影響がないと思っています。職人さんの立場から言うと1工程省けるので、安く仕上がる。手間がかからない。等のメリットがあります。
ペッグの調整は技術的に大変難しく、職人さんの腕の見せ所でもあります。白木である、ないより職人さんの腕の方がはるかに影響を及ぼします。信頼のおける職人さんに頼むのが一番間違いがないと思いますよ。それでは!
投稿者:rio 投稿日時:2001/10/22 18:18 ---
STRAD様
Ans.ありがとうございました
そうですよね、プロはほとんどの方が
染めているのですから…
これで、長い間の疑問がはれました。(^o^)丿

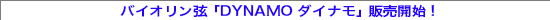
Q:楽器の中の埃
投稿者:もい 投稿日時:2001/11/03 21:07 ---
バイオリンの中にもやもやした埃が見えますが、どうやって取り除いたらよいのでしょうか。自分でできる方法を教えてください。
投稿者:ゆりか 投稿日時:2001/11/04 21:16 ---
お米を一握りF孔からいれて、ゆっくり振って埃と馴染ませて孔から出すという方法が一般的ではないでしょうか。
もちろん、生米です(笑)。
投稿者:ストラッド店主 投稿日時:2001/11/05 14:26 ---
こんにちは、もいさん。ストラッド店主です。
ゆかりさん素晴らしい答えありがとうございます。
欧米では大麦を使いますね。でも日本ではやはり米です。内部にホコリの塊が出来ると音が不明瞭になったりすることがありますので、ピンセットなどで塊は取れます。それでは!
投稿者:もい 投稿日時:2001/11/06 16:12 ---
ゆりかさま、店主さま、教えていただいてありがとうございました。
何か方法がある、と聞いたような気がしていましたが、はっきりと分からなかったのでお尋ねしてみました。さっそくやってみます。結構たくさん見えるので取れるのかな、と心配ですが。ケースに入れていつもしまっているのですけど。
入れたお米は全部、出てくるのでしょうか。